2020/12/21
長江貴士 元書店員
『素数の音楽』新潮社
マーカス・デュ・ソートイ/著 冨永星/翻訳

数学において「整数論」は「数学の女王」と呼ばれている。その「整数論」で最も重要なのが「素数」と呼ばれるものだ。
「素数」とは、「自明な正の約数(1 と自分自身)以外に約数を持たない自然数」である。もっと簡潔に表現すれば、「正の約数の個数が 2 である自然数」となる。具体的に書くと、「2,3,5,7,11,13…」となる。
「1」は素数ではないのか、と疑問を抱く人がいるかもしれないが、「1」は素数ではない。それは、「素因数分解の一意性」に関係している。数学が嫌いな人には、「因数分解」という言葉にアレルギーを抱く人も多いかもしれないが、「素因数分解」というのは、ある数字を素数の掛け算で表記することだ。「9=3×3」「28=2×2×7」のようなものが「素因数分解」である。「一意性」というのは「一つに決まる」という意味だ。
さてここで、「1」が素数だった場合どう困るのか説明しよう。先程「素因数分解」というのは「素数の掛け算で表記すること」と書いた。つまり、「9=3×3」ということだが、「1」が素数の場合、「9=1×3×3」とも、「9=1×1×3×3」とも表記出来てしまい、「一意性」が成り立たない、つまり一つに決まらない、ということになってしまう。これでは、数学を扱う上で非常に不便なので、「1」は素数ではない、と決まっているのだ。
そんな「素数」が何故数学において重要なのか。それは、素数を使えばあらゆる数を作り出せるからだ。先程の「素因数分解」の逆をやるイメージをすればいい。素数を掛け合わせる組み合わせを無数に変えれば、無数の数を作り出せる。素数の表は化学における元素の周期表のようなものなのだ。
しかし、この数学の根本を成す素数というのは、非常に扱いが難しい。というのも、数学という学問においてはパターンと秩序を見つけることが大事なのだが、素数がどんな規則によって現れるのかは、未だに誰も分かっていないのだ。どんな規則も、素数の列から見出すことは難しい。あらゆる数学者たちが、2000年以上に渡って努力を続けてきたにも関わらず、である。また、「双子素数の予想」や「ゴールドバッハ予想」など、素数に関係する未解決問題も多く存在する。
また素数は、数学という閉ざされた領域だけで重要なのではない。例えば、地球外生命体と意思の疎通をする際には、素数が使われると考えられている。知能のある生命体であれば、言語体系に依らず素数のことは理解できるはずだ、という想定に基づいてのことだ。実際、1974年に地球から約25,000光年の距離にあるヘルクレス座の球状星団 M13 に向けて送信された「アレシボ・メッセージ」は、地球外生命体が「素因数分解」を理解できる、という前提で作られている。
また、僕らの生活に身近なところでも、素数が重要なものとして使われている。クレジットカード情報などを暗号化するRSA暗号という仕組みは、「巨大な数を素因数分解するのには膨大な時間が掛かる」という事実がベースになっており、ここでも素数が非常に重要な要素として登場する。
本書は、そんな素数にある秩序を見出したリーマンという数学者と、彼が残した予想に関する物語だ。「リーマン予想」と呼ばれるその予想は、現在に至るまで未解決であり、数学上最も重要な未解決問題とみなされている。ヒルベルトという大数学者が現代数学の地平を広げるために提示した「ヒルベルトの23の問題」にも含まれており、また、クレイ数学研究所が発表した、解けば100万ドルの賞金がもらえる「ミレニアム問題」の一つでもある。
さて、「リーマン予想」の話をする前にまず、「ガウス」と「ゼータ関数」の話をしなければならない。
ガウスも素数の規則性を見つける方法について研究していたが、ある時彼はこんな風に考えることにした。
「次の素数がいつ現れるか正確に知ることは無理でも、1からある数(N)までに含まれる素数の個数ならある程度予測出来るのではないか?」
そうして彼は、対数という方法を使うことで、「ある数Nまでに含まれる素数の個数を大雑把に導き出す公式(素数定理)」を作り上げたのだ。これは数学者たちに新たな視点をもたらした。それまでは、素数一つ一つに注目していたのだが、「大雑把な素数の個数」に一定の規則性が見出されたことで、素数というものの全体に着目するようになったのだ。
もう一方の「ゼータ関数」については非常に説明しにくいのでここではざっと流すが、規則正しく並んだ分数を無限に足し合わせたもの、という感じである。音楽をきっかけにして発見されたこの無限和は、当初素数の分析に関わると思われていなかったが、オイラーが「オイラー積表示」と呼ばれる形式にゼータ関数を変換したことで、素数を扱う際の強力な武器へと変わっていった。
さて、ここでようやくリーマンが登場する。オイラーは「整数の範囲」でゼータ関数を考えていたのだが、リーマンはそれを「複素数の範囲」にまで広げた。複素数というのは、「a+bi」(a,bは実数、iは虚数)と表示されるものだ。そして複素数にまで広げてゼータ関数を考えたことで、リーマンはある発見をする。それは「ゼロ点」に関するものだ。
ゼータ関数の「ゼロ点」というのは、ゼータ関数が0になるような複素数のことを言う。例えば、「f(x)=x+1」という関数(これはゼータ関数ではなく、普通の関数)の場合、xに「-1」を入れると関数f(x)は0になる。同じように、ある複素数s(=a+bi)を入れると、ゼータ関数が0になるようなsのことを「ゼロ点」と呼ぶのだ。
リーマンは、この「ゼロ点」と素数との関係を発見した。リーマンは、ガウスの素数定理をゼータ関数によって拡張しており、その数式にさらに「ゼロ点」の情報を加味することで、「素数の個数」をより正確に予測出来る、と理解したのだ(この辺りのことは、僕もちゃんとは理解していない)。
そこでリーマンは、さらにこの「ゼロ点」について分析をしてみた。すると、いくつか計算した「ゼロ点」の実部(a+biの場合のaを実部と呼ぶ)すべてが「1/2」であることが判明した。そこで彼は、「非自明なゼロ点」と呼ばれるものの実部がすべて1/2である、と予想した。これが「リーマン予想」である。
本書は、そんな「リーマン予想」に挑んだ数学者たちの物語だ。出てくる名前をざっと挙げるだけでも、ビッグネーム揃いだ。メルセンヌ、ヒルベルト、ハーディー、ラマヌジャン、エルデシュ、ゲーデル、チューリング…。しかも、そんな錚々たる数学者たちが挑んでもなお未解決のまま、という超難問なのだ。
「リーマン予想」は、理解するのがなかなか難しく(僕もちゃんと理解しているとはとても言えない)、数学的な記述については諦めたくなるだろう。しかし、それでもいい。本書は、数学者たちの奮闘の物語として読めばいいし、それでも十分に楽しさを味わうことが出来る。
本書に登場する数学者の中では、ラマヌジャンとエルデシュが大好きだ。ラマヌジャンは、「夢で神さまが公式を教えてくれる」と言って、どっからこんな公式が現れるんだ?と誰もが首をひねるような公式を次々に生み出した(しかも、彼自身はその公式の正しさを証明できなかった)。エルデシュは、自宅を持たず、カバン一つで世界中の数学者の家を訪ねては共同研究をしたというなかなかの変人で、「彼と共同論文を書いた関係性」を表す「エルデシュ数」も有名だ。
本書を読んで、素数という、数学の神秘を教えてくれる対象の奥深さと難しさに足を踏み入れてみて欲しい。
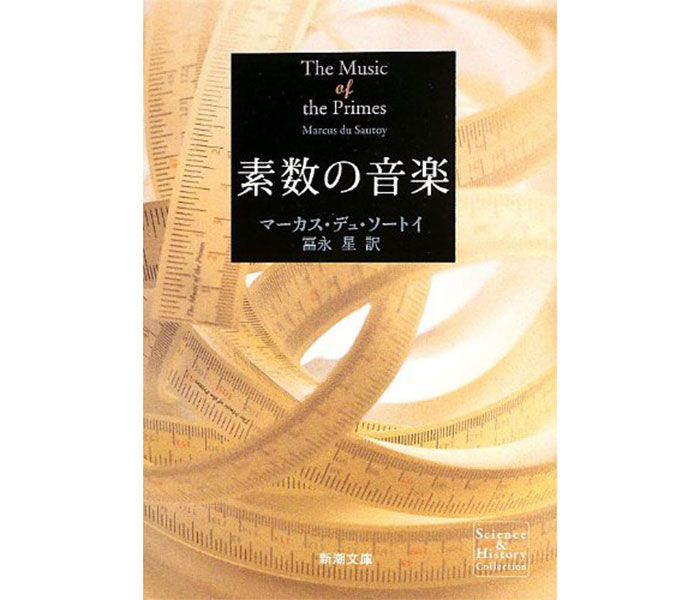
『素数の音楽』新潮社
マーカス・デュ・ソートイ/著 冨永星/翻訳

