akane
2018/05/24
akane
2018/05/24

若干24歳にして、オバマ大統領のスピーチライターとなったデビット・リット。彼の自伝的作品『24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに?!』が発売になります。彼はオバマ大統領に出会うまで、政治と縁を切っていたと語っています。そんな彼がホワイトハウスに足を向けることになったきっかけは何だったのでしょうか? そこにはあるスピーチとの出会いがありました。
*
飛行機の機内での出来事だった。僕を乗せた飛行機は、ジョン・F・ケネディ国際空港へ降下する態勢に入っていた。当時は、機内でのテレビ放送の生視聴が始まったばかりだった。僕が通販番組からスポーツ番組へとチャンネルを移動していると、その間のチャンネルでたまたま、アイオワ州の民主党党員集会を中継していた。どうやら同州の予備選が終わったところらしく、これから勝利者の演説が始まるようだ。ほかにいい番組もないので、これを見て時間をつぶすことにした。シートベルトがきちんと締まっていること、トレーテーブルがロックされていることを確認する。そして、目の前のテレビ画面に合わせて小さく映し出された会場で、五センチメートルほどの男が勝利宣言するのを見た。
それまでバラク・オバマの噂を聞いたことがなかったわけではない。二〇〇四年の民主党党大会での基調演説は記憶に残っていた。僕よりも政治に熱心な友人の中には、その選挙運動に夢中になっている者もいる。だが僕は、あまりに大人すぎて、彼らの言うことをまじめに受け止められなかった。友人たちは、フセインというミドルネームを持つこの男がアメリカの大統領になればいいと言っていた。それならいっそのこと、「歯の妖精」(訳注:抜けた乳歯をコインと交換してくれる妖精)に投票してはどうだろう? ローマ法王にはウーピー・ゴールドバーグを指名したらいい。
僕はオバマの演説を見守った。
それから数年がたち、大統領のスピーチの原稿をいくつも書いた今では、演説を読んだり聞いたりすると、つい頭の中で編集作業をする癖がついてしまった。そのアイオワ州での歴史的な党員集会で、オバマはまずこう語った。「彼らは、こんな日は絶対に来ないと言った」。今、改めてこの言葉を読んでみると、さまざまな疑問がわく。「彼ら」とは誰なのか? 彼らは本当に「絶対に」と言ったのか? 当時はジョン・エドワーズが、ヒラリー・クリントンの本来の支持基盤である白人労働者階級にも支持を広げ、二人で票を奪い合っていた。それなのに「彼ら」は、反戦を掲げて力強い資金調達活動を展開するオバマが、この三つどもえの民主党予備選に勝利できないと本気で思っていたのだろうか? それなら「彼ら」は、まるで見当違いをしていたことになる。
だが、こうした分析はいずれもあとづけに過ぎない。当時は、ストレスによる不眠症や、ホワイトハウスのレストラン「ネイビーメス」の勘定の心配などしなかったように、そんなことは考えもしなかった。むしろ、その言葉にすっかり魅了されていた。オバマは続けた。
「あなた方は、歴史におけるこの決定的瞬間に、皮肉屋から不可能だと言われたことを成し遂げた」。まるで映画に登場する大統領のような話しぶりだ。僕の父親より若く見える。僕はよくよく考えるどころか、何も考えなかった。ただその言葉を信じた。
バラク・オバマはそれから一二分間、話を続けた。着陸装置が機体から飛び出た瞬間にひやっとしたが、それ以外は演説に釘づけだった。オバマは、僕たちは一つだと言った。僕は中央の座席に座っている男性を見て、そのとおりだとうなずいた。また、民主党と共和党を一つにまとめて医療を拡大するとも述べた。僕は、彼の言うとおりになると確信した。さらにオバマは、居並ぶ運動員やボランティアのほうを見て言った。
「きみたちががんばったのは、きわめてアメリカ的な信念を持っていたからだ。それは、どんな困難に陥っても、この国を愛していれば変えられる、という信念だ」
二一歳にもなれば、突然、心を奪われるような恋心に襲われた経験もなくはない。そんなときには、話を聞いてくれそうな友人に胸の内をまくしたてる。「こんな女の子がいるんだ。カリフォルニアの子でね。以前、ワシントン州で一週間、一緒に過ごしたんだけど、どれだけ共通点があると思う?」オバマの演説を見たとき、僕をとりこにしたのは、性的な魅力ではなく政治的な魅力だった。だが政治であれ何であれ、心は望みの方向へ向かう。
僕はこの国を愛している! だったら、この国を変えられる! あの人はまるで僕のこれまでの人生を知っているみたいだ!
演説のあと、滑走路が近づきつつある飛行機の中で、自分の心に何が起きたのかを考えてみた。僕はレーガン政権の終わりごろに生まれた。そのころの政府は、解決策よりも問題を生み出していた。初めて選挙で投票したのは、ブッシュ政権のときだ。当時は、国外の敵にも国内の敵にも、「おまえは私たちの味方か、テロリストの味方か」という二者択一が適用された。だが今、この大統領候補者は、ニューヨーク市の数千フィート上空で、こう語りかけていた。僕たちは、共和党支持者と民主党支持者の寄せ集めではなく、アメリカ合衆国の市民だ、と。
僕たちが一つになれば、どちらかだけでできることより、はるかに偉大なことが成し遂げられる。
搭乗ブリッジから出てきたころには、僕はもう、バラク・オバマについて黙ってはいられない人間になっていた。僕一人ではない。大学のキャンパス中に、いやアメリカ中に、理想を求める人が続々と現れていた。希望や変革を願う人々が、ゾンビのように群れ集まっていた。
*
以上、『24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに⁈』を元に構成しました。「オバマ大統領の笑いのミューズ」と呼ばれたスピーチライターが。オバマ大統領の素顔とホワイトハウスの内幕、そして歴史に残る名演説の舞台裏をユーモア溢れる筆致で描き出します。
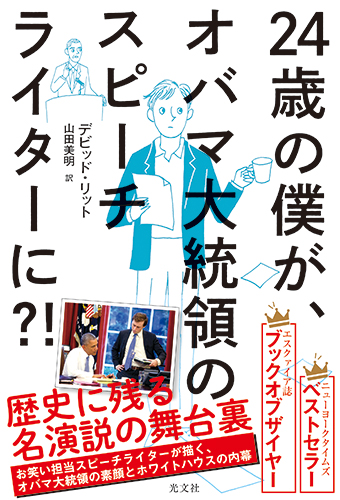
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.