ryomiyagi
2021/06/17
ryomiyagi
2021/06/17
平成から令和になる時、渋谷のスクランブル交差点では若者が乱痴気騒ぎし、記念品が売り出され、世の中はお祭り騒ぎだった。昭和から平成になる時のあの世の中がしんとした空気が身にしみた私としては、なんとも不思議だった。
昭和が終わって平成が始まったのは1989年1月8日、まさしくバブルの真っ只中だった。この頃は西暦より和暦が多用されており、1989年の1月7日までと1月8日からではまったく別の時代という感じがした。
前年の秋頃から体調を崩されていた天皇陛下のご様子は、ニュース番組や新聞などで詳細に報道されていた。プロ野球中継やドラマの放送中でも画面には度々、その時の天皇陛下の体温、脈拍、血圧、呼吸数などがテロップで流され、下血の際は下血量までもが国民に知らされた。
ついに昭和は終わるのか、口に出さなくとも誰もが思っていた。
次第に自粛ムードが強まっていった。プロ野球優勝チームのビールかけがなくなり、にぎやかなバラエティ番組やはなやかな催し物などいろいろなことが取り止めになった。井上陽水が出演していた日産のCMは、彼が走る車の助手席に乗り、窓を開けて「皆さあん、お元気ですか? 失礼しまーす」と呼びかけるというもの。あの独特の声と台詞まわしが印象的だった。しかし、この台詞が状況にそぐわないという理由で途中から音声がカットされて放映された。
昭和天皇が崩御されたのは1月7日早朝で、その日の午後には「平成」という新しい年号が発表された。昭和六十四年はわずか七日間しかなかった。

当時の私は文章を書く仕事を始める前で、「家事手伝い」という名を借りた無職。自宅住まいでやることもなく、友達とふらふら出かけることで日々を埋めていた。あの日はお昼近くまで寝て、起きてテレビをつけ、昭和が終わることを知った。テレビは訃報一色。CMもすべて自粛されていた。私は愛国者ではないし、かといって天皇制に反対するわけでもないけれど、悲しかった。今まで当たり前というか、意識さえしなかった「昭和」という年号がなくなってしまうのもさびしかった。
その夜も友達と会う約束があった。「せっかくの土曜日だから」という理由で私たちは待ち合わせた。
銀座線の外苑前駅から地上に上がって、青山ベルコモンズの前に出て、街が静かなことに気がついた。青山ベルコモンズは今の青山グランドホテルの場所にあったファッションビルだ。私たちはスキーショップジロー近くのカジュアルなご飯屋さんで待ち合わせたが、店は閉まっていた。あの頃、スキーショップジローは店の前を通ってショーウインドウを見るだけでわくわくするような存在だった。
スマホもネットもSNSもない、まだ駅では伝言板を使っていた頃である。移動中の友達に連絡するすべもなく、店の扉に寄りかかって待っていた。よくあることだった。ほどなくして友人が来て、他の店を探しに青山通りに出た。今はあまり使われない呼び名のようだが、246の三宅坂から渋谷までを青山通りと呼んでいた。
いつもはにぎやかなこの大通りも人が少ない。表参道のカフェに行ったけれど、そこも閉まっていた。街じゅうが喪に服しているのだった。それでも私たちは家に帰ろうという気にはならなかった。
何軒か空振りして、かの「ブラッスリーD」を確かめてみようということになった。
岡田大貳氏の手がけたレストランで、ブラッスリーDのDは大貳のDだ。岡田氏は東京の夜を作った人物といっても過言ではない。プロフィールを書き出すだけで、東京の夜の歴史がわかる。1960年代、東京のディスコのはしりだった赤坂の「キャステル」で支配人を務めた後、六本木で一番スノッブだったディスコ「ザ・ビー」を手がけ、1981年青山にファッショナブル中華のはしりである「ダイニズテーブル」を開業する。1986年に原宿にオープンさせた「クラブD」はその名の通りディスコからクラブへの転換となった店だ。
青山通り沿いにあるブラッスリーDは、ダイニズテーブルと同じように一レストランというより社交場というほうが相応しかった。おしゃれな大人たちが毎夜毎夜集っていた。私はブラッスリーDで、それなりのレストランには待ち合わせのためのバーがあることを知った。
無職にはハードルの高い店だけれど、思い切って階段を上がると、こんな日の夜でもブラッスリーDは開いていた。
いつもははなやかな客で埋め尽くされている店内の客はまばらだった。バーカウンターには中年の男女がいて、男性はグレーのスーツに紺色のネクタイ、女性は黒いワンピース。女性の左手首には華奢な腕時計があって、アクセサリーはそれだけだった。二人の前のグラスには赤ワインが注がれていた。
カウンターの向こうのバーテンダーは、「いらっしゃいませ」の代わりに黙礼し、お互いにゆっくり深々と頭を下げた。私たちも赤ワインを注文した。グラスが運ばれてきて、なんとなく隣の男女と目線を合わせてみんな静かにグラスをあげた。
中年の男女もバーテンダーも黙っていた。私たちもほとんど話さなかった。残り数時間となった昭和を思いながら、ワインを味わった。店を閉めるだけが喪に服すことではないのだと思った。
この話にとくにオチはない。昭和最後の日、街が喪に服していて、しんとしていたことを記録しておきたいだけだ。
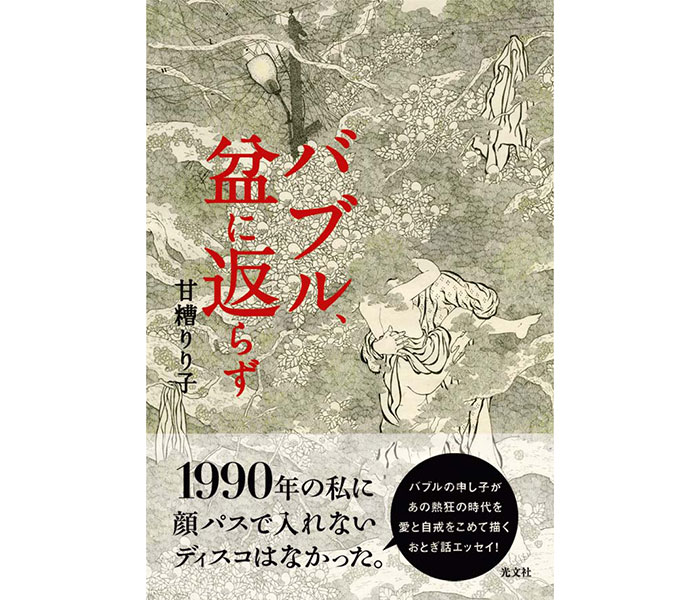

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.