akane
2019/07/15
akane
2019/07/15

益川敏英『科学者は戦争で何をしたか』(集英社新書)2015年
連載第21回で紹介した『理性の限界』に続けて読んでいただきたいのが、『科学者は戦争で何をしたか』である。本書をご覧になれば、科学者が過去の戦争で何をしたか、なぜ科学技術は「両刃の剣」にならざるをえないのか、日本の科学者を取り巻く社会環境がいかに危機的になりつつあるか、明らかになってくるだろう。
著者の益川敏英氏は、1940年生まれ。名古屋大学理学部卒業後、同大学大学院理学研究科博士課程修了。京都大学教授を経て、京都大学名誉教授。現在は名古屋大学特別教授。専門は素粒子理論。1973年、当時3種類しか知られていなかったクォークが6種類あると予測した「小林・益川理論」を発表し、後に実験で確認された。小林誠氏・南部陽一郎氏と共に2008年度ノーベル物理学賞を受賞。反戦・憲法九条護憲運動への積極的参加でも知られ、『素粒子はおもしろい』(岩波ジュニア新書)や『いっしょに考えてみようや』(共著、朝日選書)などの著書がある。
益川氏の戦争に対する「原体験」は、1945年3月12日にさかのぼる。名古屋市に空襲警報が鳴り響き、家族で避難しようとしていた瞬間、二階の屋根瓦を突き破って落ちてきた「焼夷弾」が、コロコロと土間を転がって、当時5歳の益川氏の目の前で止まった。
「焼夷弾」とは、日本の木造家屋を焼き払うために開発された爆弾で、落下後に破裂し、中に充填された発火性薬剤の黄燐が周囲に飛び散って、大火災を起こす仕組みになっている。もし爆発すれば、もちろん益川氏の命はなかったはずだが、幸いにも、その焼夷弾は不発だった!
「九死に一生を得た私たち家族は、すぐさま家を飛び出し、火の海となった名古屋の街を逃げまどいました。家財道具を積んだリヤカーの上に5歳の私がちょこんと座り、そのリヤカーを両親が火の手を避けながら必死に引っ張って走っている。太平洋戦争末期の頃の、もう70年以上も前の光景ですが、大空襲による火災でオレンジ色に染まった空の色は、今も不吉な記憶として私の中に色あせることなく残っています」という、真に恐ろしい「原体験」である。
スウェーデンの化学者アルフレッド・ノーベルは、膨大な人手と労力を必要とする採掘や土木工事を改善させるため、1866年に「ダイナマイト」を発明した。しかし彼は、当初から、その発明が、それまでの戦争の方式を一変させる爆破兵器として使用される可能性にも気付いていた。その後、第一次大戦で用いられたダイナマイトの破壊力で傷つけられた人々は、彼のことを「死の商人」と呼び、ノーベルは生涯、罪悪感で苦しみ続けたといわれている。
そこで彼は、ダイナマイトで得た巨万の財産を投げ打って基金を設立し、人類の進歩に貢献する「物理学、化学、生理学・医学、文学、平和」の偉大な研究成果に対して賞を授与することにした。彼は、「ノーベル賞」を遺すことによって自身の名誉を挽回しようとしたのである。
益川氏は、「科学者の戦争責任」という言葉を批判する。なぜなら、そこには、「自分は科学者でないから関係がない」という「無責任」や、科学者ならば責任を取る能力と義務があるだろうという「責任転嫁」のような暗黙の意図が感じられるからである。
それでは、科学者はどう責任を取ればよいのか。益川氏の結論は、「科学者ではなく、人間としての目線を持て」ということに尽きる。自分の開発した科学技術が「悪用される」可能性を誰よりも早く気付くのは、それを開発した科学者自身である。したがって、その科学者には「人類に役立つ成果を発表すると同時に、こんなふうに使われたら危険であるということを警告する義務がある」というのが、益川氏の警告である。
実際に、1903年に「放射能」の発見でノーベル物理学賞を受賞したピエール・キュリーは、「ラジウムが犯罪人の手に渡ると、非常に危険なものになるでしょう」とノーベル賞受賞記念講演で警告を発している。その背景にあるのは「私は、ノーベルとともに、人類は新しい発見から害毒以上に多くの福利を導き出すであろうと信ずる者の一人であります」という信念である。
研究者というのは非常に個人主義的であるし、そりゃあ好きな研究をやっている方が面白い。どこの国で戦争が起きようが、自分の国でどんな社会問題が起きようが、関心の薄い研究者も多いでしょう。自分の研究媒体が軍学協同の資金援助を受けたとしても、その潤沢な資金を歓迎こそすれ、そこに疑問を持ったり、抵抗を感じたりする研究者がそれ程多くいるとは思えません。そうした無関心な態度、問題意識のなさは、軍拡を進める為政者にとっては都合のいいことです。(P.110-111)
「戦争する国」に突き進んでいる日本の何が問題なのか、科学者はどのような世界的視野を持つべきなのかを認識するためにも、『科学者は戦争で何をしたか』は必読である!
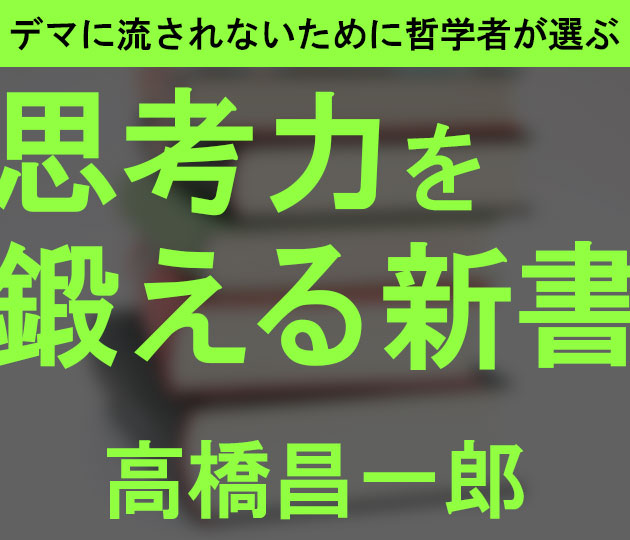
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.