akane
2019/05/20
akane
2019/05/20

新聞社の科学記者として、生命科学や環境問題、科学技術政策などの取材を担当してきた三井誠さん。三井さんはこのたび『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)を上梓しました。科学の取材を長く続けてきた三井さんにとってアメリカは、科学の新たな地平を切り開いてきた憧れの地でした。2015年、米国の首都ワシントンに科学記者として赴任が決まった時、科学の歴史が作られるアメリカの現場を見たいと心が躍ったといいます。しかし、「科学大国アメリカ」の地で三井さんの興味を最も惹き付けたのは、意外にも、最先端の科学ではありませんでした。三井さんの心の中に不可解なものとして居座り続けたのは、アメリカで広がる「科学への不信」だったそうです。
このコラムでは、前述の著作の一部を抜粋して内容をご紹介いたします。
私が「科学大国アメリカ」の地で最も惹き付けられた「社会に広がる科学への不信」。
そのきっかけは、地球温暖化を「でっちあげ」と言ったドナルド・トランプ氏でした。科学的でないことや事実に反することを平然と言うトランプ氏が、世界で最も影響力のある米国の大統領に当選したのです。これはあまりに衝撃的なことでした。2016年11月9日の未明、勤務先のワシントン支局でトランプ氏当選確実を知った時の驚きは、生涯忘れることはないでしょう。
米国には、地球温暖化への根強い疑問の声や、信仰に基づく進化論への反発など、科学的とはいい難い考え方をする人たちがいることは知っていました。しかし、地球温暖化を否定する大統領の誕生は、想像を超える出来事でした。
科学に対する不信や反発はどこから生まれ、なぜ広まっているのだろうか。「科学で最先端を走る米国の違う顔を知りたい」と思うようになりました。そんな気持ちで、科学に不信感を持つ人たちを全米各地に訪ねる取材を始めたのです。
アポロ計画で人類を月に送った科学大国アメリカで、科学不信を取材するという皮肉な巡り合わせでしたが、取材のたびに驚き、考えさせられました。
ここでは、とりわけ印象に残った次の言葉をご紹介したいと思います。
トランプ政権が2017年1月に発足し、予算方針を初めて示した3月、首都ワシントン・ホワイトハウスの記者会見で、ミック・マルバニー行政管理予算局長が話した言葉を最初に取り上げます。
「(地球温暖化の研究に)もうお金は使わない。税金の無駄だ」
NASAの地球観測をはじめ、米国の研究は地球温暖化の現状を解き明かす中核を担ってきました。それなのに、世界に誇るべき貢献を「税金の無駄」と切り捨てたのです。
トランプ政権は、地球温暖化を疑う人たちを幹部に登用しました。彼らはテレビのインタビューや連邦議会での証言で「人類の地球温暖化への影響はまだ、論争がある問題だ」「二酸化炭素が地球温暖化の主な原因とは思わない」などと発言していました。
地球温暖化を巡っては、世界中の研究者が参加する「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が2013年にまとめた報告書でこう結論付けています。「20世紀半ば以降の平均気温の上昇の半分以上は人間活動が引き起こした可能性が極めて高く、その確率は95%以上だ」。人間が石油や石炭などの化石燃料を燃やす時に出る二酸化炭素が、地球温暖化をもたらしていると科学者は考えています。二酸化炭素のほかにもメタンなど地球温暖化をもたらす気体があり、これらはまとめて「温室効果ガス」と呼ばれています。
トランプ政権下でも、NASAなど連邦政府の13省庁が2017年11月、「20世紀半ばからの気温上昇は、人間活動から排出された温室効果ガスが主な原因である可能性が極めて高く、説得力のある要因はほかにない」と、人間活動による地球温暖化を明確に認める報告書を発表しています。
それなのに、大統領をはじめ政府の主要メンバー、さらに二大政党の一つである共和党の幹部も地球温暖化を疑う姿勢を取っているのです。人間活動による地球温暖化を疑い、対策を先延ばしにしようとする人たちは「懐疑派」と呼ばれ、その主張は「懐疑論」といわれています。
懐疑派の大統領を生んだ米国は、世界のなかで温暖化懐疑論が最も深く社会に根ざしている国といえます。科学大国でありながら地球温暖化を疑う、不思議な国の背景を探ることは、人間の反科学的な側面を探る手がかりになるように思えました。
次は、神が人類を創ったとする「創造論」の世界を紹介する「創造博物館」(南部ケンタッキー州)で聞いた、父親から子どもへの言葉です。
この施設は、キリスト教の団体が2007年に作ったもので、10年間で300万人以上が訪れたそうです。実際の生き物や模型などを展示し「驚くほど多様な生物は全知全能の神が創り出した」と解説しています。聖書の世界を再現したテーマパークのような施設です。アダムとイブの模型もありました。
そこでは、約320万年前の初期人類とされる化石(複製)が、類人猿だと紹介されていました。この化石は、私たち現代人よりも、腕が足に比べて長い特徴があります。地上を歩く足よりも樹上で枝などをつかむ腕が発達していた祖先の体形が一部引き継がれたもので、まさに人類が進化してきた道のりを現代に伝えています。しかし、それが類人猿だとされていたのです。
19世紀半ばにダーウィンが進化論を発表した時、類人猿から現生人類(ホモ・サピエンス)への進化の過程を示す化石は見つかっていませんでした。しかし、その後、化石が相次いで見つかり、脳が大きくなる過程や、足や腰の骨が二足歩行に適した形になる過程がわかってきました。もはや、類人猿から人類への進化を疑う研究者はいません。
しかし、そうした進化の考え方は、創造論とは相いれません。先ほどの展示の前で、年配の男性が小学生くらいの男の子に、口をとがらせて教えていました。
「生物学者は研究費を獲得するために、(現代科学の見解に合わせ)この化石を人類のように復元しているが、本当はサルなんだ。進化論は科学者のでっちあげだ」
科学的な成果を「科学者が研究費獲得のためにでっちあげたウソ」と見なす考え方は進化論だけでなく、地球温暖化に関してもしばしば聞きました。
「地球温暖化はでっちあげ」と言ったり「進化論は科学者の予算獲得の口実」と言ったりする、科学的とはいい難い発想について、「正しい知識がないからだ」と見なす考え方があります。正しい知識がないから、科学的に振る舞えないという考え方です。逆にいえば、「正しい」振る舞いは科学的な知識によって導かれるということでもあります。
しかし、本当にそうでしょうか。
次回のコラムでは、科学と社会の関係に詳しいオークランド大学(中西部ミシガン州)のマーク・ネイビン准教授(社会・政治哲学)がインタビューで話してくれた言葉を紹介して、「正しい」振る舞いは科学的な知識によって導かれるのかどうか、そして先進各国に共通する課題について述べたいと思います。
※本稿は、三井誠『ルポ 人は科学が苦手』(光文社新書)の内容の一部を再編集したものです。
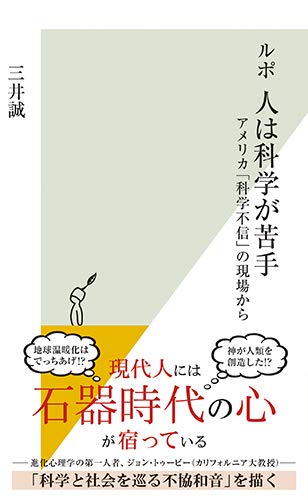
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.