akane
2018/09/06
akane
2018/09/06
──ところで、寺尾さんは「ラプラタ幻想文学」という言葉をお使いになっています。「魔術的リアリズム」という言葉がありますけど、2つは全然違うものなのですか。
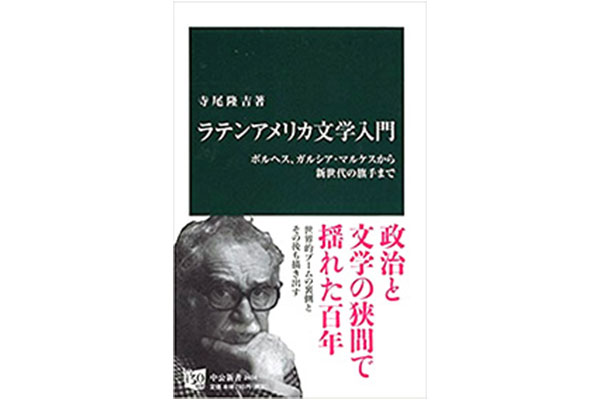
寺尾 私の見解では両者を区別しています。『魔術的リアリズム 20世紀のラテンアメリカ文学』(水声社)という本を2012年に出版して、その中で議論していますし、最近の『ラテンアメリカ文学入門 ボルヘス、ガルシア・マルケスから新世代の旗手まで』(中公新書、2016年)でも概略しています。
──簡単に言うとどう違うのですか。
寺尾 端的に言えば、魔術的リアリズムは、ある歪んだ視点を一つの共同体全体に適用し、中心に据えることで普通と違う出来事を起こすことです。それに対し、ラプラタ幻想文学の出発点は、そもそも現実を否定して、フィクションを現実と置き換えることにある。つまり、現実とフィクションの関係をひっくり返す文学です。ボルヘスとか、ビオイ=カサーレスが代表者で、コルタサルにも共通する部分があります。現実から逃れて、現実とフィクションが入れ替わってしまうような話は、『遊戯の終わり』にも出てきます。

──それを詳しく知ろうと思ったら、まず中公新書かな(笑)。
寺尾 そこから入って、水声社の本の進んでくれるといいですね(笑)。
──寺尾さんが初めてコルタサルを翻訳したのはいつ頃ですか。
寺尾 2014年の『対岸』と『八面体』が最初です。いずれも「フィクションのエル・ドラード」から、コルタサルの生誕100年に合わせて出ています。私はこの年から翌年までスペインにいて、スペインからアルゼンチンにも行きましたし、ニカラグアに行ってコルタサルの親友だった作家のセルヒオ・ラミレスにも会って、コルタサルゆかりの地にもいろいろ行きました。
──解説の中で「短編小説家コルタサル」と書いていらっしゃいました。彼には評判を呼んだ長編がないわけじゃない。それでも、彼の本質は短編だとお思いでしょうか。
寺尾 私はそう思います。『石蹴り遊び』という長編が63年に発表され、ラテンアメリカ文学ブームの真っ只中に発表されたということもあって、当時は評判を呼びましたが、ちょっと形式的な実験に走りすぎているという印象が、今読むとします。コルタサルは長編小説になると実験をするんです。手法的実験。こういう形式で小説を書いてみたらどうだろうとアイデアや野心に駆られるようですね。短編の場合は自分のオブセッションとか、見た夢とか、取り憑かれたものとかを、何としてでも書かなければという意気込みで、ワーッと一気に書くけれども、長編になると理知的に形式の事を考えてしまう。
──頭を使うわけですか。
寺尾 ええ。なので、残念ながら私には物足りない。訳したいともあまり思わない。
──深い話ですね。頭を使うほうが面白くない。
寺尾 ええ(笑)。理性的になり過ぎるんでしょうね。内側から出てくる、それこそ無意識から出てくるもののほうがよほど面白い。『懸賞』(1960年刊行、未訳)のような長編を読んでいると、確かによくできているとは思っても、登場人物が機械みたいに動かされていて、形式を追うだけのような感じがするんです。それでも『石蹴り遊び』には内面の探求みたいなところがあって、その部分は面白いけれども、やはり形式的な実験が先走って、せっかくの優れた部分が薄れてしまっている感じがします。
──やっぱり短編小説家なんですね。
寺尾 私はそう思います。『石蹴り遊び』を高く評価する人もいますが、それは好みの問題でしょうね。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.