2021/12/02
坂上友紀 本は人生のおやつです!! 店主
『魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣』文藝春秋
石井妙子/著
口絵の写真で泣きそうになったのでびっくりした。水俣病にかかった女の子を撮った写真と、水俣病によってあちこちに指が曲がってしまった上、ガリガリに痩せてしまった男性の手の写真。時に一枚の写真が百行の文章の力以上に訴えかけてくることがある。この写真が撮られた日までの間、この人たちは一体どんな人生を歩んできたのだろう。
本書に書かれているのは、必死で生きた人たちの声と、生きるための闘いの記録です。第二次世界大戦で自身もまたその後の人生に対する考えや生き方に甚大な影響を被ったアメリカ人の写真家ユージン・スミス(1918―1978)と、彼より約30歳年下で、日本人の母とアメリカ人の父を持ち、戦後の日本に生まれ、両親の離婚後は父方の祖父母にアメリカで育てられたアイリーン・美緒子・スミス。二人の生い立ちに始まり、出会って、なぜ日本に来て水俣病に罹患した人たちを撮るに至ったか。また、戦後の高度経済成長期において水俣病がどのように発生し、
確かに命を繋いでいく上で衣食住は重要です。ただ、ここまでしてまで人類は発展しないといけないのか。間違った進歩とは言えないか。経済発展による恩恵の一方で起こることの全容を踏まえた上で、どの道にどう進むのが最善なのかを決めるとき、より大切にするべきなのは進歩の度合い以上に、一人一人が持つ「魂」(心と言い換えてもよく)
本書で幾度か「写真は小さな声にすぎない」という言葉が出てきます。写真が小さな声であるのなら、本もまた、小さな声でしかない。どれだけ心震えたとしても、それは読んだ当人だけの体験でしかありません。いくつかの本(聖書のような)を例外として、ある一冊の本を世界中の人たちが読むわけでもなければ、読んだからとてみながみな同じ気持ちを覚えるわけでもやはりない。それでもだからこそ、例えば見ること、例えば読むことで、個々の「人」が感じた気持ちをそれぞれが伝えていくことによってしか、結局のところ「世界」もまた動かない。世界も国も企業も家族も、最終的には人という個の集まりで、だから一人一人が自らの人生のなかで、何に触れ、何を思い、どう生きていくのか、何を培っていくのかが大事なのだと、この本から私が強く訴えかけられたのはそういうことでした。「芸術的なもの」とはそういう感受性を揺さぶる何かのことです。
いっそ物語であればと何度も思ったくらいに残酷な過去の事実が綴られていくなか、本文中で水俣病患者が自身の心情を訴えかける言葉は、もはや文学(「それでも生きていく」という姿勢を感じる文章を、「文学」だと個人的に定義づけています)そのもののようにも感じられ、語られる内容は生活に根ざした真実の気持ちでしかないから、悲しいのに生き抜く美しさに満ちていて、胸を突かれて読んでいて何度も涙が込み上げました。文学もまた「芸術的なもの」の一つです。文章も意思ならば写真もまた意思で、表したいものが歪められることなく編集されれば、それが本でも写真でも、受け手側には自ずと伝わります。
ユージン・スミスは写真家だけど写真を撮ることが目的だったわけじゃない。いわゆる「写真家」としては批判の対象ともなり得る行為(ネガに手を入れて陰影の調整するなど)も厭わない。当時の写真界において「ユージンの写真は暗室から生み出される」と、賞賛の意味も揶揄の意味も込めて「絵画のような写真」だと言われても、そういう評価は全く大事なことではなかった。なぜなら写真を撮ること以上に、真実伝えたいことがより正確に伝わることこそが彼にとっては重要で、そして想いを最大限に現すことができる一番確かな手段が、彼にとっては写真であったから。加えて、写真につける「キャプション」もまた、表現する上で欠かせないエレメンツでした。
水俣病にかかった人たちのうち、ユージン・スミスが撮影することに最も拘った女の子がいました。それが冒頭の口絵に写っている少女・田中実子で、彼女に対するユージンの心情が垣間見える箇所があります。
実子には表情があるが、言葉はひとつも発せられない。歩くこともできない。口元から涎が流れる。
実子の写真をたくさん撮り、たくさんプリントした。写真には、まったく病が見えず、健康な、かわいらしい少女として写っているものが、たくさんあった。動画ではなく写真で彼女の病の実態を捉えることは難しい。病が写し出されないのである。美しく撮れている一枚を石川(※)が手に取り、「これ、いいですね」と言うと、ユージンは首を振った。
「親にあげるなら、それでいいのかもしれない。でも、それじゃダメなんだ。少しも撮れていない。そこには実子ちゃんの苦悩が少しも写っていないじゃないか」
ユージンは感情が込み上げてきて、床に転がって床を拳で叩き、泣き出した。
「ジツコちゃーん、ジツコちゃーん。私の写真にはあなたの苦悩が少しも写っていない」
(以下略)
※ 水俣でユージンやアイリーンと共にあり撮影を補助したカメラマン
「自分の仕事は写真や言葉によって、単なる記録以上のことをすることだ」と、語り実践したユージン・スミスは、確かに生半可ではない彼だけの写真、まさに「魂を撮る」ような仕事を成し遂げました。が、写真を撮る以外の、仕事に纏わる諸事や多くは私生活において、彼に困らされ、犠牲になった人たちが数多く存在した事実も本書から浮かび上がってきます。特に妻や恋人となった女性たちについては、「犠牲」という一言では済ませられないくらいの壮絶な関わりを否応なく持たされ、ユージン・スミスの生き様に良くも悪くも翻弄されてしまっているのも本当です。だから彼の全てが正義というわけではない。そして、水俣病を患った人たちに誠実に接していたアイリーンにおいてすら、近年「入浴する智子と母」の写真掲載を巡ってかなり不可解な行動を取ってもいる。(本書によれば、遠からずアイリーン本人によってその行動について何らかの説明がなされる模様)
改めて、「ジャーナリズム」とは一体何なのか、という問いかけが胸をかすめます。ある物事の良い面だけを書くのでも、悪い面だけを書くのでもなく、事実を事実としてあるがままに伝えるだけでもない。書く人、書かれる人、撮る人、撮られる人、訴えた人、訴えられた人……それぞれの強さと同時に弱さを、それぞれの視点に立って考えていかなければ、魂のありかが見えてこない。光の裏には影があり、善と言われたことが見方を変えれば悪にもなり得るとしても、「伝えたい」何かがあれば、例えその強い想いによってある種の公平さを失ったとしても、意思を持って伝えられることでしか、心は揺さぶられないのかもしれません。加えて、表現者と受信者がどう揺さぶるのか、揺さぶられるのかを決定づける「魂」は、ひたすらに日々を懸命に生きていくなかでしか育たないのだと、本書の最後に記されたユージン・スミスの言葉(水俣でユージンとアイリーンが暮らした家の、暗室の壁に書かれた落書き)を読んで、いま強く感じています。
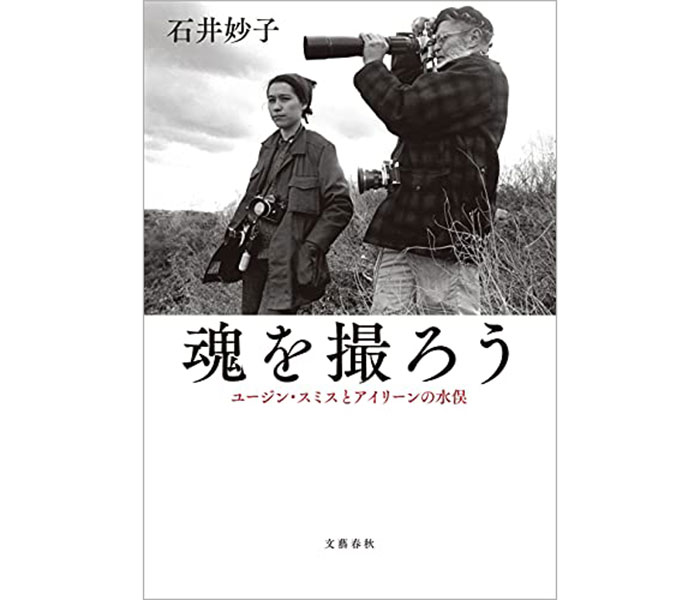
『魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣』文藝春秋
石井妙子/著

