ryomiyagi
2020/10/23
ryomiyagi
2020/10/23
第四章
パズル(5)手の記憶
「菜々子、法医学取ったの?」
「あれ、言ってなかったんだ? 二人はなんでも知ってると思ってたよ。いつもラブラブだから」
「なんでもなんか、知るはずないよ」
と、小声になっていく自分の返事が場を興ざめさせるのはわかっていたが、実際その通りになった。
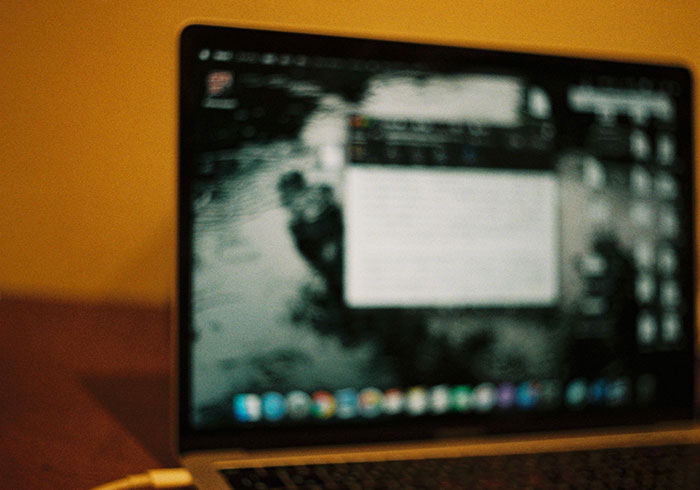
「あ、ごめん。私、なんかおかしかった?」
ジヒョンが少し眉を下げると、謙太は肩を動かし朗らかに言った。
「へえ、俺は知りたいけどね。菜々子のことはなんでも知りたいからさ」
「そうだね、わかるよ、愛してるから知りたいんだ」
と、ジヒョンはまた返すが、菜々子は自分の内側にまたひねくれた気持ちが現れるのを感じ、なんとか制した。
「法医学ね、面白い担当教官なんだ。女性の准教授。なんでも好きにやらせてくれそうなんだ。後期はちょっと入り浸りになるかもしれない」
誰に向かって返事をしているのか自分でもよくわからなかった。
「医学部四年ともなると、さすがに大変だな。ご馳走様、うまかった。ちょっと外で涼ませて」
と、謙太はジヒョンの部屋の小さなバルコニーに出た。
ガラス窓が開くと鍋の熱気も湯気も香りも一気に外に流れ出し、代わりに新鮮な空気が入ってくる気がした。
このまま謙太が拗ねたら面倒だと菜々子は思った。単純に今はそれに付き合う心の余裕もないのだった。
けれど謙太が部屋に戻って来ると、片付いたテーブルの上で、ジヒョンの方がギンガムチェックのテーブルクロスの表面を撫でながら、思わぬ告白を始めた。

「二人に、ちょうど話があったよ。私、福岡の尊くんに手紙を書いた。昔のやり方だからしないって言ったけど、やっぱり書いてみた」
そう言って頬を赤らめた。その顔はずっと見ていたいほど澄んで輝いていた。
「もう返事は、もらえたの?」
菜々子は、訊ねる。
「本当毎日ポスト、見てるけど、来ないよ。尊くんはもう私のこと覚えてないかな。それでもいいんだ。もし読んでもらえたら、それでいい」
謙太は菜々子に向かって微笑みかけて、
「来ると思うけどな。幼稚園の先生方にあんな素敵な手紙を書く人なんだからさ」
と言って頷く。
「幼稚園の時の初恋をそんなに覚えていられるんだね、ジヒョン」
水の入ったグラスの表面に浮かぶ水滴を見つめた。そう思うと、自分はいつも殺伐として、ろくに人を好きになってもこなかったように感じた。
「手、貸して、菜々子」
そう言って、ジヒョンは不意に手のひらを差し出してきた。言われるがまま手を伸ばすと、ぎゅうと力強く握られた。
「この手じゃない。それに謙太の手も借りていい?」
同様に謙太の手も握る。
「かっこいい大きい手だけど、これでもない。尊くんの手だけなんだ。いつも私の手を握っていてくれた。幼稚園で困っている時、楽しい時、不安の時も、いつも尊くんが握ってくれて、帰る時もお母さんが迎えに来るまでそうだった。だから家に帰ると私の手、いつも尊くんの手の匂いがしたよ」
いつも母に向かって伸ばしても、突き放されるように感じていた自分の手の記憶。
「何かなくしそうな時は、二人の手の中に挟んで持ってくれた。十円玉だったり、紙切れや、小石だったりもした」
「ジヒョンの話を聞いているとさ、俺まで尊くんに会ってみたくなるな」
「向こうも覚えてるよ、きっと」
菜々子はそう言って、続けた。
「あーあ、こんな忙しい時期に、ジヒョンの心には火がついちゃった。これは分かれ道だね。もし返事が来たら、まだ大切な思い出は続く。でも来なかったら、ジヒョンは次の恋に一コマ進む」
ジヒョンは少し俯いた。

「わかってる。恋じゃなくて、婚約がある」
そう言うと、ジヒョンは手の甲で自分の目尻を少し拭った。
「今日はすごく星が見える。菜々子たちも外、見てごらんよ」
再び謙太が外に出て、こちらに手招きしてくれる。
「いいな。二人は恋してる。私はずるいよ。こんな気持ちで婚約した。それが日本に来られる条件だったから」
それには、ただ耳を傾けただけで、菜々子は返事をしなかった。ジヒョンの独り言は、ただ黙って聞いてあげたらいいのだと思うのだ。
バルコニーの手すりに両腕を預けている謙太の方へ行き体を寄せると、その腕の中に菜々子を抱えて引き寄せてくれる。
「法医学だったか。何かが、菜々子を助けてくれるんならそれでいいんだ。ひとりで悩んでいるのかなと思ったら苦しかったけど、自分だったらと必死に考えても確かに答えは出なかった」
謙太が、耳元で、そう呟いた。
本当は謙太にも、止めてほしいのかもしれない。真実がわかったときに、自分がどうなるのか想像もつかない。謙太やジヒョンのような温かい人たちと、同じように過ごせるのかも自信がない。
ただ、真実を知りたいという気持ちは、止められない。そうでなく真実を突き止めなくては、自分のコマも次に進めない。
「キムチの匂い、するよ」
菜々子が、言う。
「二人とも同じでしょ。そんな日は幸せだね」
「おい、なにー? 二人でいちゃいちゃ」
ジヒョンもやって来て横に並び、少し同じ匂いをさせて、遠い星空を見上げた。
次回に続く(毎週金曜日更新)
photos:秋

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.