akane
2021/01/29
akane
2021/01/29
※本記事は連載小説です。
第7章
菜々子(2)ブルースカイ
水面が銀に輝いていた。
光が遊んでいるように、目線をどこまでも誘っていく。

湯河原に着いた謙太とは駅前の喫茶店で待ち合わせをした。親との面倒を避けたかったというよりも、一度も謙太をきちんと案内したことがなかったから良い機会だと思った。 古い温泉町だと思ってしか育たなかったけれど、いたるところには水の流れがあって、豊かな水に育まれた森林が深い。川を渡る橋や、滝からの水しぶき、歩けば出会う小さな祠や地蔵さん。
喫茶店の扉を開けて現れた謙太は、冬用の丈の長めのライダースを着て、首から小型のカメラを下げていた。
さっそく歩きはじめる。好きな風景があると立ち止まって写真を撮って、時折、菜々子の方にもカメラを向けた。
「写真、撮られるの好きじゃない」
「菜々子のことなんか撮ってないよ。後ろのプロポーションのいい樹を撮ってる」
謙太がそう言って、首を傾げてみせる。
彼が目にしているもの、愛おしそうにカメラのレンズを向けるもの、菜々子はこれまで知らずにいた気がした。
オートバイの後ろに乗っていても、菜々子が楽しんでいたのは、スピードや風や鼓動感、時には謙太のライダースの革の匂い。
けれど謙太は多分、走りながらいろいろな色や光をその目に捕まえていたのだと思う。
よく、一人でツーリングして帰ってくると、メールで報告してくれたから。
すすきの穂が綺麗だった、とか、水田の苗の葉先がみんな同じ方向に傾いていた、とか。
吉浜の海にオートバイを停めて、しばらく砂浜に並んで座っていた。凧揚げしている親子や、サーファーがぽつりぽつり。時折、歓声が波の音を縫うように伝わって来た。
「お正月なのに、来させちゃった」
「ちょうどよかったよ。菜々子とお賽銭も入れられたしさ」
小さな神社で、二人で並んで賽銭を投じて、鈴を鳴らした。なんてことはないから余計に、菜々子には湯河原の最後の思い出作りのような気がしてならなかった。
「謙太ってさ、本当はモテてるよね?」
「今更?」
「いや、モテないか。趣味が老けてるし」
「あ、そうですか」
ちょっと口を尖らせている。
「なんで急にそんなこと、思ったの? その答えなら褒め言葉でしょ? 聞きたい。お年玉がわりに」
「だって、思えばかっこいいオートバイに乗ってるし、写真とか撮っちゃうし、結構マメでしょう?」
「全然嬉しくなかったわ」
菜々子はふーんと鼻を鳴らす。
「ていうか俺、マメじゃないよ。菜々子以外には」
「偉いじゃん」
と、自分より大きな謙太の頭を撫でる。
「俺、菜々子がいればいいんだよね。菜々子がそばにいてくれるだけでいい。気持ちがつながっているだけでも、それどころか、菜々子が幸せならいい、って境地にも最近達しつつある。偉くない?」

遠くで空に上がっていたはずの凧が風に舞いながら急旋回し、近くに落下した。
すぐに立ち上がったのは菜々子で、凧を拾って両手に高く持つ。
「いいって、そっち引っ張って」
「すみません」
はしゃぐ男の子の横で、お父さんが頭を下げている。
「せーの」
と、いう声とともに凧が菜々子の両手から風を受けて引っ張られていき、空に高く上がった。男の子の高い声が響いた。
空を舞う凧は、今の流行りなのかスカイブルーで、尾が七色で長い。
「やった」
見上げながら両手を叩いていると、
「普通さ、横にいる男に頼むでしょ、まあそういうところが、好きなのかもだけど」
空から目線を落とすと、立ち上がった謙太の顔があった。
「凧揚げ、子どもの頃にやったことあったから。しかも、この浜でね。父が凧をこうして持ってて、私が走って引いたの」
「目に浮かぶようですよ」
「数少ない楽しい思い出だよ」
謙太が菜々子の肩を抱き締めると、革がこすれる音がする。頭を寄せると、ぎゅっと引き寄せられた。
「俺ずっとこうしていたい。菜々子様すぐにいなくなっちゃいますから」
「お腹空いたね」
「なんか食べていこうか。俺、今ちょっと金持ち」
と、謙太が自分の胸元を叩く。
「どうせ、お年玉をもらった分際でしょう?」
二人はしばらく砂浜の上を歩く。菜々子は、もう一度湯河原で食べておきたいものは何かを考えた。
実家は忙しかったが、町内会の付き合いもあってか、家族でよく外食した。母は海鮮が好きで、父は肉が好きだった。
幾つかの懐かしい店が思い浮かんだが、どこへ行っても思い出すのは急に不機嫌になって小言を口にする母の表情のような気もした。
「ようし、決めた。謙太に特別、私の大好物をご馳走してあげる」
「まさか、また牛丼って言わないよね?」
「あ、言うつもりだった」
「でー」と、背中を曲げる謙太を笑いながら、
「ではなく、しょうゆワンタンチャーシューラーメン、鶏ガラスープ。どうよ」
「お、ちょっといいね」
「めちゃくちゃいいって。行こう!」
二人でふたたびヘルメットをかぶり、オートバイに跨った。

駅から少し離れたラーメン店は、受験生の頃に、菜々子が湯河原に戻っている間は、一人でよく訪れた店だ。ラーメンを待つ間にも、参考書を開いていた。
心が強くいられた頃。家にいても気持ちが落ち着くことはなかったが、自分が描く未来像に向かっているという強さがあった。もがいたらその先には光があると信じていたし、今だって本当は変わらないはずだ。
今日はそう思える。
暖簾をくぐって二人で待っている。
「あらら、品のいいおスープですこと」
運ばれてきた器の澄んだ色のスープを覗き見て、謙太は嬉しそうにこちらを見ている。
「ボリューム結構あるから、負けるなよぉ」
同じものを頼んだくせに、なぜかそう励ましている。
「これはいいな。好きな味です」
と、謙太は長い指で箸を持ち上げる。長い髪の毛を首筋で一つに結わえて、懐かしいスープをすくい、こんな時間が過ごせていることが幸せだと菜々子は思った。
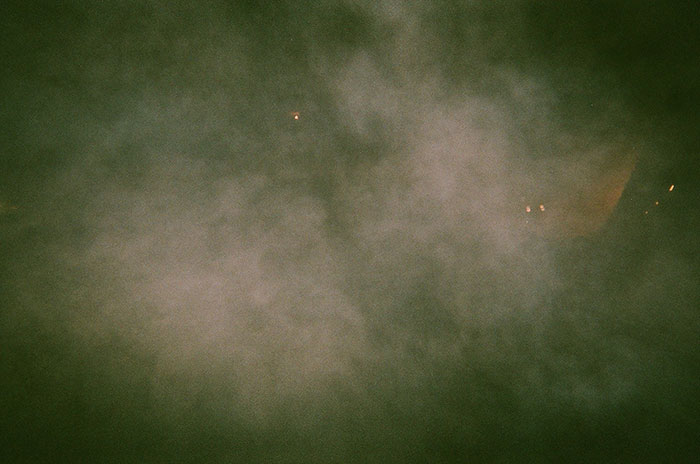
オートバイを停めた駐車場へ戻っていくと、すでに日暮れが始まっていた。
空の色がここからは刻々と変わる。いつも謙太はそれを楽しみにしている。
すでになかなか良いあわいの色で、カメラを向けるのかと思っていると、謙太が不意に自分を呼んだ。
「ナナコ」
「あ、結局謙太のお年玉にごちそうになっちゃったね。お父さんかおじいちゃんか、ありがとうございます」
と、ふざけて言うと、
「そうじゃなくて、俺、今日実は菜々子の家の前まで行ったんだよ。そうしたらメールが来たから、喫茶店に引き返した」
「なんだ、言ってくれたらよかったのに」
「お父さんの車でしょ? 停めてあった銀のセダン」
「うん、そう。地味なのね」
「地味じゃなかったよ。車の希望ナンバーさ、775だった。菜々子じゃん」
「まあ、そうだね」
「余計なことは言わないつもりだったけど、何かが掛け違えになっている気がする。事実は事実だから、それに対して理由はあるはずだけど、ご両親は知っているのかな」
「わからないんだよね、それが」
駐車場の小石が、足元で音を立てた。
新しく入ってくる車のライトが眩しくて、謙太に近づくと体を少し引き寄せてくれた。いつもそうしてくれていたのかもしれないが、気づいてもなかったし、正直言うと、普段はこんなもたついた時間が苦手だった。謙太が何かを話すタイミングがいつもちょっと遅くていらいらするのだ。だいたい、ラーメン店でだって、その前の海岸でだって、話す時間は十分、あったではないか。
でも今は、謙太が一所懸命伝えようとしてくれているのを感じた。

「大事なのは、事実そのものというより、菜々子がこれからどうやって家族と向き合えるかということだと思うから」
「わかってる。わかってるよ、謙太。ありがとう」
驚いたようにこちらを見ている。
「謙太が調べてくれた病院へ行ってみる。自分が生まれた場所が本当にそこなのか、まず確かめてみる。それで、本当に私を産んだ人が誰なのかも、教えてもらえるといいんだけど」
グローブをはめてシートに座った謙太と重なるように、菜々子はタンデムシートに跨った。
次回は2月5日(金)更新
PHOTOS:秋

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.