ryomiyagi
2021/02/05
ryomiyagi
2021/02/05
※本記事は連載小説です。
第7章
菜々子(3)母子手帳
全体に白い色調の空間。そのあちらこちらに、観葉植物が配置されている。受付の壁にもアートパネルのようになった植物があり、気持ちを落ち着かせようと眺めているうちに、よくできた人工植物であると気づく。
それを思うと急に、今いる空間すべてがまがいものに見えてきた。

待たされたのは、三十分ほどだったろうか。
「宮本さん、宮本菜々子さん。診察室一番にお入りください」
デニム地のジャケットを着た菜々子は、ショルダーバッグの肩紐を手でつかんで診察室へと入った。
「お待たせしましたね。今日は、宮本さんは妊娠の検査でよかったですか?」
パソコンのモニターに打ち込まれたデータ。頭の形に沿った、ロマンスグレーに大きなフレームの眼鏡をかけた医師がそう言った。
彼の机の上には、彼と父なのか、山頂にいる写真が立てかけられてあった。
「ええと、これね?」
と、看護師に確認している。
「先ほどのお小水の検査では、まだ反応は出ていないようですが、子宮の方をちょっと拝見しましょうね」
医師の言葉を合図に、看護師がカーテンで仕切られたスペースへと菜々子を案内する。
「ズボンと下着は脱いでいただいて、この椅子に座ってお待ちください」
産婦人科受診における手順は、知識としては持っていた。この椅子に座ると、やがて両足が大きく開くように作動する。カーテンで仕切られた向こう側で、医師はラテックスの手袋をつけて、検査をする。妊娠だけではなく、子宮筋腫や頸癌、体癌などもそうして検査をするはずだ。
わかってはいるが、座るのをためらっていると、
「すぐに済みますよ。痛みはね、そんなにありませんよ」
ベテラン風の看護師がカーテンをのぞきそう言ったが、菜々子はやはり椅子には座らなかった。
「違うんです、すみません」
そう答えると、妊娠を恐れてナーバスになった患者だとでも思ったのだろうか。
「あらあら、どうしましたか?」
看護師が、慌てている。
「子宮の様子だけでも診ておかなくてよかったですか?」
手袋をつけて準備をしていた医師が、カーテンの向こうから訊ねてくる。

菜々子は、脱ぎかけていたジーンズの前ボタンを閉めた。
「お話があってきました。というより、伺いたいことがあって。こんな形で訪ねてすみません」
「なんでしょうね。ご相談でしょうか?」
手袋を取って手を洗い再び、机に向かった医師の前に、菜々子も座った。医師の白衣の胸には、
〈高山産婦人科医院 医長 高山博将(ひろのぶ)〉
と、ウッドに黒の文字で印字された名札がつけられている。
菜々子が黙っていると、医師は少し表情を曇らせて、机の上を指で幾度か叩いた。ふっくらして清潔そうな手だった。
実家から持ってきた、角の折れ曲がった母子手帳を机の上に置く。
「あの、1997年に私は、この病院で生まれたようなんですが、その時のことを伺いたくてきました」
「なるほど」
その手が伸びてきて、母子手帳のページを開いた。
「拝見しましょう。確かに、当院で父が担当させてもらったようですが、それが、どうしましたか?」
もう一度、朗らかに訊かれた。
「私はここに書かれている宮本菜々子と申しますが、母の子でも、父の子でもないようなんです」

先ほどの手の動きが、さらに激しくなって、机をコンコン叩いた。自分でも気づいていないようだった。
「それはまた、なぜ? どうしてそう思われたんでしょうね?」
「はい。自分でDNA検査をしたからです。私は医学生です」
コンコンという音は、やがてゆっくり止まった。
「なるほど」
高山は、鼻の下に拳を当てて、看護師に目配せした。困ったね、という阿吽の目配せなのか、待合室にいる他の患者の様子を見て来るようにという合図か、いずれにしろ迷惑はしているようだった。彼にとってはそう深刻ではない風に。
「さて、どうしましょうかね。今日はこの後も、予約が続いておりまして」
そう言いかけた言葉を、菜々子は遮った。
「でも、ここに書かれている私の血液型も違っているんです」
医師は再び、母子手帳をパラパラ開く。
「いや、それは不思議な話だな」
一番そう感じているのは自分だと、菜々子は思う。だからこんな風にやってきたのだ。普通に面会を申し込んでも、受けてもらえないような気がしたのだ。
「先生、午前の予約の方だけで、あと三人おられますが」
看護師がそう言付ける。
「宮本さん、事情はなんとなくわかりました。理由が知りたいわけですよね。今現在、私の方では何とも答えられませんが、一旦、この件を父にも確認させてもらって構いませんか? 母子手帳の内容を控えさせてもらいますね」
高山が、壁の時計を見やりながら、そう確かめてきた。菜々子がうなずくと、
「コピーを取らせていただいて」
看護師に、指示を出し、またコンコンを始めた。
急に患者のふりをしてやってきたのは自分なのだし、次の患者さん方がいるのはわかっていた。けれど、うやむやにされるわけにはいかなかった。
「こちらの先生は、ご健在なんですね?」
戻された母子手帳にあった、〈高山義哲〉という名を指さす。
「まあ、なんとか」
菜々子はその言葉に、すでに面倒なことからは逃げ腰であるような狡さを感じた。
「こちらの先生に会わせていただきたいんです。今は、おいでになりませんか?」
産院といえども、小さくはない。二階は病床になっているようだ。
謙太が言っていたように、〈不妊外来〉の診察室もあり、そちらには女性の医師の名札がかけてあった。

「父も体調が万全ではないものですから」
明らかに、診察室に入ったころの朗らかさは医師からは消えていた。
「でも、答えてもらわないと困るんです。何かが違っているはずなので」
「あの、宮本さん。必ずこちらから、数日のうちにご連絡します。逃げも隠れもしませんから、それは信じてください。ただ、血液型とDNAのことは、間違いないのですね?」
菜々子は慌てて、診察台の横に添えられていたカゴの中のショルダーバッグに手をかけ、ファイルを抜き出した。
献血の際に送られてきたラブラッドの書類と、法医学研究室で自ら調べたDNA鑑定の結果だ。DNAの十五座位、それをプリントアウトした時の、迷子と化したような心境を改めて思い出していた。
「なるほど」
医師は、大雑把に資料を見て、ただそう呟いた。
「少し不躾な質問だとは思いますが、この新生児があなたであるというのは、間違いはないのですね?」
それには、菜々子は答えに詰まった。
確かに、そんな証明はどうしたらできるのかわからなかった。母子手帳に記された生まれたての人間が、自分かどうかなど、どうしたらわかるのだろう? 誰にもわからないのではないのか?
父と母の間に体重およそ3000グラムで生まれた血液型O型の女児が、自分ではない。確かにそれが一番、この産院においては考えられる可能性には違いなかった。

「生まれた時には、私は猿のような赤ら顔でした。こちらと思われる病室で、父と母の間で抱かれている写真も見たことがあります」
「あなたは、猿とは程遠いですけどね。ずいぶんお綺麗ですよ」
そんな冗談に付き合っている余裕がなくて黙っていると、
「ご両親とは、もう話されたんでしょうか?」
菜々子が首を横に振ると、前髪がさらりと顔にかかり、それを耳にかけた。
医師を腕組みをして、椅子の背にもたれた。少し唸った。
「二十二年以上前ですか。そうなるとカルテも残っているかどうかですが、必ずご連絡はしますので。あの、今の時点では、いろいろ考えすぎてもね」
菜々子は医師の顔を見上げた。困惑はしているものの、いかにも軽い言い分に感じた。清潔な白衣は、それだけで医療従事者を誠実そうに見せなくもないが、皆が同じコスチュームでいるから余計に個性は際立つのだ。
「ご連絡をお待ちしています」
「ご連絡先を受付でいただくように」
医師の言葉で菜々子が立ち上がり、ドアノブに手をかける。
ドアを閉めると、看護師への声が聞こえた。
「今日この後の、院長のスケジュールを訊いておいてくれる?」
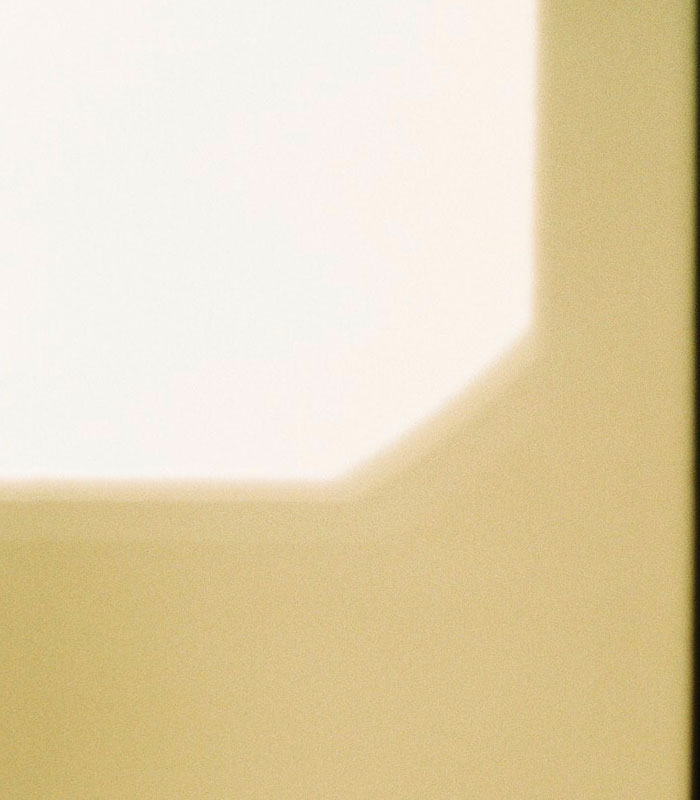
再び戻った待合室で、下腹部のせり出した妊婦たちに混じって座った。妊娠を控えた患者、妊娠を望む患者、妊娠の予後を見てもらうのか、赤ん坊を抱えた患者もいる。
かつては若い日の母も、ここにそんな一人として座っていたはずだった。そのとき腹にいた子は、自分ではなかったというのだろうか。
菜々子の名が呼ばれた。
「宮本さん、今日お会計はないそうです。ご連絡先をうかがうようにとのことです」
受付で、携帯電話の番号を書き入れようとボールペンに力を込めた時、廊下の向こうから、杖をついて歩いてくる白衣姿を見つけた。
一歩一歩、足を引きずりながらも進む医師こそ、高山義晢に違いなかった。
毎週金曜日更新
PHOTOS:秋

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.