akane
2021/02/12
akane
2021/02/12
※本記事は連載小説です。
第7章
菜々子(4)院長室
ゆっくりと、またゆっくりと、老医師は杖に体重を預けながら歩いていた。それでも、白衣というユニフォームがひどく板について見えたのは不思議なほどだった。

菜々子は、すぐには近づかなかった。ただ立ち上がった場所で、じっと見つめていた。その人に向かってどう声をかけようか、考えあぐねていた。珍しく、慎重になって。
やがて廊下の角を曲がって、彼が院長室なのか、何かの部屋の方へと入っていこうとしたので、駆け寄った。
身重な人たちの多い産婦人科医院において、それは少し目立ったのか、医師は視線を上げた。
「院長、待っていただけますか?」
近づいて、やや大きめな声をかけると、軽く耳の横に手を上げた。私は聞こえていますよ、と言いたげだ。にこやかな福々しい笑みが返ってきた。
すでにまばらになった白髪をきれいに櫛で撫でつけたヘアスタイル、背中が曲がっているからか、その頭頂部は一六七センチの身長の菜々子には、見下ろす格好になる。
「何か私に御用でしょうか?」
いかにも温厚な静かな声が返ってきた。
「先生? 私に覚えはありませんか?」
こう言ってみようと決めていた。覚えはないかと訊かれて怪訝な顔をする人間は、脛に傷がある。信用がならないもんだ、とよく父が客人たちを見定めるように呑気に口にしていた。
医師は、うーんと唸りはしたが、やはり笑顔のままだ。菜々子は、自分自身に、こんな姑息なことをして何になる? と問いかけながら、呆れるほど朗らかに言った。
「ごめんなさい、実は先生とお会いしたのはまだ赤ん坊のときです。二十年以上も前に、先生に取り上げていただいた子どもです。それから元気に育ち、今は医学生です。生まれた当時のお話を伺いたくて来ました」
「ほう、そうですか? 二十年前」
年月分の記憶を振り返っているのか、眉を寄せた。廊下を見渡し、
「よかったら、お入りになりますか? 私はもう今日は用なしの身ですから」
そう言うと、杖を持ち替えて、扉のノブを回した。ぎこちない動作だった。
「人工膝関節の手術を受け損ねてしまいましてね。MIS、最小侵襲手術の機会を待っていたら、適応年齢を超えたというんです。医者の不養生そのものです」
医学生だと名乗ったからなのか、専門的なことまで話しながら、部屋に招いてくれた。机と小さな応接セットのある部屋で、医師は内線ボタンを押して、
「コーヒーを二つね。あなたもコーヒーでいい?」
と、訊ねてくる。
うなずくと、彼はソファに向かい合って座った。

「さて、何年と言いましたかね?」
答える代わりに、菜々子はショルダーバッグから母子手帳を取り出した。
バッグの中には他に、目前の老いた人物を驚かせるかもしれないファイルが出番を待っていた。
「湯河原町……、ご両親は、旅館をされていましたかな?」
「はい。今もやっております」
医師は再び眉を寄せた。名札には確かに、〈院長 高山義哲〉と書かれてる。その名は母子手帳に記入されている担当医の名前だ。
「この時代は、何しろ出産が多かったんですよ。湯河原、そうでした」
白い手で母子手帳をめくる医師がそう呟いたとき、菜々子の中では医師はきっと覚えているはずだ、と感じた。
「なぜ、湯河原の両親がこちらの産院までやってきたのか? 不思議だと思ったのは、最近なんです。先生のクリニックは、当時から不妊治療で有名だったのですね」
「まあ、そうですね。ずいぶん遠くからも来られましたよ」
一層誇らしげな柔和な笑みを浮かべた。
「体外受精、中でも卵子凍結の受精に、秘密裏に取り組まれていたそうですね」
医師の目の奥がかすかに光ったように、菜々子には見えた。
正月明けから、謙太に手伝ってもらい、菜々子は高山のクリニックについて調べていた。
現代で言うところのネット上の口コミにおいても、評判は極めて良い病院だった。
先ほど会った医長が前線に立ち、だが目の前の御大である院長が時折見舞うと不妊の患者が決まって身籠もる、という都市伝説じみたことまで書かれてあった。
そうした最近のレビューとは別に、謙太が市井の人々のブログやツイッターに書かれたクリニックの名を検索してくれた。
多くは無事に出産を迎えた患者たちの報告だったが、中に長い日記調のブログの執筆者がいるのを、謙太が見つけた。
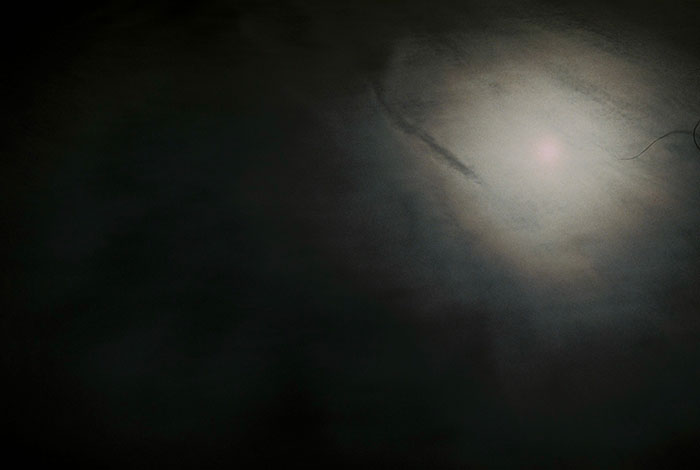
〈長い長いトンネル〉
そんなタイトルがついていた。
〈不妊治療三年目に入った。長い長いトンネルを、はじめは夫婦二人で歩いているつもりだったけど、今は自分一人きりのような気がする〉
夫の無理解が綴られている。
〈クリニックにいると、おめでたの人たちがすぐにわかる。自然と鼻や口の周りが緩んでいるから。
クリニックを変えたい気もするけど、母がここの信者だ。自分の住まいに近いからというのもあるはずだけど。昔は、まだ未承認だった卵子凍結保存による人工授精もしていて、近隣の人たちが諦めかけていたのに、赤ん坊を授かっていったのを忘れられないと話す〉
本人は仮名、顔写真もないが、世田谷のT医院とあり、産院の写真はばっちり正面から写している、という、匿名性が守られているとは言えない投稿だった。
その〈昔〉がいつに相当するのかはわからないが、おそらく今は好々爺のようにしている高山院長が、若い日に秘密裏に行なっていた医療があったのだとは思う。
自分の部屋で謙太と並んでパソコン画面を探しているうちに行き当たったこと。第一に自分は、人工授精でできた子どもなのだろうという一つの確信だった。だからわざわざ、世田谷の産院で生まれたのだ。
「人工授精に関心がありますか? それだったら、今の私よりはずいぶん息子の方が答えられると思いますよ」
そこへ、コーヒーが運ばれてきた。チェックのベストを着た事務職の女性に、医師は、
「この方はね、医学生だそうですよ。当院で生まれたそうです」
と、菜々子を紹介した。
「まあ、そうでしたか」
彼女も満面の笑みを向けて、トレイを胸に当てて戻っていった。
「先生、こちらを見ていただけますか?」
菜々子がバッグから、資料を取り出そうとした時だった。
「お父さん」
と、先ほどの息子の方の医長が慌てたように扉を開けた。
「院長、今日はもう回診は終わりでしたか?」
普段は院長と呼びかけているのか、そう言い直した。
「ああ、この方はね」
父の方は、事務員へと同じ紹介を、息子にしかけた。
「知っていますよ。先ほど、診察室へとやって来られましたから。あとで私が院長とお話する必要があります。こちらからご連絡すると、先ほどお伝えしませんでしたか?」

不機嫌な声色なのに、よほど身についているのか温厚な笑顔なのが、妙に怖かった。
「でも、直接お伝えしますね。先生がここに書かれた私の血液型は違っていました。それだけではなく、DNAも……。自分でこんなことを調べる気持ちを、少しでもわかっていただきたいんです」
自分でそう口にした言葉に、内心、笑ってやりたくなった。いつもは、自分の気持ちなどわかるはずがないと、友人たちや謙太の優しさまではねのけてきたというのに。今は少しでもわかってほしいなどと口にしている。
目の前の老医師は、角砂糖を二つくわえたコーヒーを、左手でソーサーごと持ち上げて、右手で小さく傾けながら飲んだ。
口元にも目の下にも皺が寄っていた。全てを飲み込んできた年輪のように見えた。
次回は2月26日金曜日更新
PHOTOS:秋

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.