akane
2021/01/15
akane
2021/01/15
※本記事は連載小説です。
第6章
ジヒョン(4)シェヘラザード
尊とジヒョンは、それぞれ二十三歳になっていた。
六歳で別れたきり、十七年もの間、日本と韓国にて各々育った。
「織姫と彦星は、一年に一度会うんでしょう? 私たちも、六歳にタイムスリップをして、一年ずつ再会してみないかな」

ジヒョンの提案に、尊は織姫を通じて、返事をした。
「やってみよう。むずかしそうだけれど」
「どちらから、始める?」
「君から」
ジヒョンは精一杯の日本語で、尊の言葉は織姫が発する。どちらも、片言に響く。片言とは、幼児が発するようなたどたどしい不完全な言葉。でももう自分たちは、幼児ではない。生身の体を有した男と女なのだ。
「私が、六歳だった時、ソウルコウガイのシンコウトシで暮らし始めた。学校にすぐになじめなかったよ」
そしてよく尊のことを思っていた、と心の中でジヒョンは付け足す。
「六歳の僕は、地元の小学校に上がった。サッカーを始めたんだ」
ボールを蹴る尊の元気いっぱいの姿が、すぐに思い浮かんだ。
「じゃあ、次は尊くんから」
瞬きした尊の目が動く。
「七歳の夏に、大阪に引越しした。実はその年から、うちは父の転勤が続いた。その夏は特別暑くて、長く感じたよ。またサッカーチームに入ろうとしたんだけど、うまく仲間に入れてもらえなくて、自転車に乗り始めたんだ」
「私の七歳は、両親がお祝いの会を開いてくださった。普通は一歳でやるトルチャンチというお祝いを、韓国に帰って一年だからと言って。でも多分、友達ができるように考えてくださったんだ。黄色いチマチョゴリを着たよ」
「見たかったな。今度、写真を見せてよ」
尊は言う。
そうやって話していって、ようやく十歳にまでなった時に、尊は少し苦しくなって、ジヒョンが吸引した。
どの年を思い出しても、ジヒョンの記憶には、心の中で尊を探す気持ちが宿っていた。尊の方は、どの年も力一杯一人で歩いているように見えた。

「十三歳に、中学生になった。韓国は受験戦争が始まる。私は夜遅くまで塾で勉強した」
いつか日本に行って、尊に会いたかったから。ジヒョンは、毎日のように通った、市街地にあるビルの三階の塾の様子を思い出しながら話した。
「塾の壁にたくさん、英語の言葉が書かれていたよ。たぶん、英語の先生がそういうのが好きだったから。一番覚えているのは、インドのマハトマ・ガンディが言ったこと。毎日、その言葉が見える席に座ったから、すっかり覚えた。
英語は下手だけど、言ってみようか。
〈Lives as if you were to die tomorrow.
Learn as if you were to live forever〉
通じたかな?」
「きれいな英語だったよ」
ジヒョンは褒められて、自分の頬が赤らむのを感じた。
「どう訳そうか?」
尊が訊いてくる。
「明日、死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」
病人の尊には残酷に響く言葉だったろうか。けれど彼は、少しの間を置いてこう言った。
「ガンディは、さすがだ。僕も、まだ学べってさ」
尊はそう言って、目を閉じた。
「少し休もうか?」
「雪、まだある?」
尊がそう訊いてきた。ベッドを起こしてあげようかと思ったのに、尊は目を横に動かした。ジヒョンが代わりに尊の目になっていいのだと感じた。
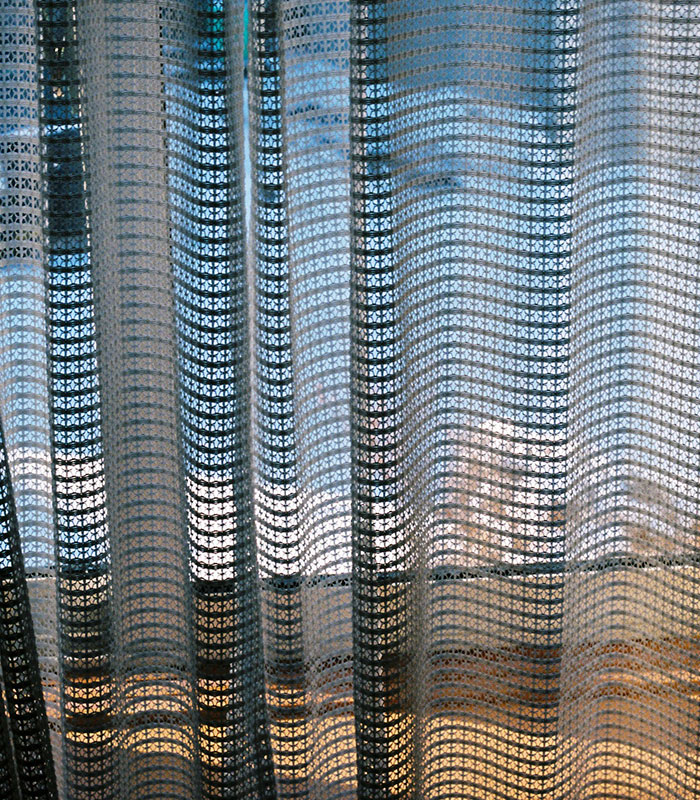
窓辺に寄って、外を眺める。
窓を開けてみた。冷たい空気が流れ込み、同時に中にこもっていたどこか重たい熱気が押し出されていくように感じた。
「本当よく降ったんだね。まだ、積もっているよ。少し溶け始めたところが、光っているよ」
「触りたい」
尊から言葉が響いた。
「私も」
ジヒョンは玄関から外に出た。階段を降りていき、道路を渡った向こう側の樹木の根の周りに降り積もった、まだ汚れていない白い雪を両手に載せた。履いてきた靴は丈が短くて、すぐに埋まってしまった。その冷たさまでが、かけがえがないのだと感じた。尊が感じたくても感じられない感覚を、全身に浴びていたかった。
すぐにジヒョンの手が赤くなった。お団子を二つ。大きなお団子をいつも尊が作ってくれて、その上にジヒョンが小さいのを載せた。
赤い実を押し込み目にして、枝を挿して両手にしてやる。雪団子の表面は丸く整えられて、両目もきっちり押し込み目にしている。幼稚園の頃より、どこか大人びた雪だるまを両手で抱えて部屋に戻ると、慌てた様子の母親が、吸引をしていた。
「ごめんなさい。私のせいです」
思わず雪だるまを手に乗せたまま、立ち尽くしてしまう。
「違うのよ、大丈夫、ジヒョンちゃん。これが尊の毎日なの」
母親が、尊の背中を撫でている。
苦しそうな息遣いが、やがて落ち着いていった。
「僕はただ、雪でよかった」
尊は、崩れ始めた雪だるまを見て、そう言葉を響かせ、少し眠った。

七夕ごっこは、十四歳までで陽が暮れた。
十四歳になった時、尊の話にははじめてのガールフレンドが登場した。一緒に登下校をするようになったそうだ。活発な子で、二人で自転車旅行をした。
「キスした?」
ジヒョンがそう訊ねると、
「もちろん」と、答えが返ってきた。
尊はしだいにジヒョンに気遣いなどしなくなっていった。ジヒョンの中で甘やかな幻想が崩れていく。目に浮かんだ愁いがあったはずなのに、
「初恋だったんだ」と、まで尊は続けた。
そうか、尊の初恋はその子だったんだと思う。
「続きはまた、明日ね」
そう言って、尊の手に触れて、ジヒョンは母親と役割を交代しようと思った。急に疲労に襲われた。尊がはじめてのガールフレンドの話なんかをするからだろうか。
「終わらないと、いい」
部屋を出ようとすると、織姫がそう伝えてきた。
「でも、今日はもう遅いよ」
「そうだね」
扉に手をかけると、さらに織姫が言葉を発した。
「〈シェヘラザード〉は知ってる?」
「よくわからないけど、確か、曲の名前?」
クラシックの曲の名前として聞いた覚えがあるだけで、よくわからない。
「いい曲だから、後で聴いてみて」
急になぜ尊がそう言ったのかもよく考えずに、「おやすみ」と言って、ジヒョンは部屋を出た。

リビングで母親に伝えて、ベッドを借りている二階の客間へと上がった。少し冷たい寝具にジヒョンはそのまま横たわった。
カーテンのすぐ向こうに夜気が広がっているのを感じる。雪は止み、隙間から青い夜空が見えていた。頭だけ冴えていて、スマホでシェヘラザードを探した。
音源を探すと、バイオリンの美しい旋律から始まる曲が流れてきた。
そのまま音に身を委ねながら、少し眠ったようだった。
目が覚めて、曲のことをふと調べてみた。ガンディ曰く、〈永遠に生きるかのように学びなさい〉。
調べると、シェヘラザードは、『千夜一夜物語』を元に作られたロシアの交響曲だとわかる。
暴君だった王を鎮めるために嫁いだシェヘラザードは、毎夜、物語を聞かせる。
「続きは、また明日の夜に」
王は、かつての妻に裏切られた憎しみから、女たちを抱いては殺し、抱いては殺しを繰り返していたが、物語の続きを聞きたいがために、シェヘラザードとの夜を重ねる。
シェヘラザードは、命がけで物語を紡ぎ続ける。
バイオリンの旋律は、その物語の音色だったのだ。
終わらないよ。
それでずっと、尊くんが生きていてくれるなら、二人で毎日話し続けよう。
ジヒョンは、自分の十五歳の架空の物語を想像し始めた。本当はただ塾と学校に通うばかりの退屈な十五歳だったから。
次回は1月22日(金)更新
PHOTOS:秋

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.