akane
2019/12/21
akane
2019/12/21

世代を超えて大人気の、若き天才作家――。直木賞作家の辻村深月さんのことをそう呼んでも異を唱える人は出版界にはいないでしょう。’04年に長編青春ミステリー小説『冷たい校舎の時は止まる』でデビューして以来、15年間で出した単行本は長編、短編集等併せてじつに35冊! その多くが映像化や漫画化されたりしていることからも、いかに多くの人の心を捉えてきたか想像に難くありません。またデビュー作でメフィスト賞を受賞して以来、毎年のように主要な文学賞を受賞するか候補になり、出版界で高く評価されてきました。
「デビュー当時、担当編集者が『記念周年のときなど、いつかデビュー作の愛蔵版を出せるといいね』と言ってくださって。それを糧に頑張ってきたところもあるのですが、作家デビュー15周年の今年に出していただき、夢がかなったんです。15年たって、今、自分のなりたかった作家になれたと思っています」
にこやかに語る辻村さんが、デビュー作を書いたのは高校3年生のときでした。
「受験勉強から逃げたくて書き始めたのが『冷たい校舎~』の前半部分。大学に受かったら解放感から書かなくなり、その後就職活動が嫌で続きを書きました(笑)。実家に戻ってOLになり、何度も手を入れて完成までに2年かけようやく投稿したんです」
デビュー後は執筆に邁進。
「’05年の『凍りのくじら』は章タイトルをすべてドラえもんのひみつ道具にした小説。本作と’06年の『ぼくのメジャースプーン』でミステリーの要素で女のコの自意識や子ども同士の複雑な関係を書けるとはっきりわかり、作家としてやりたいことが見えてきました」
『ぼくのメジャー~』は辻村さんに作家としての在り方を示唆した作品でもあったと続けます。
「これまでは小説は自分の中で結論が出ているから書くものだと思っていたのですが、書きながら主人公と一緒に迷い、考えてもいいんだと思ったんです」
デビューして数年のこの時期に、辻村さんの作家人生を方向付ける作品も2つ誕生します。’07年の『名前探しの放課後』と’11年の『オーダーメイド殺人クラブ』です。
「『冷たい校舎~』で10代の子どもたちの群像劇と密室ミステリーを書き、『名前~』で地方都市を意識し始め、『オーダー~』で初めて中学生を書き、長く言語化できなかったことがようやく言葉にできました。らせん階段を上りながら、高さの違うところから次の作品が書けた感じです」
地方都市に住む10代の葛藤、女子の自意識やモテ格差、母と娘の関係性などをミステリーのテクニックを使って書く――。幅広く支持される作家・辻村深月の作風はこうして確立していきました。
「この3作品があったから『かがみの孤城』が書けたと思います」
さて、新作『ツナグ 想い人の心得』は、'10年のベストセラー『ツナグ』の続編です。
「自分はシリーズものをやらない作家だと思っていたのですが、前作は映画になったこともあって、さまざまな感想をいただきました。私が書いたことを超えて、読者の方々が自分の物語として読んでくださっていたんです」
辻村さんは少し早口になり作品に込めた思いを語ります。
「前作『ツナグ』は『ぼくの~』を読んだ新潮社の編集者・木村由花さんから“ぜひ一緒にお仕事を”と、熱いメールをいただいたことがきっかけ。当初は現実ではかなうはずのない望みをかなえる不思議な力が登場するシチュエーションで書こうと思い、死んだ人に会う設定を思い付きました。しかし、まだ20代後半。“別離の経験もそんなにないだろうから人の死について書くのは早いのでは”と周囲に言われたりもしましたが、だからこそどんな依頼人に対してもフラットに書けると思って。ですが書いているうちに“死んだ人間を呼んで再会するなど、生きている人間のエゴでは”と思うようになり、私の逡巡がそのまま主人公の歩美の葛藤になりました」
前作を世に送り出した翌年に、東日本大震災が起こりました。
「震災のあとだったら、この小説は書けなかったかもしれません。この9年の間に自然災害や考えられないような事故など個人の力ではどうにもならないことが多々起こりました。新作『ツナグ 想い人の心得』について、宮部みゆきさんが書評で“この厳しい時代に(中略)〈死が全てを無に帰すわけではない〉ことも思い出させてくれる”と書いてくださった。この言葉に到達したくて私はこの小説を書いたのかもしれません」
ツナグに出合えるかどうかは“ご縁”、というのがこのシリーズのルールですが、本作執筆にあたり辻村さんにも不思議なご縁が。
「由花さんに“自分より年若い人を送った人の再会を書いてほしい”と言われ、子どもを水難事故で亡くした母親の話を考えました。でも、私には書けなかった」
辻村さんにも子どもがいます。事故でわが子を亡くすことは、設定としては思いつけても書くことにどうしても抵抗があったのです。
「そんなとき、たまたま『東京會舘とわたし』という本の取材で訪れた東京會舘で、戦時中に結婚式をあげた方から届いたというお礼状を見せていただきました。その方にお会いしたいと相談したら、新婦さんが92歳でご存命とわかって。それで取材に伺ったところ、その方はまだ20代だったお嬢さまを亡くされていたんです。そのエピソードがあまりに胸に刺さり、こんな形の喪失からの人生があるのかと胸が震えました。話が盛り上がっていたとき、2歳の子をお迎えに行かなきゃと気づいて慌てたら『お母さんなんですね』と声をかけていただいたんです。私が『こんな母親でいいのかって思いながら育てています……』と思わず言ってしまったら、『あなたなら大丈夫よ!』と。するとスッと肩の力が抜けたんです。『大丈夫』と言ってもらえることはこんなにも安心感を得られることと知り、この体験をそのまま作品に書き止めたのです」
それが「母の心得」。涙亡くしては読めない中編です。
「もう一つ。実は『母の心得』を書く前に、担当編集の由花さんが病気でお亡くなりになって……。約束どおり、2作目も本にできたので、いつかツナグの歩美に頼んで渡してもらえたらうれしいと思っています」
9年を経て『ツナグ 想い人の心得』を出した辻村さんは、今、自身のことをこう分析します。
「30代になったばかりの私には、死は無情で、突然すべてを断ち切ってしまうものでした。今は“亡くなったあなたに今もここにいてほしかったことと、今の自分が幸せでいること”という両方が矛盾なく存在することがわかります。私は人は年齢とともに考え方も変わると思っていたんですが、それは劇的に起こることではなく、緩やかに熟成していくようなものなのだと思えるようになりました。
そうやって考えると作家は幸福な仕事。20代のときに正解だと思って書いたものが今も小説の形で残っていますから。今の私だったらこうする、と思うこともありますが、それでも、今の私は昔の私に“それがあなたの正解なんだね”と言いたい。20代の私にとって大事だったことを、きっと今まさに必要としてくれる読者の方もいらっしゃると思うんです。その年の自分に戻れないからこそ、その時々の思いを小説にしていくことが大事なのだと改めて感じています」
辻村さんにとって小説とは?
「自分自身が大きな喪失を抱えているから『ツナグ』は読めない、と言われたことがあります。それもそうなのだと思うんです。それでもフィクションで喪失を描くことには意味があると思いたい。確かにネット社会では、一義的、一期的な答えはすぐ手にできますが、そこで得られるのはむき出しのリアル。リアルであればあるほど、人はもっと追い詰められてしまうこともあると思う。一方、他者の物語を読むことで他人を生きる経験ができ、それが自分の悩みから自由にしてくれることもあると思っています」
年末年始、辻村作品を堪能し、深い情愛と勇気を得て、充実した‘20年をお迎えください!

『ツナグ 想い人の心得』新潮社
’10年に出版された『ツナグ』は’11年に第32回吉川英治文学新人賞を受賞した作品。一生に1度だけ、死者との再会をかなえるというツナグ。心の支えだったのに突然死したアイドルに会いたいOL、がん告知できなかった老いた母に会いたい息子らがツナグの仲介で死者と再会する連作長編小説。『ツナグ 想い人の心得』は前作から7年たった設定。高校生だった歩美は社会人になり、仕事をしながら祖母から引き継いだツナグを行っていた。事故死した幼い娘に会いたい母、乳がんで亡くなった娘に会いたい母らが歩美のもとを訪れる。

『ツナグ』新潮社

’04年 デビュー作
「文庫は上下巻に分かれるが、上巻を高校3年の受験直前に、下巻を大学時代の就職活動中に書いた。書き終えても「名刺代わりの小説」と思うとすぐには投稿できず、地元でOLをしながら2年かけて手を入れた」(第31回メフィスト賞受賞)
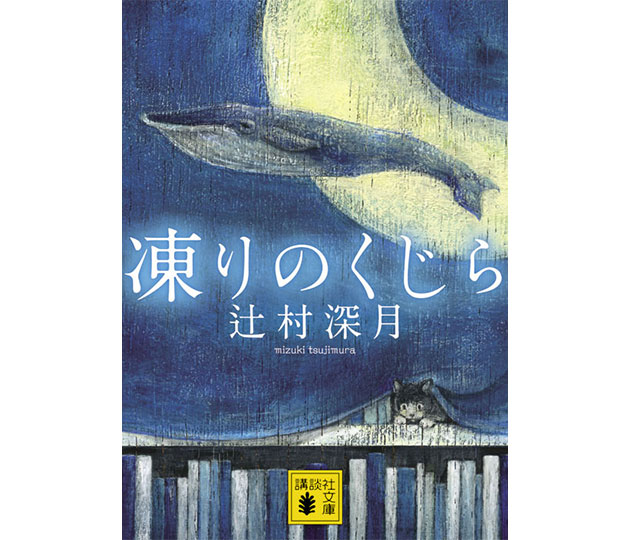
’05年
『凍りのくじら』講談社
「章タイトルはすべてドラえもんのひみつ道具の名前にした。幸せだった子ども時代の象徴として『ドラえもん』を借りた小説を書きたかった。この作品が縁で、藤子プロさんから書下ろしの映画脚本のお話を頂き、今年公開された」(第27回吉川英治文学新人賞候補)

’06年
「不思議な設定を作り、罪と罰について書こうと思ったのだが自分の中で答えが見つからないまま書き始め、書き終えたときに結論が出た。自分にとって小説は考える場なのだと実感できた作品」(第60回日本推理作家協会賞〈長編および連作短編集部門〉候補)
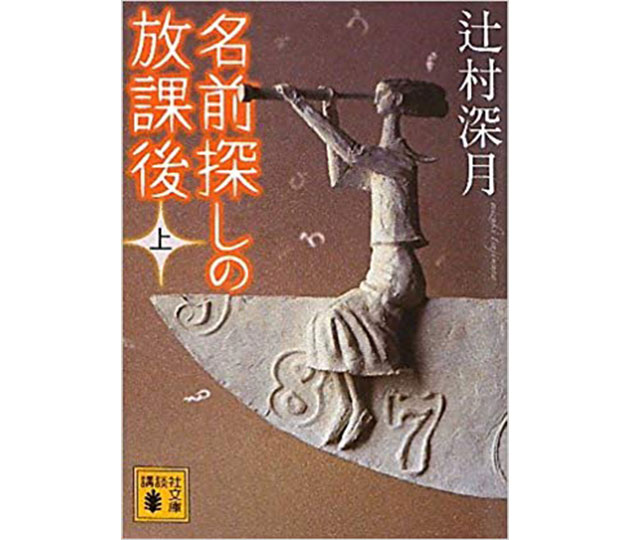
’07年
『名前探しの放課後』講談社
「『冷たい校舎~』の外側バージョン、つまり時間が戻されて同級生が自殺するのを止める設定の小説を書きたかった。地方都市を意識し始めたのはこの作品のころから。渋谷だけが高校生のいる場所じゃない、と思うようになって(笑)」(第29回吉川英治文学新人賞候補)

’09年
「この作品で地方格差と女子のモテ格差、母と娘の関係性について一生書くと決定的に自覚。小説家としての“青春時代”の代表作。“意味はわからないけど忘れない”タイトルを付ける勇気が出た作品でもある」(第142回直木三十五賞候補、第31回吉川英治文学新人賞候補)

’11年
「中学生は高校生ほど自由でなく小学生ほど無垢ではないと思って書いた。中学時代、すがるように本ばかり読んでいた。そんな封印していた中学時代の記憶を開けることができ、当時、言語化できなかったことをやっと言葉にできたと思えた作品」(第145回直木三十五賞候補)
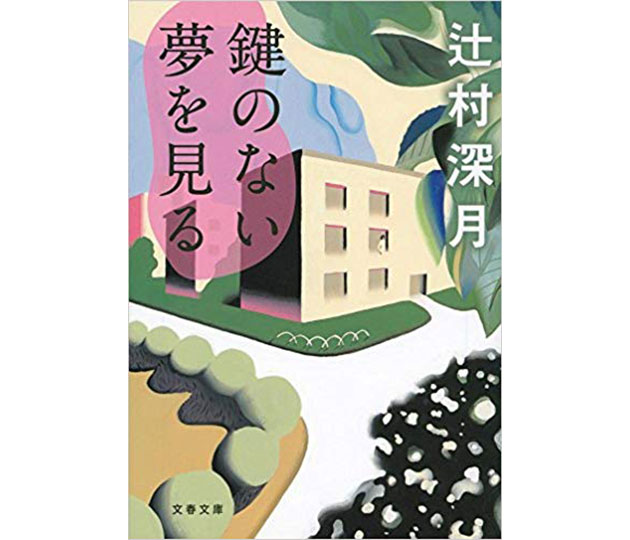
’12年
『鍵のない夢を見る』文藝春秋
地方紙の三面記事にあるような小さな記事をモチーフにスキルを使いながら初めて書いた大人向けの犯罪小説。地方に生きる女性の閉塞感が出ていると言われたが、自分としてはこの作品を書いて、もう地方との闘いをしなくてもいいと実感。(第147回直木三十五賞受賞)

’13年
『島はぼくらと』講談社
「地方を肯定しようとの思いで書いた作品。それまで私の小説は圧倒的に“教室小説”だと思ってきたが、この作品で高校生たちを教室から太陽と海に囲まれた外に出した。そうしたことで部活でもなく家族関係でもない、新しい成長小説が書けたと思う」(第11回本屋大賞第3位)

’15年
『朝が来る』文藝春秋
「『辻村さんに書いてほしいテーマがある』」と言われ挑んだ作品。不妊治療や卵子の老化などについては考えていたが、養子をもらうということは考えていなかったので、新しい題材に飛び込めると即答した」(第13回本屋大賞第6位、‘20年、河瀬直美監督により映画化が決定)

’16年
『クローバーナイト』光文社
「桐野夏生先生のあとの連載小説だったのでプレッシャーもあった。育児の日常を書いているつもりだったが、途中で“普通って何?”がテーマだと気づいた。タイトルは4人家族のなかの父親をイメージしたが、月刊誌『VERY』の連載でなければ書かなかった主人公かも(笑)」

’17年
『かがみの孤城』ポプラ社
「現段階で私の集大成。今を生きる中学生・高校生が“自分のために書かれた小説”と思ってくれたらうれしい。10代の子が読んで親に薦め、親が読んで子に薦めるという現象が起こり、世代を越えて読んでいただきとても幸せ。本屋大賞にも感謝!」(第15回本屋大賞第1位)
PROFILE
つじむら・みつき◎’80年、山梨県生まれ。千葉大学教育学部卒業。’04年『冷たい校舎の時は止まる』でデビュー。’11年『ツナグ』で第32回吉川英治文学新人賞、’12年『鍵のない夢を見る』で第147回直木三十五賞、’18年『かがみの孤城』で第15回本屋大賞を受賞。著書に『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』『朝が来る』『東京會舘とわたし』など
聞き手/品川裕香
しながわ・ゆか◎フリー編集者・教育ジャーナリスト。’03年より『女性自身』の書評欄担当。著書は「若い人に贈る読書のすすめ2014」(読書推進運動協議会)の一冊に選ばれた『「働く」ために必要なこと』(筑摩書房)ほか多数。
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.