akane
2018/07/19
akane
2018/07/19
ーートゥローのコメントにもありましたが、フォースターは登場人物の欠点を容赦なく描写していますね。
加賀山 モーリスに対してもあまり利口じゃないとはっきり言っています。悩める主人公を一方的に応援するとかじゃなくて、時には落としてみたり、持ち上げてみたりして。同じ人でもいい面があり、悪い面がある。そういうところに公正な目を持っている作家なんだと思いました。
ーー登場人物同士が互いをどう品定めしているのかも興味深い。
加賀山 あとがきにも書きましたけど、貴族がモーリスをどう見ているかはけっこうおもしろかったです。最初の恋人クライヴの屋敷に招かれたモーリスが、母親のダラム夫人に嫌われてもかまわないとやけになって振舞っていたら、それがむしろプラスの評価になってダラム家の人々から敬意を払われるとか。
ーー感謝するのは育ちの悪い人間のすることだと考えているというのには、へー!と驚きました。加賀山さんは、今イギリスがマイブームだそうですが、あちらに行かれた時などに階級を感じること何かはありましたか?

加賀山 実際イギリスに行ったのは3回くらいで、一番新しいイギリス体験はドラマ『ダウントン・アビー』ですね。これがまたおもしろくて。たとえば、貴族たちと使用人が、鉢合わせしないような建物の構造になっていたりするんです。使用人は必ず裏から入るとか、同じ館の中に世界が二つあるみたいな。出張や観光で行っても貴族と話す機会はないのでわかりませんでしたが、小説を読んだり、映画を観たりすると、すごく多層的な国だなと思います。
ーー『ダウントン・アビー』の時代はいつ頃ですか?
加賀山 『モーリス』と同じぐらいじゃないかな。第一次世界大戦があるから、やっぱり20世紀の初めぐらい。
ーー翻訳の手助けになるようなところもありましたか?
加賀山 けっこうありました。たとえばクリケットの試合。屋敷のホスピタリティだと思うんですけど、屋敷が参加者全員の食事を出したり、全面的にアレンジして、村で働いている人たちを呼んで試合をするというのが『ダウントン・アビー』にあったんですよね。『モーリス』にもダラム家が主催するそういう交流試合がでてきて、ああ、これじゃんと思いました。
ーー福利厚生的なイベントで、違う世界に住む人々を交わらせるんですね。
加賀山 あのときはみんな仲良くやるわけです。無礼講みたいな感じで。フォースター的に好きなテーマなんじゃないかと思います。
ーーそういう試合が大切な年中行事として機能しているのも、多層的であるがゆえですね。
加賀山 自分も含め、イギリスに夢中になる人がいるのはよくわかる。アメリカって、言ってしまえば単純ですが、イギリスはあの面積だけじゃない広がりがある感じがします。さほど大きな国じゃないけれど、あの中に日本なんか比べ物にならないくらい多くの社会がある。日本も地方によって違いはありますが、イングランド、ウェールズ、アイルランド、スコットランドは地理的にもずいぶん違うし、同じロンドンでも階級的にすごく違う。
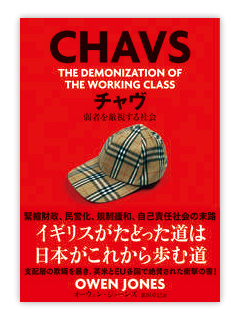
ーー『チャヴ 弱者を敵視する社会』(オーウェン・ジョーンズ、海と月社)もそういうことを扱っていますよね。いまどき、階級なんかないのかと思いきや、むしろ階級をつくるんだとか。
加賀山 そうです。新たな下層階級が必要だという話ですね。たぶんイギリス人は、階級なしでやっていけないんじゃないでしょうか。あまりにも伝統がありすぎて。
ーー這い上がるには自分の下に人をつくる。『チャヴ』が言っているのは、中流というか、総中流になるために、要するに攻撃する相手が必要だということですよね。
加賀山 チャールズ・ディケンズなんかは、どちらかというと下のほう、あまり貴族のような上のほうは扱わない大衆的な作家ですけど、一般的には、イギリス人は階級が好きなんだろうと思います。なしではいられない。フラットな社会はなかなか想像できないんじゃないかな。
ーー『モーリス』の最初のほうで、思春期のモーリスが昔からいる使用人に対して尊大な口を聞くと、使用人のほうは機嫌を損ねたふりをするけれど、実のところはそうじゃないなんてくだりもありました。
加賀山 亡くなった父親に似て「もういっぱしの風格がある」なんて言ってね。主人なんだから主人らしく振る舞えよということなんでしょう。
ーーそれによって居心地がいいというか、安心する。だから階級がなくならない。
加賀山 そんな状況下で、主人公は、階級のみならずいくつものハードルを越えていく。だから『モーリス』はとても革新的な作品なんですね。
ーーモーリスとクライヴがバイクでデートに行った先で農家のおかみさんの世話になるエピソードも、普通にしていたら出会わない者同士の接触を描いた場面として強く残っています。
加賀山 たしかにあの設定は、学校や家族というごく狭い世界だけで暮らしていたモーリスが、はじめてよその世界を知るために用意されたものですね。つまりクライヴとああいう関係にならなければ、外の世界に出て行かなかったわけです。
ーーあれ以降、待宵草が何度も出てきますよね。

加賀山 訳すときはあまり作品分析をしない方なんですが、たしかに、けっこう出てくるなとは思っていました。印象的な場面でけっこう使われているじゃないですか。ディナーの途中で抜け出して庭を散策していたモーリスがアレックと遭遇して、屋敷に戻ってくると黒髪に待宵草の黄色い花粉がふりかかっていたとか。
ーーすごく色っぽいし、夜とか闇が強調されている。待宵草の花は、文字どおり夕方に咲いて、翌朝にはしぼんでしまいます。なので、簡単に踏み込めないイメージの野茨とか、視界を遮るほどの激しい雨なんかと並んで、モーリスの秘密を周りから守る装置のように感じられました。
加賀山 なるほど。あと森もありますね。昔は森に逃げればよかったでしょ。社会から外れた人が隠れる場所が森だった。この作品では、ロンドンからちょっと離れた田舎町ペンジの、ダラム家の屋敷の前に森が広がっているというのがまたポイントなのかな。階級を超えて、森番と結ばれる話といえばD・H・ロレンスの『チャタレー夫人の恋人』が有名ですが、同じ森番との恋でも『モーリス』は階級だけじゃなくて、社会が決めたセクシャリティも超えちゃう。より一層ハードルが高い。
ーー1960年に追記された「著者によるはしがき」に、D・H・ロレンスがこんなものを書いたけど、というような箇所があってちょっとおかしかったです。
加賀山 自分のほうが先に書いたのに、あっちに先に発表されちゃったということですよね。フォースターに言わせれば。
ーー書かずにはいられなかったんですね(笑)。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.