ryomiyagi
2020/04/28
ryomiyagi
2020/04/28
ここ数年でよく耳にするようになったサステイナブル(持続可能)という言葉。温暖化する地球環境を考えることは待ったなしと言える状況ですから、それぞれが環境に対して何が出来るか、サステイナブルに暮らすために真剣に取り組まなければなりません。エコバッグを持ち歩く、ゴミの量を減らす努力をする、という初歩的なところから始めて、次に取り組むならどんな方法があるのか? 今回は、サステイナブルの為に循環型生活の少し先を歩いている浅川あやさんの暮らしから、そのヒントを見つけてみたいと思います。

「環境について考え始めたのは20代の頃で、2000年の少し前でした。京都議定書が話題になっていた頃で、「宇宙船地球号操縦マニュアル」という本を読んで、著者であるフラーの考え方にも傾倒したことがきっかけです。その概念に共感して。でも、実際に暮らしのなかで意識するようになったのは息子が生まれてからだと思います。親として、命のために、これからの未来を考えずにはいられませんから」
あやさんは泥んこになって遊ぶことが大好きな子どもでした。その背景があり、環境破壊の怖さや悲しさを肌で感じられる大人に成長。結果、そうした危機を乗り越えるための知恵を育む習慣が付いたのではないかと想像します。
バックミンスター・フラーが提唱する「宇宙船地球号」とは、地球をひとつの宇宙船として捉え、その閉じた世界では、限りのある資源を循環させながら適切に使用しなくてはならないとしました。
この考え方、世界観は、あやさんのような環境保護に対して積極的な人ならずとも、今となっては誰の心にも響くのではないでしょうか。地球で起こることは、国境や人種に関係なく全ての生命に影響することを、私たちは現在嫌と言うほど思い知らされています。
「具体的に取り入れている循環型への方法はコンポストと雨水タンクです。以前はコンポスト=生ゴミ処理と思っていました。ちょっと臭くて汚いイメージがあったのですが、それは間違いで、土を作ることなんです。息子が通っていた保育園でコンポストを使用していて、そこで子どもたちが生ゴミをコンポストに混ぜて『ここは温かいね~』と喜んでいる姿に感動したのを覚えています。自然の持つ力が温かいことを身をもって経験したわけです」
そのコンポストに、先生はゴミの中にプラスチックが少々混ざっていても気にせず入れていたそう。
最後まで土に戻らないプラゴミを見て、子どもたちは永遠にゴミとして残ってしまうモノの存在を感覚として学んだことでしょう。学びが、体験でしか得られないことも、あやさんは知りました。

「保育園では雨水を溜める大きなタンクも設置していました。庭の水やり、水遊びはその水を使って行われ、どうしても水が流れてしまう場所には水分を多く必要とする植物を植えて、無駄のないように工夫していましたね。まだ、我が家でそれを徹底するのは難しいのですが、数年かけて試行錯誤しながらやって行けたらと考えています。季節によって陽の当たり方、雨の降り方、水の行方、植物の生え方は段々とわかってくると思うので。これは義務として捉えているのではなく、自然や生きものと仲良く暮らす楽しみであるんです」

そう、なにごとも楽しめなければ続けられないのは事実です。それがなければ持続可能が無理なことを私たちは知っています。だから、あやさんにとっての、楽しみながらサスティナブルのコツを聞いてみました。
「私はザックリとした性格なので緻密なことは苦手です(笑)。たとえ、その行動が良いことであるとわかっていても苦痛に感じれば続かない。無理をしないことですよね。出来ることを出来るときにやる。ルールなどは作らない。やってみてダメだと感じたら、気軽に違うやり方に変えればいい。コンポストも、こうでなければいけないという決まりはありません。だから取り敢えずやってみる。雨水タンクに溜めた水は、庭の水やりに使っていますが、もしものときはトイレや洗濯水としても使えます。それから、この土地に放置されていた竹などの木材をやっと整理し終えたので、少しずつ畑をつくり始めました。今は種蒔きのシーズンですから、それが楽しみになっています」

暮らしを楽しむことと、環境に良いことを繋ぐ。その考え方の根底には、無理せずに、自ら動いて学びながら進むことなのだと教えてもらいました。自分の手足を使い、自然と戯れながら何かを生みだす歓びは、実践してみなければ味わえないことです。
「サステイナブルな生活の豊かさを考えるとき、物質的なことも無視は出来ませんが、それよりも精神的な満足感を大事にすると感覚として嬉しいことに気づきました。いいなぁと思えることが増えたんです。例えば、たくさんの器を持つ満足感より、大好きな作家がつくったひとつの器を持つ歓びのほうが大きいと感じるんです。それを愛しいと感じるんですよね。そんなことを店を通して、お客様に伝えられたらと思うようになりました。」

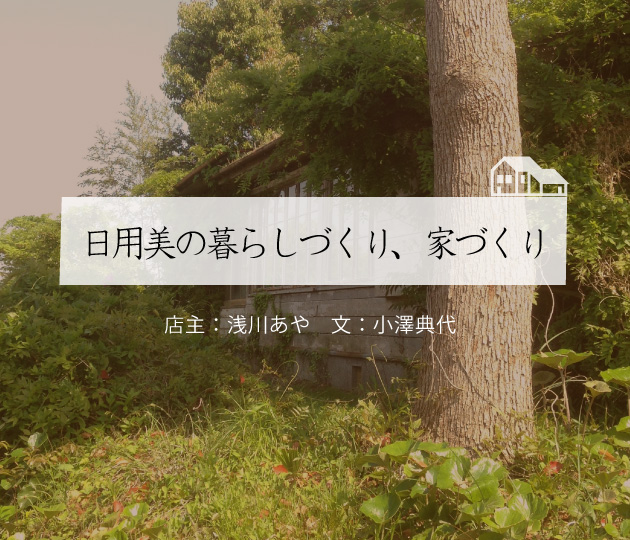
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.