akane
2021/03/19
akane
2021/03/19
※本記事は連載小説です。
第8章
DNA(4)金と琥珀
眉間に皺を寄せた母が、ソファの中央深くに座っていた。
その横で父が腕組みをして、ため息を吐き続けていた。
サーちゃんの家に、父と母と弟までがお邪魔していた。戸籍上の自分の家族たちだ。

「なんであんたが、一人であれやこれや調べていたの? それを、ここでは、さつきには相談してたって言うの?」
レースのハンカチを握って、母が甲高い、脳髄に響くような声を出す。
今日、これから皆で高山産婦人科医院を訪ねることになっている。向こうは多分、弁護士も一緒だ。
弁護士から、今回の事の顛末と二十二年前の説明をしたいという報告を受けた母が、慌てて、菜々子に電話をしてきた。電話口では一体、どういうことなのか、と混乱していた。
菜々子の方から、その話をしに湯河原に出向く勇気がなかった。
それでサーちゃんに頼んで、一緒に説明してもらうことにしたのだ。
母一人が先ほどからいきり立っていたが、今静かに弟が口を開いた。今日は父と同じように、わざわざ紺のブレザーを着ている。
「そんなことより、問題は違うだろ。姉貴の立場になってみろよ」
意外な台詞に、菜々子は弟を見つめる。両手を膝の上に重ね、先ほどから落ち着きなくさすっている。
彼が今、本当に気にしているのは、果たして姉の心情なのか? それとも家族に持ち込まれた厄介ごとが、自分にも降りかかる可能性なのか? またはこれから何が起きるかわからないという予測できない不安に対してなのか?
弟と自分が仲の良いきょうだいだった時期は、幼少期だけだ。どこへ遊びに行くにも後ろをついてくる弟は可愛かったのに、転んだり怪我をしたりするたびに菜々子が母に叱られるうちに、それが、喧嘩の種になっていった。
「今更訊きますけど、あなたは、あそこで不妊治療を受けていたんですよね?」
母親に対して、思わずそんな他人行儀な訊き方になると、
「姉貴も、姉貴だよ」
と、弟は首を横に振った。
そして、母が前のめりになって何かを話し出そうとするのを遮ったのは、父のふっくらした手だった。
「いい、私が話そう」
と、和服を着た母の膝をなだめるように触れた。
「うちはね、なかなか子どもができなかったんだ。菜々子は医者の卵なんだから、もうわかるね? 私の精子の運動率が低いとかいう言葉を、確かあの病院の医師は使っていたと思う」
父はスラックスのポケットから格子柄のハンカチを取り出すと、ずいぶん生え際の後退した額に急に浮かび上がった汗を拭った。
「世田谷に人工授精でずいぶん成功率の高いクリニックがあると、サーちゃんが教えてくれて、ああ、悪いね、サーちゃんのせいにするつもりはまったくないよ」
父はいつもより力の抜けたような笑みを浮かべてそう言って、続けた。
「高山という、自信に満ちた医師がやっているその病院を、お母さんと二人で訪ねた。どんな治療だったのかは、きっと今日説明があるんだろうし、はっきり言って私はお母さんに任せきりだった。人工授精なのは、間違いない。ただ、菜々子には悪かったが、人工授精であることは、周囲には話さずにおこうと二人で決めたんだ。だから、湯河原ではうちの親たちも知らないはずだ」
「恥じていたわけじゃないわ。ただ、十年以上も子どもを授からなかったのに、挑戦させてもらえた」
母が割って入った。
「治療のことは、もちろん、つぶさに覚えています。だから、今日は、あの医師に全てぶちまけさせますよ。何があったのかってね」
「ねえ、ミーちゃん、そんな口調じゃだめだよ。わかってるでしょ? だから菜々子だって」
と、サーちゃんは自分の姉を思わずミーちゃんと呼び、何かを言いかけて席を立った。
「もう一回、コーヒーを入れてくる」
「私、手伝おうか? サーちゃん」
「大丈夫、菜々子はちゃんと話を訊いておきなさい」

少しすると、キッチンからは聞き馴染んだ優しい音が聞こえてきた。コーヒーメーカーに豆やフィルターをセットして、水を注ぐ。じきに聞こえてくるのは、ガリゴリ、ガリゴリと豆を挽く音のはずだ。
いつだったかそれを、首をかくかくと動かしながら、「ガーリゴリガーリゴリ」と真似していたら、サーちゃんは腹を抱えてしばらく大笑いしてくれた。
だから今も、その音が響きだすと、萎んでいた心が少し膨らんだ。
「じゃあ、訊くね。。人工授精の中でも、どんな方法を取ったかを高山医師は言っていた? どういう治療だったか教えてくれる? 当時の一般的なことなら、私も少し調べてみたから」
菜々子が冷静に問いかけると、母も少し気持ちを鎮めたようだった。
「まず、排卵誘発剤というのを使ったわ。私は湯河原から通って、何度か卵子を採取してもらった。それに、精子を注入して、先生は最初に受精卵をたくさん作った。そこからが確か、他の病院と違っていたはず。一度できた受精卵を、凍結して保存するんだって言ってた。だから、何度でも、それを溶かして、胚移植できると言っていたのを覚えてる」
菜々子の思考が、しばらく止まった。何秒だったのか、何十秒だったのかわからないが、はじめにでたのは、
「待って」という言葉だった。
「凍結って、本当に言ってた?」
「うん、そう言ってたと思う」
やっぱりそうだったか、と菜々子は理解した。
「日本ではまだ認可されていない頃から、あの病院では受精卵の凍結保存による人工授精が、行われていたらしくてね」
それがどうあれ自分という生命体の始まりのはずなのに、菜々子はまるで客観的にそう口にしていた。
「病院は、それを隠しているだろうから、今回のこともちゃんと明らかにしないかもしれない」
「だけど、何かを間違えたわけなんだろう」
父が拳を握りしめてそう言うと、母は目を赤くして、首を大きく横に逸らした。
「どうして? どうして今ごろ、そんな話になるの?」
父が母の背中に手をやる。
「大体なぜ菜々子は、そんなに知りたかったの? 私たちの子どもであるのが、そんなに嫌だったの?」
それにはもう誰も声を発しなかった。呆れていたのもあるが、菜々子は厳密に言うと、返事ができなかった。むしろ、母が今頃そんな風に自分に問いかける方が不思議だった。
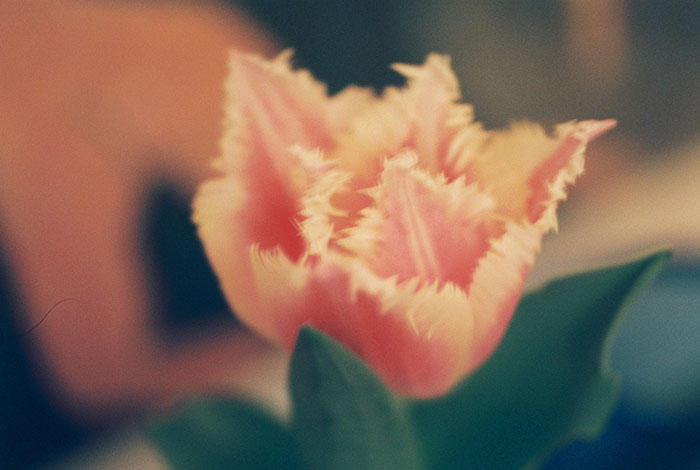
「ねえ、ここで訊くのは悪いかもしれないけど、俺もその人工授精とやらで生まれたわけ?」
弟が訊ねると、母は駄々っ子みたいに首を横に振った。
「違うわよ。あんたは自然に生まれてきてくれた子なの。期待もしていなかった時に、授かったの」
「よかったぁ」と、小声で呟く弟に、苦笑してしまう。
サーちゃんが、大きなトレイでコーヒーをまず四脚運んできた。
菜々子も立ち上がって、手伝った。
素晴らしい香りがした。金の縁取りのよそ行きのカップに、琥珀色のコーヒーが湯気を立てて揺れていた。
母をはじめ家族それぞれの動揺は、菜々子にだって理解ができた。自分自身はもうすでに経験済みの時間だ。
ただ、今は、たった一人で受け止めていた時とは違う寂しさがあった。
遊園地のコーヒーカップの乗り物のあの心地悪さが不意に思い出された。
くるくる、くるくる、それぞれが回るうちに、遠くへ放り出されるような気持ちになる。菜々子にはちょっと苦手な、爽快感に欠ける乗り物だ。まるで、あれと同じように、今は皆が胸に渦巻く混乱を抱えている。けれど、振り落とされるのは、菜々子だけなのだ。
「菜々子、お父さんはお前に、これからどんな話になるのかはわからないけれど、一つだけはどうしても言っておきたい」
コーヒーを含み、父は言った。
「みずきだって、サーちゃんだって覚えているはずだよ。菜々子を授かったとわかったとき、そして無事に生まれてきてくれたとき、私たちがどれだけ喜んだか。菜々子が成長していくとき、どの瞬間だって、そう思ったよ。菜々子が思春期になると、お母さんとは、だいぶやり合った。それは、放っておいたお父さんも悪かったかもしれない。でも、親子なんだから、他愛のないことだと思ったさ。お母さんは、あの旅館でたくさん大変な役目を引き受けてしまったから、菜々子には甘えていたかったんだと思う」
今更そんな話は、ずるいと思う。
「私はずっと、愛されていないんだと思ってたよ」
菜々子は小首を傾げ、少しおどけるようにそう口にした。その瞬間、危うく涙が溢れそうになり、顔を天井に向けた。いつもそうやって泣くのを我慢してきた。でも少し涙が溢れてしまい、髪の毛をつたい、デニムの腿のあたりがポツポツと濡れた。
医師や弁護士に会うからって、菜々子は正装などするつもりはなかった。ただ、真実を知りに行くだけなのだから。

「電話だ。向こうの準備ができたようだ。タクシーを呼ぼう」
父が、携帯電話の画面に着信を確認する。
「コーヒー、最後までいただいてから行きましょうよ。今、大事な話をしていたんだから」
母がそう言って、菜々子の方を見た。不思議だが今は、その涼しげな目に抱きしめられているように感じた。
毎週金曜日更新
PHOTOS:秋

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.