ryomiyagi
2021/04/23
ryomiyagi
2021/04/23
※本記事は連載小説です。
第10章
ポゴシポ(1)川
ジヒョンのマンションは川崎の川沿いにある。ベランダの窓から、彼女はよく川べりで遊ぶ人たちを眺めているそうだ。
道路に面したエントランスの前にオートバイが停まる。もう何度、こうして二人乗りでやってきたかしれないのに、いつもと違って謙太は、フルフェイスのシールドだけを指であげて、
「じゃあ」
と言った。
誘わなくてもいつもなら自分もついてくる。または、頼まなくても自分から買い出しを申し出て、両手にレジ袋を提げて急いでジヒョンの部屋の呼び鈴を押す。
子犬のような謙太。
子供っぽくて、時折いじめたくなり、それでも拗ねずに付き合ってくれるから長続きしていたような気がする。でも、今の謙太はだんだん引き潮のようだ。

「一緒に、寄っていかない?」
そう誘ってみた。少し間があったが、
「いや、大事な話だろうから」
と、こちらを見つめた。
「わかった」
それなら先にシールドを下げて走り出してくれたらいいのに、その場にじっといる謙太とは、まるでこれきりになるような気がした。
いや、だったらそれで構わないではないかと菜々子は自分に言い聞かせた。誰と付き合う時にも、恋愛はいつか終わるのだから。それが早いか遅いだけの違いだと思うから、がむしゃらにもならずにきた。その終わりが、自分からとは限らないのだと教えてくれるのが、謙太になるのかもしれない。
「じゃあ、行くね」と、菜々子が言いかけたとき、またスマホが鳴った。バッグから取り出し、ジヒョンからかと思って画面を覗くと、
〈おとうと〉と、表示されている。
〈父〉〈母〉〈おとうと〉。
湯河原の家族の表示は皆、そうなっている。
これまで誰からも、ほとんど電話など鳴らなかったのに、
「はい、何?」
菜々子は少し離れたところへ行って、後で掛け直すと言って、一旦通話を切った。謙太にきちんと挨拶がしたかった。
「送ってくれて、ありがとう」
「誰? どうしたの」
謙太が、よく慣れた声でそう訊いてきた。
「どうして?」
「だって今、菜々子、すごく困った顔をしてたよ」
「まだ、心配してくれるんだ」
苦笑まじりに呟いていた。
謙太はこちらをまっすぐに見つめた。
「誰だったの? 今度は誰が、菜々子を困らせてるんだよ」
「おとうと、だよ」
「あいつが、どうしたの?」
病院で面会した日の夜に、弟から長いメールが届いた。
〈驚くかもしれないけど、俺は姉貴が好きだ。自分はおかしいのかと思ってきたけど、今はもうこう言っていいはずだから。
姉貴は俺のことなんて眼中にないのかもしれないけど、これからはちゃんと意識してほしい。少し考えてみてください。
近々電話します〉
姉と弟として育ったはずなのに。オムツだって替えてやったし、一緒に手を繋いで遊んだ。小さい頃はすぐ泣く弟をなだめるのも自分の役だった。
思春期に入ると、同じ屋根の下にいるのが息苦しくなった。菜々子にはもう性体験もあったし、家庭に持ち込んではいけない雰囲気をまとっているのかとも感じた。
「あいつね、血の繋がりがないのがわかって、ちょっと混乱しているみたい」
謙太が天を仰ぐ。
「俺が会いに行って、話そうか。ふざけんなって言ってやるよ。今から行くから、そう伝えて」
必死にそう話す謙太の体温が上がっていくようで、久しぶりにその背中や胸の温もりが愛おしくなった。
「仕方ないよ」
けれど菜々子がそう苦笑いをすると、
「ごめん、俺、また余計なことばかり言って」
「ごめんは、こっちだよ。ざらざらする気持ちになることばかりが続いていて、謙太にまで曇り空を運んでる」
謙太は黙ってしまう。
「弟のことは気にしないで。あいつ、ばかだもん」
俯く謙太が唇を噛み締めている。
「じゃあ、ジヒョンを待たせているから、行くね」
菜々子は頭の上で手を振った。

ジヒョンは、謙太が一緒ではないことを不思議がらなかった。
「ここまで送ってもらってきたんだ」
いつもなら「なぜ謙太来ないの?」と、訊いてきそうだったから、逆に訊いてみた。
「そのまま帰るなんて、らしくないよね?」
ジヒョンは首を振る。
ベージュの上下の部屋着姿で、髪の毛を一つにまとめたジヒョンは、たった今まで、レポートを書いていたようだ。ダイニングテーブルにノートパソコンと資料が広がっていたのをまとめると、日本の緑茶を淹れてくれた。
「謙太の話はまた後でする。この間、相談されたから。それより、わかったことを伝える。日本で不妊治療を受けていた、ソン家の人たちのこと、多分間違いじゃない」
菜々子は席に座った。
「同じ頃、同じ世田谷にいたソン家の住所はうちからとても近かった。ソンという苗字はよくあるから。それで時々、郵便が間違って届いた。お互いの家で歩いて郵便物を届け合ううちに、家族同士が顔見知りになった。その家にも、可愛い女の子がいたって母はおっしゃっていた」
そこから始まる話に、菜々子は惹きつけられていった。
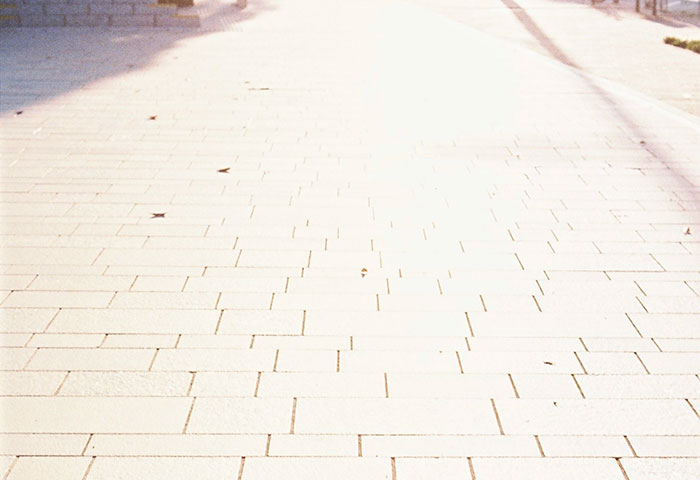
「お父さんは、会社を経営されていた。お母さんは、元水泳の選手だった。手と足が長い綺麗な人だった。でもお父さんの会社、うまくいかなくなった。日本で騙されたと言っていたらしい。それで韓国に帰るという連絡は、もらっていた。私のお母さんが、すぐにその住所、訪ねてくださった。もうそこにはいなかったけど、近所の人が引越し先を教えてくれた。そこにはまだいるようだった」
菜々子は、その話に登場する本当の父と母を想像していた。人を騙した人ではなく、騙された人なんだ。帰国をきちんと伝えに来た人たちなんだ。お母さんは、水泳の選手だったんだ。そう思うと、体に力が湧いてくる気がした。
「でもね、菜々子、今の本当のお父さんとお母さんは、裕福ではないようなんだよ。それでも、構わないか、うちのお母さんは少し心配されている」
「ジヒョン、私、韓国へ行ってくる」
うなずくジヒョンより、彼女の前のお茶の表面を見ていた。
「まず、自分だけで行ってくる。家族とではなく、一人で行こうと思うよ」
「一人で、会いたいんだね」
そう言うと、ジヒョンの目からテーブルに涙がこぼれ落ちた。
「なんで、あんたが泣くの?」
「ポゴシポ、会いたい気持ちがわかるから」
ジヒョンは、涙も拭わず続けた。
「でもね、謙太には、会いたい気持ちがわからないって。菜々子のどんな話も、受け止められていないって。だから、悩んでる。多分、今一緒にいても、菜々子はいつも物足りないんじゃないかって」
「そう言われても困るよ」
「だから、謙太に言ったよ。少し待ってあげてって。それでよかったよね?」

窓から川べりを見下ろす。謙太のオートバイが停まっているかもしれないと思った。だけどそこには、暗い川を照らす、等間隔の街灯だけが光って見えた。
毎週金曜日更新
PHOTOS:秋

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.