2020/10/06
馬場紀衣 文筆家・ライター
『死を招くファッション: 服飾とテクノロジーの危険な関係』化学同人
Alison Matthews David/著、安部恵子/訳

ファッションについて書かれた書籍の中で『死を招くファッション』ほど魅力を放つものはそうないだろう。そう言いきれてしまうほど、服飾の死の歴史を記したこの本は、読者の胸を締めつける。そして読後には、ファッションをまったく違った目で見ることになってしまうのだ。
あたかも自分が魅力的な人物になったかのように演出してくれるファッションは、今も昔も多くの人々の関心事だ。そして人が衣服なしには生きていけないというのは、事実だろう。ファッションについて考えるとき、それに包まれる自分の身体について考えないわけにはいかない。「ファッションは皮膚の延長」とか「衣服は第二の皮膚」と言われることがあるように、ファッションとは衣服と身体によって作り出されるものだ。「私」の身体の一部である衣服とは、身体を覆っている単なる容れ物ではないのだから。
本書をめくると、半身が骸骨でもう一方の半身はお洒落な服を身につけた男女人形の写真が載っている。1805年~10年頃のもので、蝋と布で作られている。見る者にファッションと人間の命どちらも脆くてはかないことを再認識させるものだ。
19世紀初頭、それはファッショナブルな衣類が人間の自然な身体のシルエットを機械的なものへと変貌させた時代でもある。優雅な生活を誇る人々は、健康よりも身なりを大切にしていた。女性は張り骨入りのコルセットで体をきつくひもで締め、大きく広がったスカートを身に付けた。足もとはよろめくほどのヒールの高い靴。男性は、汗だくになって重いフエルト帽をかぶり、固く糊のきいた襟の服を着て、こちらも窮屈な靴を履いていた。そうしてファッションの犠牲になった人の数は、ほとんど男女等しいと考えられている。裕福な人々が流行に注いだ欲望が、彼らの命を奪うことになったのだ。
1800年代初期から1905年頃まで流行していた裾を引きずるスカートは、女性が町を裾で「掃いて歩く」せいで出歩くたびに病気を家に持ちこむことになった。当時の都市は、犬や馬の排泄物やその他の汚物で街路が非常に不衛生だったことが関係している。
1850年代以前には、靴は右足と左足の区別のないまっすぐなものが標準だった。これは靴職人を樂にさせたが、履く人の足を変形させた。女性達は鉛の含まれたフェイスパウダーで化粧をした。それは肌を白くしたが、顔以外にも影響を及ぼすことになる。色鮮やかなドレスは、ヒ素などの毒物を用いて着色されていた。それだけではない。男性の礼装品の帽子には水銀が含まれていた。フエルト帽に使う動物の毛を加工する際に水銀が使われていたのだ。だから衣類を作る労働者たちも水銀中毒となり、多くの犠牲がでた。著者は「衣服を作る労働者と衣類の消費者は等しく「奴隷」であり、「犠牲者」であり、半ば神聖な「殉教者」とさえみなされる」と語っている。
本書は主にフランスやイギリス、北米の19世紀と20世紀前半を舞台としているが、これはけっして過去の話ではない。ボタン一つで衣類が清潔になる一方で、清潔へのこだわりが新たな汚染問題を生み出していることは、それほど認識されていない。子ども用の衣服についているひもやボタンが遊具に絡まって死亡事故が起きたのもつい最近の話だ。それでもファッションは不安をかきたてるだけのものではないと著者は信じている。
ファッションには、強力なパワーがある。身に付ける人に健康と喜びを与えてくれることを私たちは知っている。ファッションの犠牲者と加害者にならないためにも、まずは自分のクローゼットを見直してみたい。
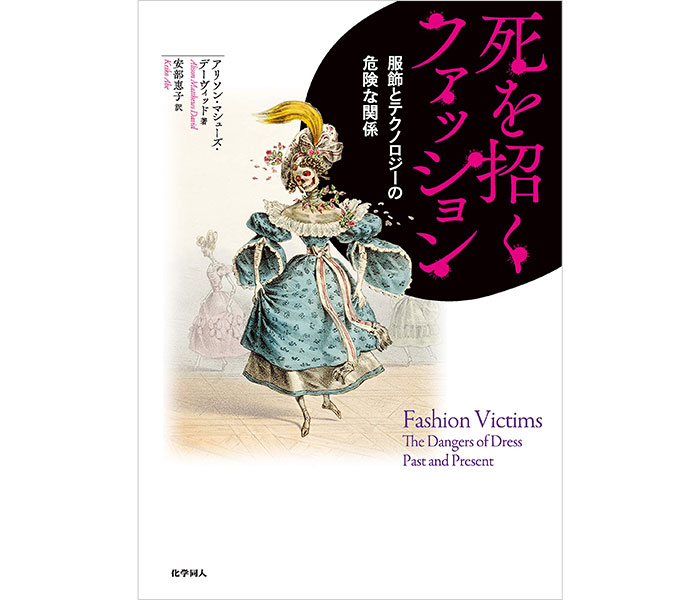
『死を招くファッション: 服飾とテクノロジーの危険な関係』化学同人
Alison Matthews David/著、安部恵子/訳

