2021/08/09
長江貴士 元書店員
「数学ガール ゲーデルの不完全性定理」SBクリエイティブ
結城浩/著

さて今回は、ゲーデルという数学者が数学界に絶望と衝撃を与えた「不完全性定理」について書くつもりだが、そのためにはまず、「現代数学の父」と呼ばれる、20世紀の数学を方向づけたと言われるヒルベルトという数学者について触れる必要がある。
ヒルベルトの成したことで有名なものを二つ挙げるとすれば、「ヒルベルトの23の問題」と「ヒルベルト・プログラム」だろう。
「ヒルベルトの23の問題」というのは、1900年のパリ国際数学者会議でヒルベルトが発表した23の問題のことである。23の問題は、その当時未解決だったものであり、これらを提示することで彼は、現代数学を方向づけたのだ。実際、世界中の数学者がこれら23の問題に取り組むことで、新たな数学の地平が広がり、多くの発見が得られた。ヒルベルトが「指導的数学者」と呼ばれるのは、このように数学界という大きなものを動かすだけの実力と名声を兼ね備えた、真に力のある数学者だったからだ。
そしてもう一つの「ヒルベルト・プログラム」が、「ゲーデルの不完全性定理」と関わってくるものだ。
さてここから、「ヒルベルト・プログラム」と「ゲーデルの不完全性定理」について書いていく。まず「ヒルベルト・プログラム」についてだが、これには三つの手順がある。
一つ目は「形式的体系の導入」だ。これは、数学を形式的体系で表現する、という意味なのだが、よく分からないだろう。
例えば僕たちは、「1+1=2」という数式は普通に理解できる。これを僕らは、「1個のものと1個のものを足し合わせると2個になる」というように、記号に何らかの意味を持たせて読むが、ヒルベルトは、数式に意味などなくていい、と言う。そこに形式的体系さえあれば、数学は十分だ、と。
例えば、こういう<数式>(数式に見えないだろうからカッコに入れてみた)を考えてみる。
「蟻△ド☆Q」
こんな<数式>は、僕らには意味不明なのだが、それは、「蟻」「△」「ド」「☆」「Q」というそれぞれの記号の定義を知らないからだ。先程の「1+1=2」の場合、正確に表現できるかどうかはともかく、僕らは「1」「+」「=」「2」という記号の定義をちゃんと知っているから意味が分かる。同じく、「蟻」「△」「ド」「☆」「Q」も、ちゃんとそれぞれ定義して使えば、ちゃんと<数式>として認めることが出来る。こんな風に、あらゆるものを「定義された記号」に落とし込んで数式(正確には「論理式」)を作っていくことを、ヒルベルトは形式的体系と呼んだ。
ここから一気に省略するが、彼は「数学」というものを、
記号に変換して推論規則によってあれこれいじくり回せるもの
と考えた、ぐらいの認識で良いと思う。
さてヒルベルトは数学をそんな風に捉えた上で、「無矛盾性の証明」と「完全性の証明」に挑もうとする。
「無矛盾性」というのは、
「Aである」と「Aではない」の両方が証明されることはない
というものだ。例えば「1+1=2」の例で言えば、
「1+1=2」と「1+1≠2」の両方が証明されることはない
ということだ。まあ、当たり前に思えるかもしれないが、ヒルベルトの時代には、集合論の分野で、いわゆるパラドックスと呼ばれる様々な矛盾が発見されていたのだ。有名なのは「ラッセルのパラドックス」で、これは「図書館の蔵書目録」を例に挙げた分かりやすい説明がよく成されるので、ネットで検索してみてほしい。ヒルベルトは、数学という完璧な体系から矛盾を排除したいと考え、形式的体系には無矛盾性が成り立つことを証明したいと考えたのだ。
もう一つの「完全性」というのは、
「Aである」と「Aではない」のどちらか一方は証明出来る
というものだ。つまりヒルベルトは、「どんな数学の問題も真偽が判定できるはずだ」ということを証明しようとしたのだ。
ここで「ヒルベルト・プログラム」についてまとめよう。彼はまず、数学というのは、定義された記号をこねくり回すことが可能な形式的体系であり、さらにその体系は、「矛盾なく」「どんな問題も真偽が判定できる」ものであると証明しようとした。これが、大数学者ヒルベルトがぶち上げた、過去何千年と積み上げられてきた数学の叡智を体系的にまとめようとする壮大な試みだったのだ。
しかし、そんなヒルベルトの野望を打ち砕いたのが、弱冠25歳の若き数学者・ゲーデルだった。
ゲーデルがどんなことを主張したのか。その正確な記述はここでは避けるが、大雑把に言えば彼はこんな主張をした。
ある条件を満たす形式的体系については、「完全性」も「自己の無矛盾性」も形式的には証明できない
つまりゲーデルは、ヒルベルトのやろうとしたことを完膚なきまでに打ち砕いたのだ。
さて、「ゲーデルの不完全性定理」は時に、「数学って不完全な学問なのだ」という主張で引用されることがある。しかしその理解は間違っている。ゲーデルが主張しているのは、「ある条件を満たす形式的体系」についてであり、「数学そのもの」ではない。それに、ゲーデルが「証明できない」としているのは「“自己の”無矛盾性」である。形式的体系というのは様々に定義することが出来、例えば「Aという形式的体系」の無矛盾性を「Aという形式的体系」で証明することは出来ないが、「Aという形式的体系」の無矛盾性を「Bという形式的体系」で証明できる可能性はあるのだ。「不完全性定理」という言葉には惑わされやすいが、ゲーデルの主張は、決して数学に不備があるというようなものではない。
とはいえ、ゲーデルの主張は、ヒルベルトがやろうとしたことに大打撃を与えたことは間違いないし、また数学界に大きな衝撃を与えることにもなった。その衝撃の一つは、「ある条件を満たす形式的体系には、真偽が判定できない問題が存在する」と証明されてしまったことだ。数学者は常に何らかの問題に取り組んでいるが、彼らはずっと、「その問題が正しいか間違っているか、いずれ分かる」と思えるからこそ膨大な時間を注げるのだ。しかしゲーデルは、「いくら時間を掛けてもその形式的体系内では真偽を判定できない問題が存在する」ということを証明してしまったので、数学者たちは戦々恐々とすることになったのだ。今取り組んでいるこの問題が、実は真偽の判定できない問題だとしたら…。自分が注ぎ込んできた時間すべてが無駄になってしまうのだから。
さてゲーデルは、一体どんな風にしてそんな証明を成し遂げたのか。これは超絶難しくて、本書を読んでもほぼ理解できなかったが、「ゲーデル数」という発想には感動した。それさえ、簡単には説明できないので本書を読んでほしいが、「ゲーデル数」というものを定義することで、すべての論理式にある数字を割り振ってしまい、それを駆使することで、その形式的体系内に「決定不能な文」を作り出す手順をゲーデルは導き出したのだ。…と書いていても自分でも何を言っているのかちゃんとは理解できていないが、まあ、とにかく凄いんだよ(と書くしかない 笑)。
ちなみに、高橋昌一郎『理性の限界』もオススメだ。こちらは、「アロウの不可能性定理」「ゲーデルの不完全性定理」「ハイゼンベルグの不確定性原理」の三つが扱われているが、文系の人であっても目からウロコというぐらい分かりやすく、これらの難しい理論が描かれている。是非読んでみてほしい。
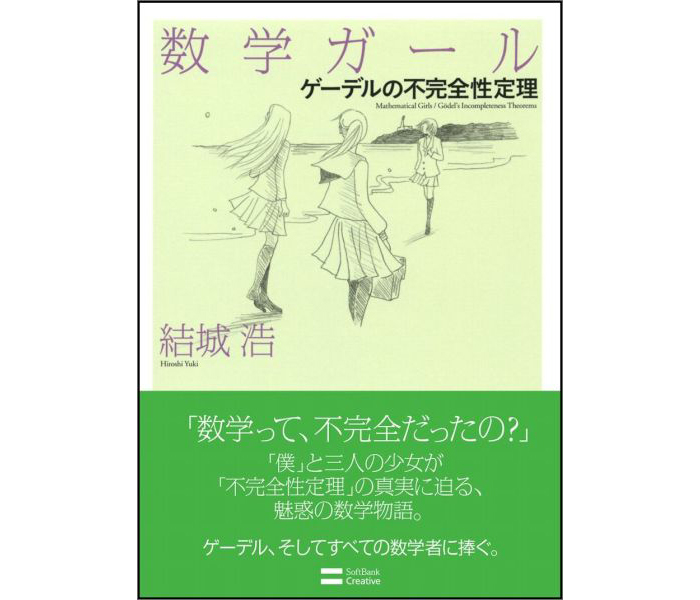
「数学ガール ゲーデルの不完全性定理」SBクリエイティブ
結城浩/著

