ryomiyagi
2020/07/01
ryomiyagi
2020/07/01
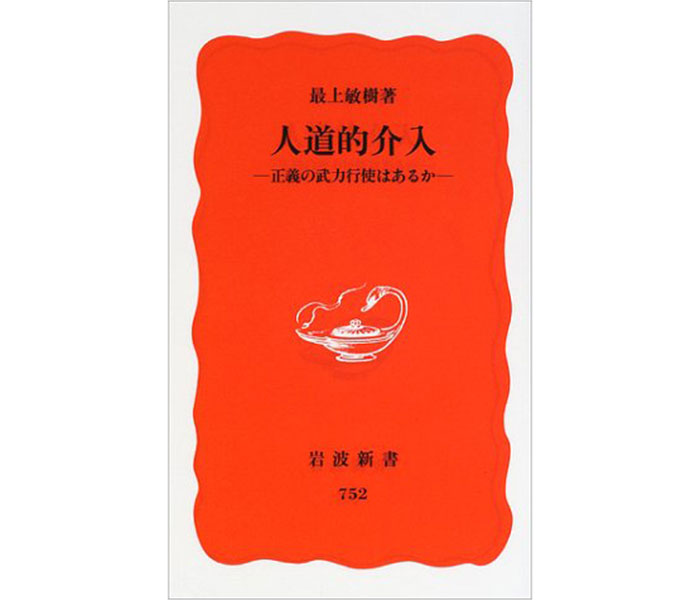
最上敏樹『人道的介入』(岩波新書)2001年
連載第44回で紹介した『戦争調査会』に続けて読んでいただきたいのが、『人道的介入――正義の武力行使はあるか』である。本書をご覧になれば、どのような事態で「人道的介入」が必要とされるのか、介入されるケースとされないケースの相違は何か、今後の「人道的介入」はどうあるべきか、明らかになってくるだろう。
著者の最上敏樹氏は、1950年生まれ。東京大学法学部卒業後、同大学大学院政治学研究科博士課程修了。法学博士。国際基督教大学教授を経て、現在は早稲田大学教授。専門は国際法・国際機構論。とくに国連や国際機構が世界平和に果たす役割に関する実証研究で知られ、『国際機構論』(東京大学出版会)や『国際立憲主義の時代』(岩波書店)などの著書がある。
さて、1994年にアフリカのルワンダで「大虐殺」が生じた。ルワンダは、もともと人口の85%を占めるフツ族と、14%を占めるツチ族で構成される国である。ベルギーが植民統治していた時代にはツチ族が優遇されていたが、1962年に独立して以来、多数派のフツ族が軍政を握り、少数派を迫害する「民族浄化」理念に基づくメディア戦略とヘイト・スピーチによって、ツチ族に対する国民の憎悪感情を煽り立てた。
1994年4月6日、両族の緊張が高まった時点で、フツ族出身の大統領の乗った飛行機がツチ族によって撃墜され、結果的にルワンダ大統領は暗殺された。これに激怒したフツ族の軍人と市民が激怒し、ツチ族の人間を捉えて、リンチを始めた。
極度に興奮したリンチはエスカレートして留まるところを知らず、結果的に、隣国ウガンダで結成されたツチ族反政府勢力がルワンダを制圧するまでの100日間に、ツチ族の50万人以上が虐殺された。その残虐さは、筆舌に尽くし難いものだった。
ツチ族の市民は、手足を切断され、顔や身体中をナタで切り刻まれた。あまりの苦痛に、犠牲者は兵士に金を渡して、銃で一思いに殺すように頼んだという。殺害者数を数えるために、男性は性器が切り落とされ、女性は強姦されて乳房が切り落とされ、それらが部位ごとに整理して積み上げられたという証言もある。母親は、助かりたければ、自分の幼児を殺すように命じられ、新生児は汚物層に捨てられた。
常軌を逸した大虐殺が始まった初期段階で、「国際赤十字」や「国境なき医師団」は、国連に「武力介入」して虐殺を止めるように訴えた。しかし、国連は「内政不干渉」の原則を押し通して、軍事的介入を拒否した。国連に代表される国際社会は、結果的に「手をこまねいてこの事態を傍観していた」のである。
本書の定義によれば、次の(1)から(5)を満たすのが「狭義」、(1)から(7)を満たすのが「広義」の「人道的介入」である。しかし、本書に登場する過去の事例を比較すると、国際情勢に応じて、実施されたりされなかったりする矛盾が浮かび上がる。
(1) はなはだしい人権侵害(「最高度人道緊急事態」)が存在すること
(2) 武力行使は最後の手段であること(それ以外の平和的手段が尽きていること)
(3) 介入の目的は、はなはだしい人権侵害の停止に限られること(それ以外の国益の実現などの目的を含まないこと)
(4) 取られる手段は、状況の深刻さの度合いに比例していること(実施期間も必要最低限に限られること)
(5) 取られた措置(とくに武力行使)の結果として、相応の人道的成果を期待できること(多くの人々が迫害から逃れられ、生命が救われること)
(6) 国連安保理の承認を得ること(あるいは、少なくとも今後取るべき介入措置を安保理に通告すること)
(7) 介入は、国連、地域的国際機構、個別の国々の決定の順に優先されること
迫害され危難にさらされている人々は何としても救わなければならない。しかし、一国あるいは少数国の独断による武力行使が、その目的のための最善かつ第一の手段であるかどうかは、また別の問題である、とりわけ、その種の武力行使は、恣意的な懲罰あるいは感情的な報復に陥る可能性が小さくない。そういう「害」に十分注意すべき所以である。(P.212)
今でも世界各地で生じている「虐殺」や「虐待」にどのように立ち向かえばよいのか、今後の「世界平和」の意味を考えるためにも、『人道的介入』は必読である!
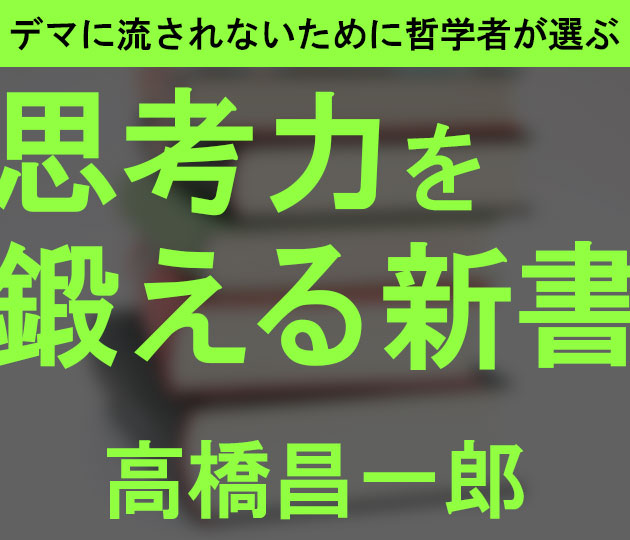
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.