ryomiyagi
2020/01/01
ryomiyagi
2020/01/01
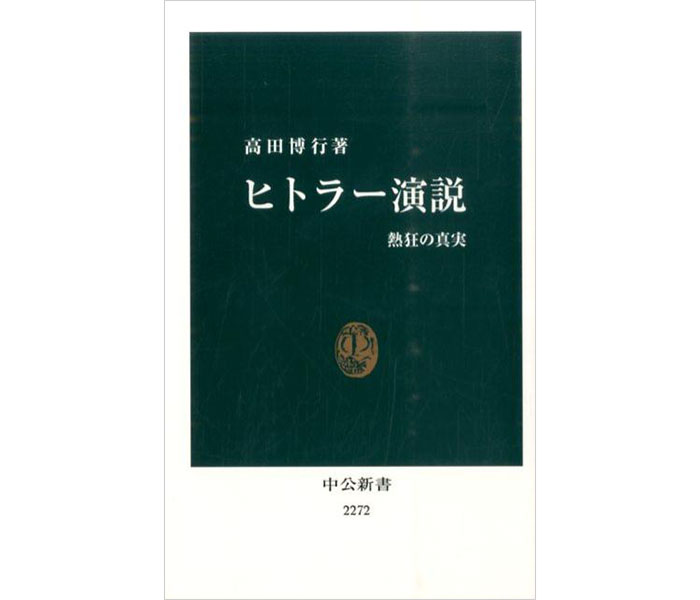
高田博行『ヒトラー演説』(中公新書)2014年
連載第32回で紹介した『ヒトラーに抵抗した人々』に続けて読んでいただきたいのが、『ヒトラー演説――熱狂の真実』である。本書をご覧になれば、ヒトラーの演説はどのようなものだったのか、どこに人々を熱狂させる要因があったのか、なぜその効力が失われていったのか、明らかになってくるだろう。
著者の高田博行氏は、1955年生まれ。大阪外国語大学卒業後、同大学大学院修士課程修了。関西大学教授を経て、現在は学習院大学教授。専門はドイツ語学・歴史社会言語学。とくにナチズムに関する社会言語学的分析で知られ、『歴史社会言語学入門』(大修館)や『グリム兄弟言語論集』(ひつじ書房)などの共編著書がある。
さて、1920年4月27日、30歳になったばかりのアドルフ・ヒトラーは、ミュンヘンのビアホール「ホーフブロイハウス」で1200人の聴衆を前にして、経済破綻した共和制ドイツを立て直すためには「天才的な独裁者が必要である」と叫んだ。
高田氏によれば、ヒトラーの「芝居がかった自己演出」が受け入れられたのは、ナチスが基盤にしたのがミュンヘンだったからである。北ドイツのベルリンと違って、南ドイツの市民は、大げさなことを好む気質だという。ビアホールの聴衆は、仕事帰りのサラリーマンや販売店員であり、その4分の1は女性だった。彼らは、政治集会というよりは、「おもしろい見世物」を楽しむ感覚でビアホールに立ち寄った。
当時の集会に参加した作家カール・ツックマイヤーは、ヒトラーは「激情に身を任せ踊り狂い、うなるように叫ぶ人間であった。しかし、彼は、葉巻の霞とソーセージのなかで無感覚にぼんやりと集まっている大衆を興奮させ、感激させる術を心得ていた」と述べている。それは、弱い個人を共同体感覚で豹変させる「術」だった。
1920年の1年間だけで、ヒトラーは50回近くも公開集会で演説している。8月13日のビアホールの集会では、2000人の一般大衆を前にして、「なぜわれわれは反ユダヤ主義なのか」を演説した。彼の話は2時間の間に58回も歓声で遮られた。
高田氏の詳細な分析によると、この演説約11,000語中の語彙の頻度は、「ユダヤ人」78回・「民族・国民」63回・「労働」54回・「人種」43回である。仮定を示す接続詞「もし~ならば」は85回、焦点を絞る副詞「~だけ」は68回、対比を表す接続詞「しかし」は48回も登場する。この分析を眺めるだけでも、ヒトラーが自分の主張を仮定し、敵対する主張と対比させながら、うまく結論を誘導していく論法が目に浮かぶ。
1925年12月12日、ディンゴルフィングで行われたナチス集会でのヒトラーの演説は、目前のクリスマスの話から始まる。キリストが生まれた当時の「ユダヤ人気質によって病んだ唯物主義的世界」は、「もっとも憐れむべき状況下で生を受けた人物」によって救われた。そして「キリストはアーリアの血をもっていたのだ」と続く。ヒトラーは、自分こそが「新世界の救世主」だと聴衆に認識させたのである。
開発されたばかりのラウドスピーカーのおかげで、彼の声は巨大な演説会場の最後尾まで届くようになった。宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスの1932年4月4日の日記には、「総統は、本日ザクセンで25万人を前に演説。ベルリンの遊歩公園では15万人が行進し、私と総統が演説。熱狂のるつぼと化す。時速100キロでポツダムへ移動、総統が5万人を前に演説。夜はベルリンのスポーツ宮殿で総統が1.8万人を前に演説。割れんばかりの喝采」とある。ラジオで聴いた国民も、同時に熱狂した。
1933年1月30日、ヒトラーはドイツ首相に就任した。ところが、ラジオから流れてきた彼の施政演説は、抑揚のない原稿の棒読みに過ぎなかった。聴衆との一体感も臨場感もないスタジオ録音は、人々の熱狂を一気に消滅させたのである!
国民を鼓舞できないヒトラー演説、国民が異議を挟むヒトラー演説、そしてヒトラー自身がやる気をなくしたヒトラー演説。このようなヒトラー演説の真実が、われわれの持っているヒトラー演説と矛盾するとすれば、それはヒトラーをカリスマとして描くナチスドイツのプロパガンダに、八〇年以上も経った今なおわれわれが惑わされている証であろう。(P.262)
戦局が不利になるにつれて、現実から目を背け、ラジオ演説さえ避けるようになったヒトラーの最後を知るためにも、『ヒトラー演説』は必読である!
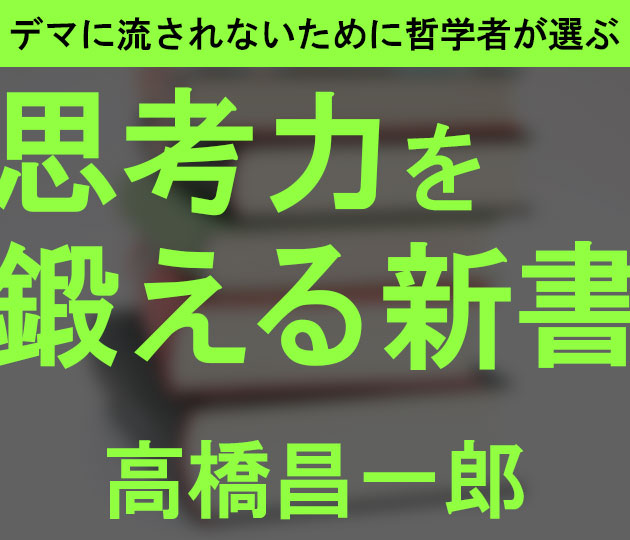
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.