ryomiyagi
2019/12/24
ryomiyagi
2019/12/24
※本稿は、森村泰昌『自画像のゆくえ』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

“自分を描く”という自画像のスタイルを日本が受容したのは、公式には明治以降のことだった。しかし明治以前の日本美術史上に自画像がなかったわけではない。
以下、日本美術史に登場した自画像の作例を三点とりあげてみる。
最初は雪舟である。あまりにも有名な室町時代の水墨画家である。この画聖に自画像がある(図9・1)。
斜め45度にかまえたバストショットで、背景になにも配さず人物(雪舟自身)だけを描いている。まるで西洋の肖像画スタイルを知っていたかのような作風である。
雪舟71歳の自画像である。制作年は1491年。レオナルド・ダ・ヴィンチの(とされている)、有名な自画像(下図)よりも、さらにはやい時期に描かれている。

私たちのよく知る雪舟の水墨画とはまったくことなる画風で描かれている点にもおどろかされる。通称《破墨山水図》の抽象画と見まがう絵画世界とは対照的に、この自画像はみごとに写実的である。頭にのせたかぶりものがすけて、なかに頭の形が見えるところまで、ちゃんと描いてある。
このかぶりものは、雪舟が中国で入手した特別な品なんだそうである。当時の中国への渡航経験者は、いまでいえば、地球の外にでた宇宙飛行士にも匹敵する別格の存在であった。かぶりものはその証であり、雪舟は少々自慢げにこれをアピールしている。
二番目は岩佐又兵衛の自画像である(図9・2)。

又兵衛は、戦国時代から江戸時代へとうつりかわる、おおきな歴史の変化のなかに生きた絵師だった。
父、荒木村重は織田信長に謀反をくわだてるが、不首尾におわり城から逃走。のこされた家族は信長に惨殺された。しかし又兵衛は奇跡的に救われ、母方の「岩佐」を名乗り、やがて絵師の道にすすむ。ちなみに父の村重は晩年、「利休十哲」にも数えられる茶人となった。
又兵衛がつかえた福井藩主、松平忠直は、菊池寛の小説『忠直卿行状記』にも登場する“御乱心”の殿様だった。しかしそのいっぽうで芸術に造詣がふかく、又兵衛の名作の数々も、この藩主のもとでつくられた。
そんな岩佐又兵衛の自画像を見てみると、世をすねたような、すべては風まかせとでもいいたげな、ひょうひょうたる雰囲気をただよわせ、あじわいぶかい。
代表作の絵巻《山中常磐物語》には、血みどろの殺戮シーンが描かれている。信長に母を殺された子としての又兵衛の怨念がこめられているかのようである。自画像ではそしらぬふりをよそおっていても、心のうちには煮えたぎる怒りや悲しみが秘められていたのかもしれない。
しかしこの絵師には、またべつの顔もある。又兵衛の《洛中洛外図屏風》には、四条河原の人形浄瑠璃の小屋が描かれ、「山中常磐あやつり」と書かれた短冊がそえられている(インターネットでそのように指摘したひとがいた)。
浄瑠璃語りにもなっているくらいだから、又兵衛の《山中常磐物語》も、かつての戦乱の悲劇を江戸期の平和なにぎわいのなかで語ろうとする、大衆娯楽としての要素を持ちあわせていたかもしれない。
岩佐又兵衛にはエンターテインメントの資質があったわけで、この絵師をして浮世絵の始祖とする説も、じゅうぶんうなずける。
岩佐又兵衛の自画像は、ひょうひょうたる風情だが、戦乱の荒波を生きぬいてきただけあって、このひと、なかなか一筋縄ではいかない人物のようである。

最後は葛飾北斎。あまりにも有名で知ったつもりでいたが、はたして私は北斎のなにを知っているのだろうかと、少々不安になることがある。
風景画もあれば人物画もある。動物や植物も描いている。祭りの山車のための絵や、妖怪図、漫画、春画となにもかもがそろっている。
その三万点にもおよぶ作品は、内容も筆法も変幻自在で、どれが北斎の本領なのか、私の理解をはるかにこえている《富岳三十六景 神奈川沖浪裏》のおどろおどろしい荒波を描く殺気と、《北斎漫画》の軽妙洒脱が同一の作者によるものだというのだから、スゴすぎはしないか。
変幻自在といえば、北斎の名前は「北斎」だけではないというのもびっくりさせられる。北斎は、雅号をおよそ30回も改名したという。
「北斎」のほか、「辰政」「為一」などは、さほどおどろかないが、春画を描くときは「鉄棒ぬらぬら」である。晩年は「画狂老人」や「卍」と名乗っていた。凡人は自分の名前にやたら固執するものだが、北斎は名前の重圧から簡単にぬけだしていく。
そんな北斎の自画像もまた、風狂を装いフラフラしている老人として自分を描いているかと思えば(図9・3)、狂気をはらみ妖怪と化した83歳の自画像もある(図9・4)。相手にへりくだっているかのようなポーズと表情で好々爺に描かれるばあいもある(図9・5)。


どれが素顔に近いのかわからない。引越しも93回あったという。名前や住所といった“身分証明”から生涯逸脱しつづけた巷間の仙人は、たやすく本性を見せてはくれないのである。
明治以前の日本美術史から三人の自画像を紹介してみたが、いずれもあじわいぶかく興味がつきない。
それで、おもしろい自画像を描く日本の絵師がもっとほかにはいないかとさがしてみるのであるが、明兆(吉山明兆)や雪村らに自画像の逸品が見いだせはするものの、残念ながらそのあとがつづかない。
日本美術史は、尾形光琳、俵 屋宗達、円山応挙、長谷川等伯、狩野永徳と、すばらしい絵師の宝庫ではある。しかしかれらの手になる自画像はない。他人が描いたそのひとの肖像ならたまにのこっている。
しかしみずからが手がけた自分自身の肖像(自画像)はまれである。昨今人気が高騰している伊藤若冲も、本人の顔についてはよくわからない。
西洋美術史なら、自画像の名作を年代順にならべていくことで、美術の歴史や人間の精神史までもが語りうる。しかし日本美術史では、おもしろい自画像が散見できても、持続的な歴史を形成するまでにはいたらない。
単純化しすぎることを承知であえていうなら、日本美術とは環境芸術か宗教芸術のいずれかである。襖や壁や天井をいかに素晴らしく演出するかが、絵師にあたえられた役割であり、彫刻とは、寺に安置される祈りの対象を造形化する仏師の仕事のことである。
画家が鏡に自分の顔を映しだし、自問自答するような私的な探求など、さしはさむ余地があろうはずはないのだ。
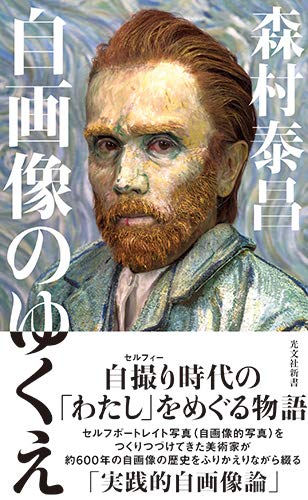
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.