ryomiyagi
2020/09/08
ryomiyagi
2020/09/08

ロシア文学の多くは、登場人物の名前が長く複雑であるため、覚えづらくてなかなか感情移入できない。その上、暗い・難しいというイメージがあり、タイトルは知っているけれど、まだ読んだことがない――。
『桜の園』に対するイメージを聞くと、こう答える人が少なくない。
かく言う筆者もそうだった。戯曲とは、そもそも舞台上で役者が演じることを目的に書かれた脚本であるため、小説のような情景描写がない。シーンによっては発言者が目まぐるしく変わるため、登場人物たちの生い立ちも、彼らが置かれている歴史的背景についてもさほど説明がなされないまま、会話だけが軽やかに展開していくように感じていたのだ。短いセリフの核心に触れることができないまま、ページをめくっていた。
しかし、『小説で読む世界の戯曲』シリーズの第1弾である『桜の園』は、登場人物の人となりがしっかりと分かり、個性が際立っていることが印象的だった。それぞれの顔立ちや表情、19世紀の装いといった外見はもちろん、本作には彼らの内面が語られるオリジナルのシーンも少なくない。
例えば、今では実業家となった主人公・ロパーヒンがまだ少年だった頃、元農奴であった父親のなけなしの誇りを傷つけたために、暴行を受けるシーン。また、この上なく美しく愛情溢れる貴婦人然としながら、その実承認欲求に囚われているラネーフスカヤが、金銭を搾取されながらも若い愛人に依存していく心理描写など。戯曲では割愛されている生々しいエピソードを繊細な筆で丁寧に描くことで、登場人物たちが背負っている歴史、抱えている感情や葛藤、原体験が色鮮やかに立ち上がる。
かつて桜の園の領主に所有され、代々、家畜同然に売り買いされる農奴であったロパーヒンの一族。対して、彼らを所有し続けてきた領主である、ラネーフスカヤの一族。1861年に「農奴解放令」が発布されたとはいえ、その身分格差はそれぞれの価値観として、現在も根深く残っている。
(前略)こちらをじっと見つめたまま、ラネーフスカヤが眉ひとつ動かさずに言った。
「でも、別荘族って、申し訳ないけど、低級なのよねえ」
ラネーフスカヤの目を見て、ロパーヒンは悟った。
彼女は別荘族を嫌悪してさえいない。それ以前に、微塵(みじん)も興味がないのだ。別荘族など自分の人生には、これまでも、これからも一切関わることがないと、心の底から確信している人間の、冷ややかな微笑みがそこにあった。(【第二幕】P.123~124)
今や借金まみれであるラネーフスカヤに、資金調達と収益化に向けた事業計画を提案したロパーヒン。彼に対して、ラネーフスカヤが見せた表情である。
本作は随所に自然の美しい風景が描かれており、とりわけ、登場人物の心の移ろいが投影された、桜の樹々の様々な表情が目を引く。そして、その中にふと、こういった残酷な描写が小さな棘のように潜んでいる。現実に対する登場人物たちの温度差も含め、極端といえる差異も、本作の特徴といえるだろう。
本作最大のクライマックスである、【第三幕】の競売のシーンも、本間によるオリジナルだ。
競売場を覆う緊迫した空気の中で、ロパーヒンは自分の全財産をかけて桜の園を守ってやろうと決意しながらも、当事者である領主のガーエフ※からなお差別され続けていることで、ふと自問自答するシーンがある。(※ラネーフスカヤの兄)
(前略)自分が事業を続けている理由を改めて考えた。(中略)ヘドロの底のような境遇から這い出したいと必死で立ち上がったのではなかったか。貴族たちに下種だとけなされるたびに、自分と同じ境遇で育った仲間たちを思ってきたのではなかったか。実業家として成功を目指し続けているのは、自分のためだけではない。自分が成功をつかむ姿が、同じ境遇を生き抜いてきた仲間たちに、己の可能性を確信させるだけの小さな例になると、考えているからではなかったか。
(中略)
俺が買う。時代が変わったのだ。百姓の息子でも、これだけの領地の地主になれるのだと、同じ境遇の仲間に伝えよう。(【第三幕】P.206~207)
この瞬間に貴族は没落し、ロパーヒンとラネーフスカヤ一家との立場が逆転する。そして、現実を飲み込んでいく領主のあり様も真に迫っている。
ガーエフはロパーヒンをにらみつけた。この守銭奴が、と続けるか? ロパーヒンはガーエフの目をまっすぐに見つめ返す。しかし、ガーエフに、ロパーヒンをなじる力はないようだ。ガーエフが状況を飲みこんでいくのがありありと伝わった。ガーエフの目に混乱から、怒りが湧き、一瞬すがるような顔をして、すっと生命力が消えていった。(【第三幕】P.208)
作者のもとには本作を読み終えた人たちから、「引き込まれて一気に読んだ」「桜の園がどういった物語なのか理解できた」「時代が変わろうとする、当時のロシアの空気がリアルに感じられた」といった感想が寄せられているという。
また、中には「自分がまだ駆け出しで、必死だった頃を思い出した。そして立場が変わった今だからこそ分かることが、この小説にはあった」という声も。
本作を書いた本間文子(ほんまあやこ)は、2002年に『ボディロック? 』で第10回ストリートノベル大賞を受賞し、リトルモアからデビュー。アップルシード・エージェンシーのプロデュースによる『桜の園』は、3冊目の単行本となる。
「いい作品を書けるという期待感が持て、『桜の園』の持つ世界観に合っていそうだった」
本間に執筆を依頼した理由を、アップルシード・エージェンシーの鬼塚忠社長が振り返る。
「原作を読み返すたびに、作中人物それぞれに共感や同情を覚えました」と、本間も語る。執筆に際しては、「家柄や過去に囚われながらも前進しようともがき続ける人間を、また彼らの“業”を歪曲せず、そのまま描ききろう」と決めていた。これは、本間が小説を書く理由に通じるのだという。

「私はずっと、人間関係の端で “変わり者” 扱いされている仲間に向けて小説を書いています。勇気を出して人間関係を変えたり、自立できるだけの社会的な力をつけて住む場所を変えたりすることで、今矯正されそうになっている個性を糧に生きていけるようになるから、あまりにも他人を傷つけるのでなければ、決して心の翼を折らないでほしい。そう伝えたくて」
高貴な俗物と正義の成り上がり――。いささか過激な表現であるが、単行本の帯に書かれた文言は、本間自らの言葉であるという。この一文は、『桜の園』中の差異を象徴しているかのように感じられる。同時に、筆者にはこの一文が本間の姿勢の表明であるようにも読めた。
(前略)何様のつもり? あなたはどんなに難しい問題でも正論をふりかざして済ませるけれど、それはまだ人生がゆらぐほど大きな悩みに苦しんだことがないから、軽く片づけられるだけなのよ。ペーチャは、人間が割り切れない生き物なのだということこそ学んだ方がいいわよ。(【第三幕】P.183)
ラネーフスカヤが初めて、怒気のままに吐露した言葉だ。彼女の本音にも耳を傾けながら、『桜の園』を読んでみたい。
過去の作品を通して、本間の小説は “生き直し” や “再出発” といった一縷の光を予感させながら、その物語を閉じてきた。本作もまた、大きく移り変わる時代の波を越えて、それぞれが新しい人生を歩み始めるところで幕が下りる。コロナ禍の今、どこか私たちへのエールにも読み取れるのは、筆者だけだろうか。
【あらすじ】
舞台は19世紀、「農奴解放令」発布後のロシア。古くから「桜の園」と呼ばれてきた広大なサクランボ畑を持つ貴族の家に、領土主であるラネーフスカヤ夫人が5年ぶりに帰ってきたところから、物語は始まる。ラネーフスカヤの家は破産寸前で、資金繰りの目途が立たなければ、もうすぐ全領土が競売にかけられてしまう。それを阻止すべく、実業家のロパーヒンが立ち上がった。しかし、別荘地としての事業展開を提案するも、貴族たちには暖簾(のれん)に腕押し。とうとう競売にかけられた桜の園を手中に収めるのは誰なのか――? 原作は、ロシアの文豪チェーホフにより1902年に書き上げられ、1904年に初上演された戯曲である。
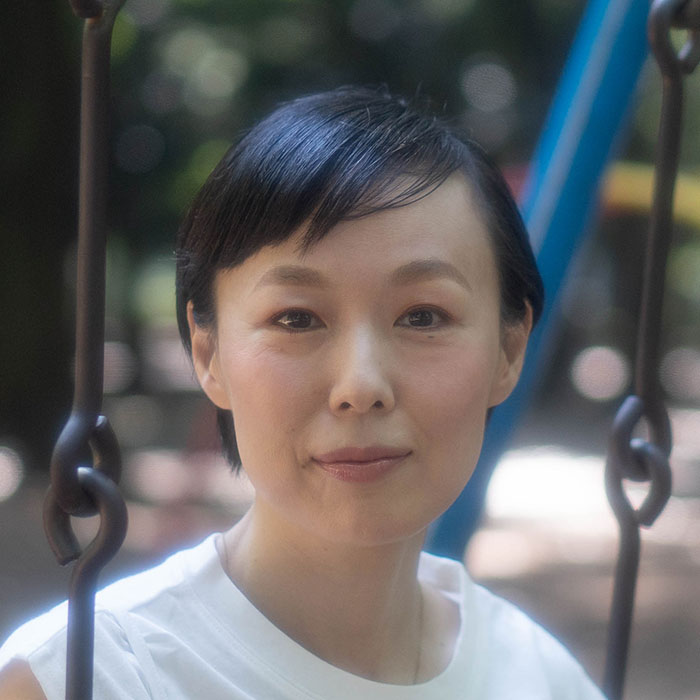
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.