ryomiyagi
2021/07/01
ryomiyagi
2021/07/01
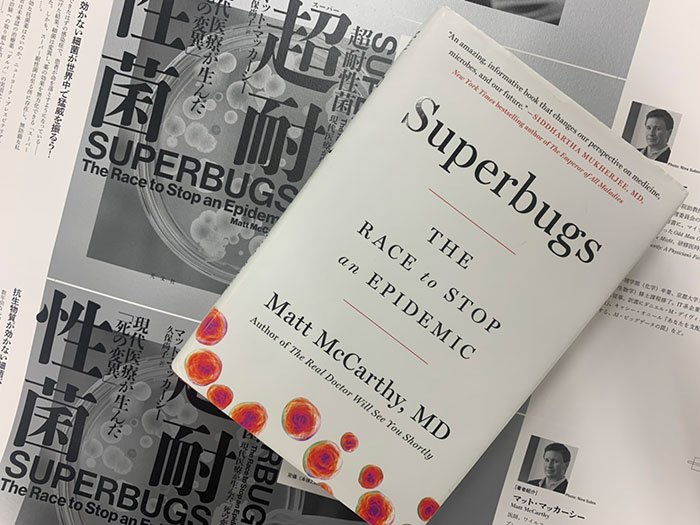
※本稿はマット・マッカーシー『超(スーパー)耐性菌 現代医療が生んだ「死の変異」』収録の「訳者あとがき」を抜粋・再構成したものです。
ニューヨークで一人目の新型コロナウイルス感染者が確認された日の翌日、2020年3月2日、『超耐性菌』の著者マット・マッカーシー氏は、米大手製薬会社ファイザーの取締役スコット・ゴットリーブ氏とともに、米国のニュース専門放送局CNBCの番組にゲスト出演していた。感染症の専門医として、これからニューヨークで、全米で、何が起きようとしているのかを予測し、診断検査が利用できない現状を憂い、診断検査の必要性を懸命に訴えた。だが、番組のキャスターたちは、この時点では事の重大さがまだ飲み込めていない様子で、マッカーシー氏が熱くなればなるほど、ジョークを交えて話をはぐらかした。まさか彼の予測が現実のものとなって迫ってくるとは、すぐには想定できなかったのだろう。その番組の一週間後には、マッカーシー氏が勤務する病院でも実際に感染患者が確認され、以来、彼は救急医療の現場に立って患者の治療にあたりながら、COVID-19の研究にも携わっている。
コロナ禍を経験したことで、今、私たちは、治療法のない感染症の恐ろしさを身に染みて感じている。一日も早くワクチンが行き渡り、確かな治療薬が登場することを願っている。
だが、薬が効かない病との闘いは、もっと前から始まっていた。マッカーシー氏は以前から、抗菌薬が効かない「スーパー耐性菌」による感染症の治療薬を求めて、医療の最前線で奮闘していたのだ。そして、その闘いが本格化するのは、おそらく、まだこれからだ。COVID-19の世界的流行が落ち着いたとしても、感染症との闘いはそれで終わりとは限らない。
『超耐性菌』はそんな闘いを続けている著者が、ある抗菌薬の治験にまつわる実話をもとに、自身の奮闘の日々を描いた物語、Superbugs: The Race to Stop an Epidemic(Avery, New York, 2019)の全訳である。

舞台はニューヨークのマンハッタン。物語は2014年10月から始まる。ニューヨーク・プレスビテリアン病院の救急治療室に、左脚を銃で撃たれた男性が運び込まれた。その治療のために呼び出された著者マットは、その患者が多剤耐性菌に感染していて治療がとても困難であることに気づく。かつて、抗生物質は細菌感染症に対する天然の特効薬としてもてはやされ、抗生物質を模した新しい抗菌薬も次々に開発されてきた。ところが近年、抗菌薬の使い過ぎが問題になっている。医療現場での不適切な処方習慣や農畜産業での見境のない商業利用が、細菌の変異を促した。複数の抗菌薬に耐性をもつように変異した多剤耐性菌が世界中の至るところで発生するようになり、医師や研究者のあいだでは、「スーパー耐性菌」と呼ばれて恐れられている。以前なら薬で治せたはずの感染症に薬が効かなくなり、患者の命を救うことが難しくなっているのだ。目の前の患者を救うためには、新しい抗菌薬が必要だった。
ちょうどこれと同じ日に、マットは共同研究者のトム・ウォルシュから、ある知らせを受けていた。大手製薬会社が開発中の新規分子のなかに、スーパー耐性菌に感染した患者の治療薬候補になりそうな分子があるので、治療薬として承認を受けるために、臨床試験(治験)を実施してほしいという依頼が来ているというのだ。トムは原因不明の感染症に関する世界的権威であり、治療困難な感染症患者を抱える世界中の医師から相談を受けながら、国際研究チームのリーダーとして新しい抗菌薬の開発にも取り組んでいる。マットは、トムと一緒にこの治験を引き受けることにした。その瞬間から、スーパー耐性菌の蔓延を阻止するための闘いの最前線に身を置くことになったのだ。
ここで念のために補足しておくが、抗菌薬(抗生物質など)は、細菌が原因の感染症に対する治療薬である。ウイルスと細菌は大きさも増殖の仕組みも異なるので、ウイルスに抗菌薬は効かない。ウイルス感染症の治療には抗ウイルス薬が必要だ。油断すると混同しそうになるが、少し意識しておくと、理解の助けになるかもしれない。
とはいえ、抗菌薬にせよ、抗ウイルス薬にせよ、新しい治療薬として承認を受けるためには、治験を実施して安全性と有効性を確認する必要がある。薬の種類は違っても、治験を担当する医師らが直面する現実や苦労には共通する部分も多いだろう。
治験を実施するには、まず、プロトコールと呼ばれる治験計画書を作成する必要がある。本書のなかでトムは「プロトコールですべてが決まる」と言っている。薬の「候補」をヒトに試すことになるのだから、治験に参加する人たちの人権や安全が守られているか、倫理的に不適切な点はないか、副作用や効果の評価方法は科学的に正しいか、といった点に十分に配慮しなければならない。完成した計画書は、利害関係のない治験審査委員会(IRB)による審査を受ける。この審査に通らなければ、治験を実施することはできない。審査に通るまで、何度でも計画書を修正することになるわけだ。
プロトコールが承認されれば、いよいよ治験が始まる。プロトコールで定められた治験対象者の条件に合いそうな患者が見つかったら、その患者と面談し、本当に条件に合っているかを確認し、治験について詳しい説明をしたうえで、インフォームド・コンセントを取得しなくてはならない。マット自身も治験前期(観察試験)に参加してくれるボランティアの患者を探して回ることになるのだが――人に歴史あり。同じような症状に苦しむ患者だとしても、まったく同じ患者などいない。それぞれにさまざまな事情を抱えている。治験の結果は数字で表されるが、医師が向き合う相手は、生身の人間だ。そして、面談を通してそこに立ち入ることになる医師自身もまた人間なのだということを、本書は臨場感をもって描き出している。
治験の運営に悩み、患者の治療に悩み、家族の問題にも苦悩するマットは、折々に、病院の外の空気を吸いに出る。随所に登場するマンハッタンの風景は、仕事や観光でニューヨークを訪れたことのある読者にとって、これは現実の話なのだとハッとさせられる要素にもなるだろう。本書後半では、同じマンハッタンの街で進められてきた感染症研究がいくつか紹介される。いずれもマットが勤務するニューヨーク・プレスビテリアン病院の近所にある有名な研究所での出来事だ。マットも実際に足を運び、研究者本人から詳しい話を聞いている。抗菌薬開発の最先端の話は、マットにとっても私たち読者にとっても、希望の光のように感じられる。
ようやく治験後期(投与試験)が始まると、実際に患者に薬を投与し、治療の経過を改善できるかどうか確かめていく。マットは再び、条件に合いそうな患者と面談し、さまざまな人生の機微に触れることになるが、それでも、前期の観察試験とは異なり、今回は条件に合う患者からインフォームド・コンセントが得られれば、その薬をすぐに投与することができる。目の前の患者を治療できるかもしれないのだ。しかし、本当に効くかどうかは、投与してみなければわからない。まだ誰も使用したことのない薬の「候補」を使うことに同意してくれる患者を探すのは、そう簡単なことではなかった。マットの物語がどのように締めくくられるのかは、本編でお楽しみいただきたい。
本書の翻訳をご依頼いただいてすぐのころに、私はツアー旅行でニューヨークを観光した。帰国後にこの本を訳すことを意識して歩き回ったので、マンハッタンの街の様子がしっかりと記憶に残っている。まだ新型コロナウイルスが登場する前のマンハッタンだ。今、あらためて、一日も早くあの日常が戻ってきてほしいと願っている。そして、このような感染症の世界的流行が繰り返されることのないように、スーパー耐性菌の蔓延を阻止するために何が必要なのかを、本書を通じて多くの人に知ってもらえたなら幸いである。
久保尚子 くぼ・なおこ
翻訳家。京都大学理学部(化学)卒業、京都大学大学院理学研究科(分子生物学)修士課程修了。IT系企業勤務を経て、翻訳業に従事。訳書にダニエル・M・デイヴィス『美しき免疫の力』、キャシー・オニール『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビックデータの罠』など。
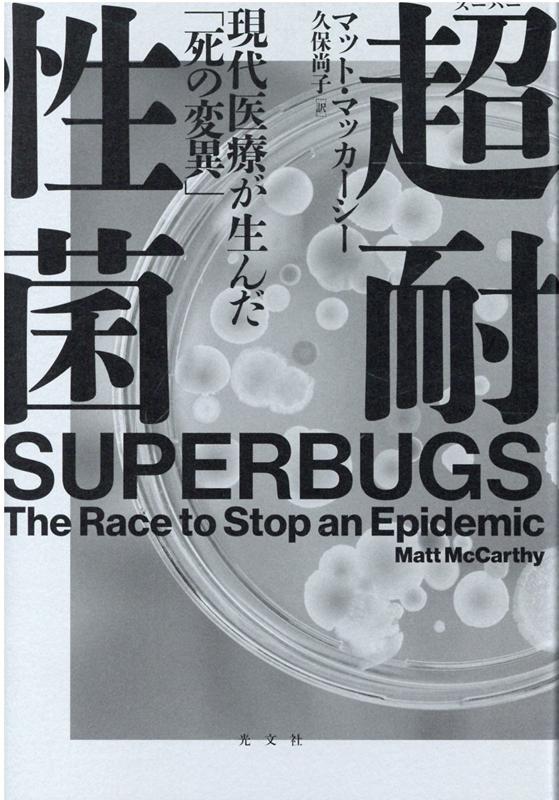
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.