BW_machida
2022/07/28
BW_machida
2022/07/28

本書の内容は多岐にわたる。いい写真とは何かという問いかけに始まり、写真を撮る者の条件、被写体との関係、今という瞬間をどのように撮影するか。最終章では、写真はなぜ「わからない」のかを考える。鑑賞する側、評論する側からではなく、撮る側が抱える「わからなさ」の正体とはいったい何なのか。
著者いわく、「わからなさ」は写真というメディアに常について回るものらしい。この「わからなさ」は、ときに喜びをもたらしてくれる。
「それはもしかしたら、人間が人間に飽きることがないのと似ているかもしれない。写真であれ、人間であれ、やはり『わからなさ』というものが存在しているからだ。予測不能、コントロール不能で、常に変化している。」
写真を観る側にも「わからなさ」を感じている人はいるのではないだろうか。映画を観て、あるいは小説を読んで涙を流したことはあっても、写真を見て涙を流したという話はあまり聞かない。その理由を著者は、写真が他のどのメディアよりも観る側に託す部分が大きいためだと説明する。つまり、求心力の差である。
画像が動き続ける映画は、写真と比べて情報量が圧倒的に多い。さらに言葉と音楽が加わることで、強烈に観賞者の五感へ訴えることを可能にする。なにより、こうした映像作品には、始まりから終わりにかけての明確なストーリーがある。これが写真となると事情は違ってくる。写真展には、あらかじめ決められた順路はあるものの、逆から観始めたとしても問題はない。写真集がそうであるように、写真はどの順で観ても成立するし、映画のような強制力もない。
「額の中やページの中で写真は黙って静止しているだけだ。つまり、観る人を静かに待っているだけだ。どこまでも受け身なのである。だからこそ観る側に委ね、観る側の観る力にたよるところが大きくなる。観る側の想像力も含めた写真を読む力に頼らざるをえない。このことは、写真全般を語る上で重要なポイントだ。」
写真をどのように受け取るかは、観る側に委ねられている。では、撮影者の意図を知るにはどうしたらよいのだろう――と思っていたら、趣味も興味も思考も世代も違う全ての人に同じように伝わる写真はないと断言されてしまった。さらに「写真を観た人の6割くらいの人にこちらの意図が伝われば上出来」と述べたうえで、「10人中10人に伝わる写真は、つまらない」とも。写真はすべての人に同じように伝わるメディアではない。そこに新鮮さがあり、オリジナリティがあるのだ。つまり、新たな価値観の提示である。
最終章では、撮る者と観る者、双方が感じる写真の「わからなさ」が丁寧に語られていく。いい写真とは、こういうことかと教えられる。著者の熱気のようなものが伝わってきて、読むほうも夢中になってしまう。
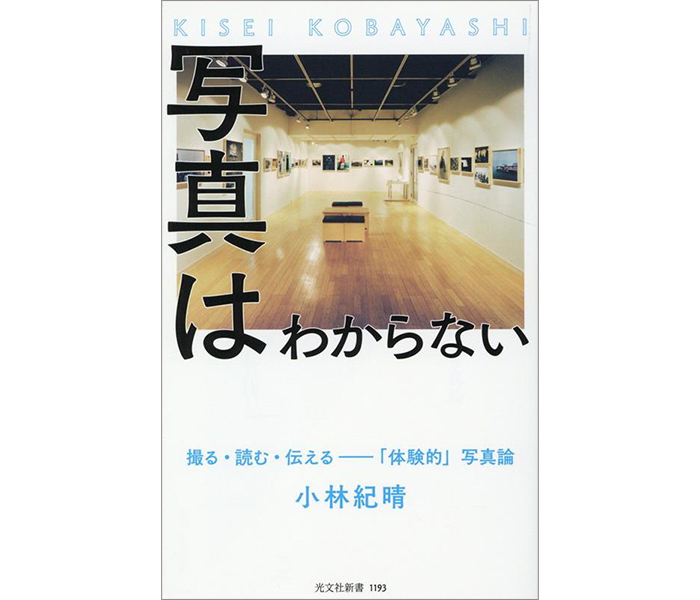
『写真はわからない』
小林紀晴/著
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.