2018/12/11
石戸諭 記者・ノンフィクションライター
『大江健三郎全小説 第3巻』講談社
大江健三郎/著
戦後文学の一つの到達点であり、偉大な才能であり、最大のタブー作を生み出した作家、それがノーベル文学賞作家・大江健三郎である。彼の社会的発言だけを聞きかじって、「戦後民主主義」的な価値観をひきづった過去の人と結論づけるのはもったいない。
一人の少年にある性的な恍惚感と政治の接点、暴力的な言葉を叫び、テロリストになっていく心理を誰よりも克明に描写した『セヴンティーン』『政治少年死す』は今の時代にこそ読まれるべき小説なのだから。
『政治少年死す』は1961年2月号の「文學界」発表以降、右翼団体の抗議を受けて長らく書籍未収録だった。本作はいまも文庫でも手に入る小説『セヴンティーン』の第二部と位置付けられている。一部と二部を連続して読むことが50年以上できなかったのだ。詳細な経緯は本書収録の解説に収められているので、ここでは触れない。
本書をあらためて読み、20代の大江が描いたこの2作は連続して読んでこそ初めて真価が発揮されるのだと思い知る。
『セヴンティーン』は、「17歳=セヴンティーン」になったばかりの「おれ」が一人称で世界に苛立ちをぶつけ、性を語り、時代の閉塞感を畳み掛けるようにぶちまける。「おれ」は極右団体の活動と出会い、多くのインテリが《左》のご時世にあえて《右》になる。「おれ」は《右》として、「十万の《左》どもに立ちむかう」。彼は恍惚感とともに「最も勇敢で最も凶暴な、最も右よりのセヴンティーン」になっていく。
第二部は「おれ」が「死を超え、死から恐怖の牙をもぎとり、恐怖を至福にかえて死をかざる存在」である「純粋天皇」との一体化を夢見て、テロリストとして政治家を刺殺する。大江の想像力は、現実に起きた右翼少年・山口二矢による社会党委員長刺殺事件と密接にリンクする小説を生み出した。
「おれ」は性的な衝動を大いなる「純粋天皇」にぶつけるかのように、政治的にエスカレートし、テロへと突っ走る。「おれ」の純粋すぎる危うさは、世界で起きる自爆テロ、真偽不確かな情報をもとに「在日」をバッシングする日本の極右にのめり込む心理に通じるものがある。
大江は読売新聞記者であり、おそらく彼が最も信頼している聞き手であろう尾崎真理子のインタビューにこう答えている。
「戦後民主主義者である自分の中には、天皇に命を捧げる右翼少年の心情に入っていって小説に書きたいという、矛盾した思いも抑え難くあった。10年くらい左右両派から激しく攻撃されました」
「様々なテロが起こるたび、“今、起きていることは自分がかつて小説に書いた”と感じてきた。なぜ若者たちは自爆テロに突き進むのか。政治的な熱狂と性的な衝動は人間の同じところから発生し、現実化する……。青年の頃、未熟なまま直観して『叫び声』なども書いたのです」(読売新聞2018年5月6日付朝刊)
社会的発言以上に作品は雄弁に作家の思想を語る。政治的に正しい立場からの発言だけでなく、抑えがたい矛盾や衝動を描く。そこに時代を超えた叫びが内包されている。
書かれた時代以上に暴力的な言葉が社会を飛び交う「今」こそ、若き大江の作品群は同時代性を持つ。彼が多用する言葉をあえて使えば、それ自体が一つの「アイロニー」のなのだが……。
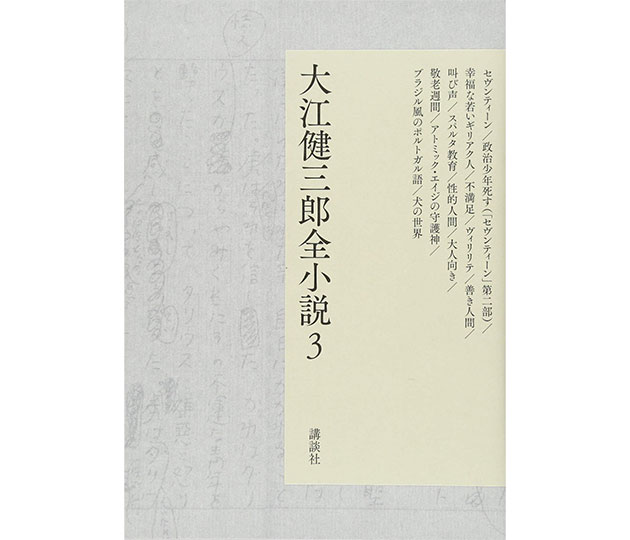
『大江健三郎全小説 第3巻』講談社
大江健三郎/著

