2020/02/04
横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店
『西の魔女が死んだ』新潮社
梨木香歩/著

この物語とはじめて出会ったのは、いつのことだっただろう。たしか、高校生か大学生の頃だったと思うけれど、はっきりとした記憶はない。その頃の私は、図書館で片端から本を借り、読み漁っていた。むかしから、本を読むのが好きだった。ページを開くと途端に広がる未知の世界を知ることが、何よりも楽しくしあわせだった。でも、私が本を手に取っていた理由はそれだけではなかった。私は物語に、自分の「居場所」を求めていた。それは大人になった私にも必要な場所だけれど、当時の私は今の私とは違う、もっと切実な理由で物語を欲していた。その頃に出会った、たくさんの物語の中の一冊がこの本だった。
主人公のまいは、中学一年生。季節の変わり目に喘息を発症して学校を休んでから、学校に通うことができなくなってしまった。単身赴任中のパパと、まいと二人で暮らすママで話し合った結果、まいは離れて暮らすママのママ、“西の魔女”のもとに預けられることになった。
おばあちゃんには“西の魔女”と呼ばれる理由があった。英国人のおばあちゃんは、黒に近い褐色の大きな瞳と半分以上白くなった褐色の髪に、骨格のしっかりした大柄な身体という出で立ちをしている。そして、まるで全てお見通しとでもいうように、にやりと魔女みたいに笑う。
また、家系の中に透視や予知ができる人がいて、おばあちゃんは妹とともに、叔母に魔女教育を受けたという。血を受け継ぐまいにもその素質があるけれど、素質があるだけでは、本物の魔女にはなれない。“本物”になるためには何事も修業が必要なのだ。その為には早寝早起きをして、食事をしっかりとって運動をすること。規則正しい生活を送るという基礎を、まず身につけなければならなかった。
おばあちゃんと家事をしたり、庭仕事をしたり。時には自然の中に身を置き、ぼーっとしたり。日常に溶け込む暮らしの知恵や、冷静に物事を判断する心の在り方を教えてもらったり。すべてが、魔女になるための修業の一環だった。やがておばあちゃんと過ごすうちに、まいは本来の自分の力を取り戻していきつつあった。
しかし、それと比例するように、心の闇の部分とも向き合わざるえないような出来事も起こってきた。隣の家に住む隣人への猜疑心と嫌悪感。田舎特有のだらしない寛容さへの苛立ち。無残にも破壊された命の生々しい姿。時おり顔を覗かす、ママとパパの浅はかさ。抑えきれずにおばあちゃんにぶつけてしまった怒りの感情。
心の闇の部分が出てくる度に、おばあちゃんは、まいを受け止め、励ましてくれた。
<「おばあちゃん、大好き」「アイ・ノウ」>
そう、まいにとって一番必要だったのは、どんな時でも飛び込める、自分だけの居場所だった。
おばあちゃんと暮らし始めてしばらくしたころ、引っ越して三人で暮らそうとパパが提案してきた。まいは迷ったけれど、パパとママと一緒に暮らす道を選んだ。おばあちゃんと離れたくないと思うと同時に、このままこの場所で暮らし続けるのも違う気がした。新しい場所で魔女修業に勤しもうとも思えた。けれど、急速に慌ただしくなった現実と、心の折り合いがつかなくて、おばあちゃんとうまく別れることができなかった。しこりを残したまま、新しい生活は否応なくスタートし、結局おばあちゃんと再び会うことができず、二年という歳月があっという間に流れた。
魔女は最後に、まいに贈り物を残してくれた。人はなぜ、困難だらけのこの世界に生まれてくるのか?死ぬって、何?かつて、まいが疑問をぶつけたことの答え、“死”を経験した魔女からの、まいだけにしか分からない方法で伝えられたメッセージ。それは、魔女からの愛と光の贈り物だった。
あの頃の私が、この本と出会ったのは偶然なんかじゃなかったと強く思う。私もまいと同じ、孤独な心を抱え立ちすくむ、力なき少女だった。家族がいても、友だちがいても、心にぽっかり空いた真っ暗な穴を埋めることはできなかった。その穴は真っ暗で底が見えなくて、「寂しい」って叫んでいる私が膝を抱える場所だった。誰にもこの気持ちを分かってもらえないと涙をこぼす場所だった。
きっと、私たちは繊細過ぎたのだ。繊細で傷つきやすい心を持っているがゆえに、周囲の人の些細な言動に傷つき、心を閉ざし蹲り、たったひとりで泣いていた女の子だったのだ。
まいにとっての西の魔女のように、私に魔法をかけてくれたのは、たくさんの本だった。私に似た主人公たちは、ページを開くといつでも私の心に寄り添ってくれた。私だけじゃないって、ひとりじゃないんだって、どんなに心を励まされたかわからない。そして、本からもらったたくさんの言葉は、私に抱えきれないほどの知恵と勇気を与えてくれた。
私は、本物の魔法の力を知っている。それは、私自身が本から授かったたくさんの言葉の中に内包されていた。だから、今度は私が渡したい。辛いときや悲しいとき、さりげなく、でも真っ直ぐに、あなたの心に届く善き魔法をかけてあげたい。
「アイ・ノウ」
「マイ・ディア」
本の中で鳴り響いていた言葉は、私の中からも聞こえてくる。
西の魔女は、私にも魔法をかけてくれた偉大な魔女だった。
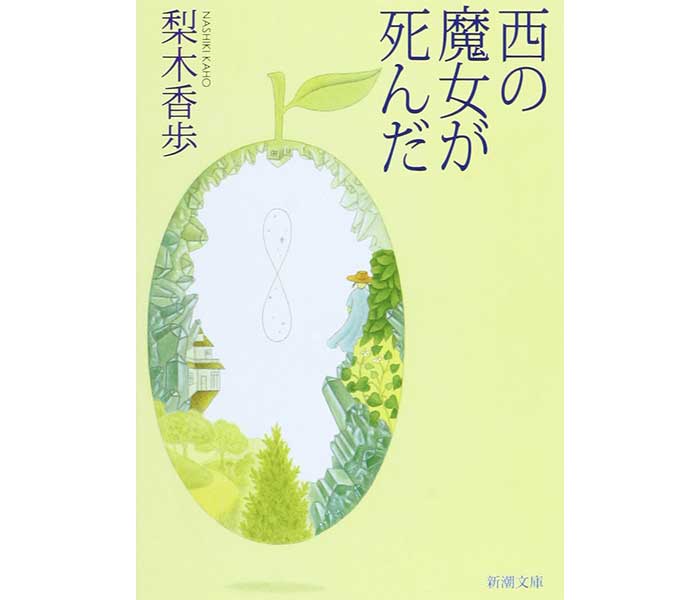
『西の魔女が死んだ』新潮社
梨木香歩/著

