2020/02/12
坂爪真吾 NPO法人風テラス理事長
『精神病理学私記』日本評論社
H・S・サリヴァン/著 阿部大樹、須貝秀平/訳

本書は、アメリカ精神医学の先駆者であり、現代精神医療の基礎を築いたH.S.サリヴァンが、1929年〜1933年にかけて執筆した私記である。
サリヴァンが生前に書き下ろした唯一の著作であり、同性愛者である彼自身の性的指向とアルコール耽溺、 スキゾフレニア(統合失調症)やパラノイア(偏執病)について語っている。
文化人類学者のルース・ベネディクトなど、同時代の著名な社会科学者とも親交があったサリヴァンは、強い社会志向性を持っていた。
「精神医学は対人関係の学である」「病の原因を個人に求めるのではなく、周囲の人との交流全体に求めるべき」と考え、社会のあり方が精神障害に対してどれほど甚大な影響を与えているかという点に着目した。
サリヴァンの臨床理論は、1940年代以降のアメリカ精神医学界において絶大な影響を与えた。その一方で、共産主義陣営との接触の疑いをかけられたり、同性愛への親和的言説に対する忌避もあり、死後、その著作の出版は差し止められていた。
「精神病理学は市井の人びとに目を向ける」と主張したサリヴァンは、シカゴのスラムや精神病院を訪れる人々に接する中で、精緻な観察や人間的な相互交流を通して、友人、家族、患者、そして自分自身がどのように変化していくかを見つめた。
そうした実践の中から、「精神病理学とは、人格が育つ過程について学ぶこと、それによって人間同士が関係を結ぶことの限界について知ること」「机に向かって苦吟することで到達できるものではない。理解することそれ自体が人格の発展に結びつくような知の体系こそ、精神病理学と呼ばれるべきである」といった主張が生まれてくることになる。
サリヴァンは、精神疾患に伴う社会的課題を解決することは、社会的承認と個人的昇華を近接させるために知恵を絞ることにある、と述べている。
昇華とは、社会的に実現不可能な目標、葛藤や満たす事が出来ない欲求から、別のより高度で社会に認められる目標(芸術・スポーツ・学問など)に目を向け、その実現によって自己実現を図ろうとすることを指す。
そうした個人的昇華によって得られた成果が社会的承認につながれば、個人も社会もプラスの方向に発展する、というわけだ。
しかし、実際に社会課題の現場で起こっていることは、その正反対であることが多い。
NPOや社会運動の世界では、自分自身の劣等感や不全感を埋めるために、都合の良い「敵」や「加害者」を作り上げて、それを叩くことを「社会のため」「正義のため」と主張する人たちが少なくない。
自ら作り上げた「加害者」を叩くこと、そして都合の良い「被害者」に同一化することに熱心になり、反対意見に耳を傾けることもしない。
持論に沿わない現実は最初から見ないため、不安を直視することが回避され、本質的ではない問題に手当たり次第に突っかかっていくようになる。自分たちの外部に欠陥を見出すことで、自分の中の葛藤やコンプレックスと向き合うことを避ける。
こうした振る舞いは、ジェンダーやセクシュアリティ(性差別やLGBTなど)をめぐる議論においては、より顕著かつ苛烈になる傾向がある。
SNSでの情報発信、クラウドファンディングやオンライン署名サイトの普及によって、誰もが気軽に社会を変える活動に関われるようになった反面、かつては一部の活動家特有のものだった原理主義的な思考や二項対立を煽る行動がタイムラインを通して「伝染」し、市井の人々の行動や思考を変容させるようになっている。
誰もが「被害者」のポジションに立ちたがり、安全圏から「社会正義」の名の下に「加害者」を糾弾することで得られる快楽や嗜虐性に囚われ、論理や倫理を見失ってしまう。いうなれば、「一億総活動家社会」だ。
こうした社会の中で、他者からの共感や承認を求める欲望(あるいはその裏返しとして、理解できない異質な他者を攻撃したくなる欲望)を暴走させずに、精神疾患に伴う社会課題を解決するため=社会的承認と個人的昇華を近接させるために、「人格が育つ過程について学ぶこと」「人間同士が関係を結ぶことの限界について知ること」について立ち止まって考える時間は、決して無駄ではないはずだ。
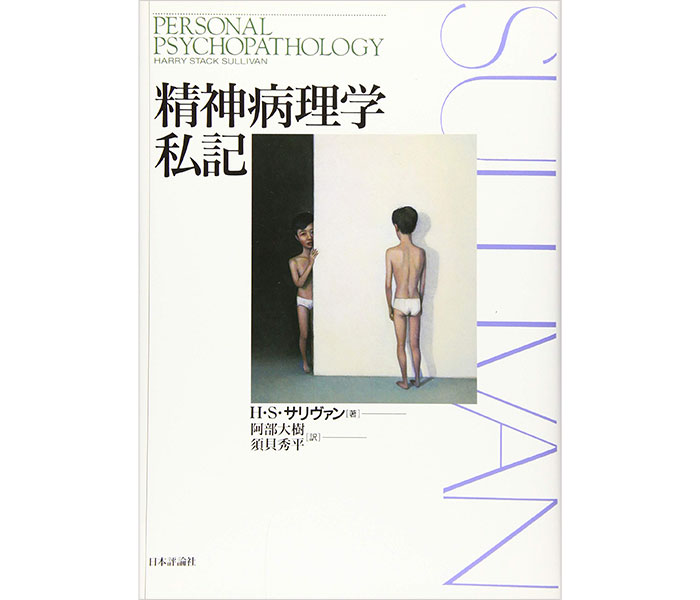
『精神病理学私記』日本評論社
H・S・サリヴァン/著 阿部大樹、須貝秀平/訳

