2020/05/19
田崎健太 ノンフィクション作家
『裁判官も人である 良心と組織の狭間で』講談社
岩瀬達哉 / 著

自分の狭量さを思い知るのは、評価に値しない思った本が、次々と重版が掛かるときだ(ほとんどの場合、そうした本は目を通していないのだが)。平たく言えば、嫉妬である――。
可能な限り人に会い、資料を漁り、ぎりぎりまで粘って原稿に推敲を重ねている自分が否定されたような気になる。売れる本にはそれなりの理由があるのだと言い聞かせてやり過ごすしかない。
一方、ぼくは物書きである以前に、子どもの頃から読書を愛する人間であった。いい本と出会ったときには、これはもっと読まれるべきだと思うこともある。
岩瀬達哉の『裁判官も人である 良心と組織の狭間で』(講談社)もそんな一冊だ。
題材は裁判官――非常に地味である。売上げで作家を値踏みするような編集者は一笑に付すはずだ(もちろん、そんな編集者には書き手も企画さえ持ち込まないだろうが)。そして、この本を読むと、ぼくたちは日本の三権分立が非常に危うい、いや、三権分立が機能していないという、不都合な事実を見せつけられることになる。
著者の岩瀬達哉は、裁判官たちを「正解指向」と表現する。
〈幼稚園の頃から、とびきりよくできると褒めそやされ、優等生として走り続けてきた彼らは挫折を知らず、下積み経験もなく育ってきた。まさに、エリート層の「上澄み」であり、元々正解指向で怪我をすることをひどく恐れている〉
この“正解指向”がなぜ問題なのか。ある研究会の出席者は「なぜ正解かという理屈を考えないで、こういう問題だったらこれが正解と機械的に覚えちゃっている」と証言する。
それなりに名の知れた大学に進学するような学生たちは、同じような家庭環境、経済環境になりがちである。そして就職してはじめて、自分たちが恵まれた環境で育ってきたことを自覚するものだ。裁判官たちのほとんどはそうした経験を経ることがない。
司法試験は難解である。試験勉強に没頭し、自分の周囲の均質化した社会から出ることはない。そして、試験に合格したというエリート意識が根深く彼らの躯の中に染みついている。そのため弱者に対する目がそもそも欠けがちだ。
裁判官という秀才たちは、自らをこう分析する。
〈自分を含め、修習生は基本的に小賢しい生き物で、指導官の求めている答えをすぐに読める。修習生は『おかしい』とか『それは刑事訴訟法の趣旨と異なる』などと思ったりしても、部長に逆らっても無駄であるという思いから、部長の欲している回答を出すようになるのである〉
つまり事なかれ主義、世間知らずの秀才たちが、生臭い人たちを裁いているのだ。
その秀才たちは、司法の独立を託すには、実に頼りない。
〈裁判官って、弱いんですよ。ひとり、一人は。ただのサラリーマンですから。とりわけ司法制度改革のあとは司法試験の合格者が急増していて、この20年間で弁護士人口は、2倍強に増えた。弁護士が余っていて、裁判官を辞めても弁護士に転身できないんです。だから当局に睨まれることなく、賢くやっていきたいという自信のないヒラメ裁判官が増えることになる〉
中には、そうでない裁判官もいる。
しかし、良心的な彼らはこの閉鎖的で陰湿な社会からはじき飛ばされる。
この本では、原子力発電所に関する裁判で最高裁の意に染まない判決を出した裁判官たちが地裁から家庭裁判所へ“左遷”された例が列挙されている。
匿名で取材に応じている裁判官の言葉が重い。
「良心に従って原発を停められるのは、定年退官か依願退官かは別にして裁判官を辞めると決めた時でしょう。でないと原発を停めた途端、裁判所での居場所をなくしてしまいますから」
法に則して判断するのではなく、国、最高裁の意向に沿って判決を出す。司法の独立など幻想に過ぎず、あらかじめ結論は決まっているのが現状なのだ。
その他、えん罪が生まれる背景、裁判員制度の問題点――本を読み進めるとこの国は本当に法治国家なのかと暗澹たる気持ちになる。だからこそ、読まれるべき一冊なのだ。
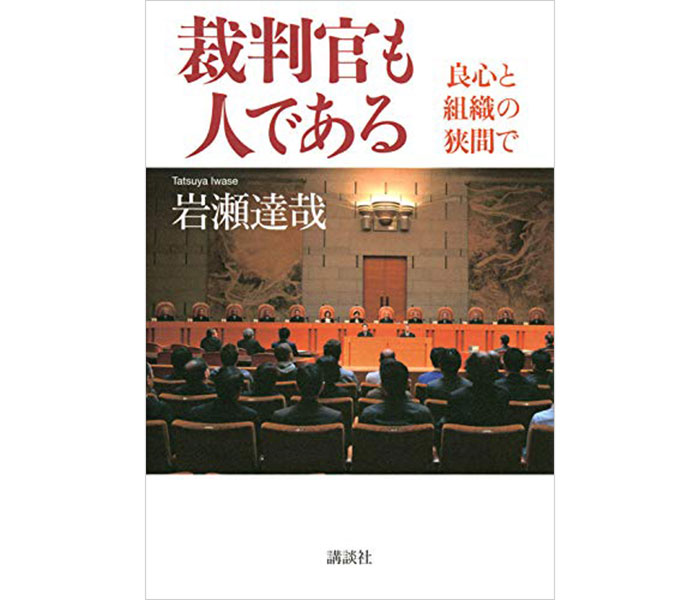
『裁判官も人である 良心と組織の狭間で』講談社
岩瀬達哉 / 著

