2020/07/17
藤代冥砂 写真家・作家
『熊 他三篇』岩波書店
ウィリアム・フォークナー/著 加島祥造/訳
ようやく「熊」を読んだ。
50年代に書かれた、アメリカ文学。ウィリアム・フォークナーによる狩猟小説。詩人ゲーリー・スナイダーに、とても重要な作品と評されたもの。
難解ともされるフォークナーだし、スナイダーの太鼓判付きともなれば、頭がクリアな時に、ベストコンディションで臨みたいと考えていたのだが、実際読み始めたのは、休日の昼食後で、幾重もの波となって襲いくる睡魔に抵抗しながらの読書だった。
いきなり余談だが、私が初めて読破を試みた原書が、フォークナーの「八月の光」で、その試みは挫折継続中なのだが、予想に反して、読みやすい英文だったのを覚えている。フォークナーを原書で読めたら格好いいな、という動機は、やがてケルアックを原書で読めたら格好いいな、に乗り換えられ、生涯初の読破した英書となったのが「路上」であることは、ちょっとした自慢でもある。
偶然にも50年代アメリカ文学2冊に手を出していたのだが、ケルアックに比べて、フォークナーは日本では知名度ほど若い読者を得ていないような気がしているが、僕の視野の狭さを示す感想かもしれない。
影響を受けた書物や作家の名前に、フォークナーを挙げた人を、実際私は一人も知らないのだ。
まあ、余談はこのくらいにして、ケルアックと同じくビートジェネレーションの一人として語られるスナイダーが認めていた「熊」。粗筋は控えたいが、やはり狩猟小説といっていいと思う。
少年が、森に入り、熊狩りに数年越しに参加し続け、そこでの人間、犬、森の生物、森全体、などの影響を受けながら成長していく様が描かれていることを踏まえれば、イニシエーションものとして読むことも出来るだろう。
読後直後の感触は、とてもどっしりとした古典を読んだ、という満足感と、ありきたりな言い方だが、今も、そしてこれからも古びない骨格と語り口を持った、堂々とした作品だと敬意さえ抱いた。
狩猟というのは、我々日本人が感覚的に共感しづらい、西洋狩猟民の「遊び」の一部でもある。ハンティング・スポーツというくらいで、体を動かし、汗をかき、獲物を仕留めるという得点を競うことで、確かにスポーツである。もともと貴族の嗜みに属していて、社交の一部でもあったことから、昔は命の尊厳という視点が入る余地がなかったのだろう。思えば、家康も鷹狩が好きだったわけだし、日本人の庶民には縁がなかったものの、権力者たちには、遊びとしてあったことも確かだ。
「熊」は、西洋人の「狩猟」への感覚を持ち得ない人が、例えば日本人の若い世代が読んでも、もちろん、面白い作品だと思う。
ここに描かれている森は、人間の文明生活の対比として置かれているのではなくて、あいまいな境はあるものの、地続きの闇としてある。町外れを行けば、田園があり、それが途切れる辺りから森となり、さらに奥へ行けば、闇となり、熊が、鹿が、狼がいる。さらに、長い距離を歩いていけば、やがて熊の懐に達するという感覚。これは、かつて日本人にもあった感覚だろう。もちろん、今でも地方によっては、この感覚が通用する場所も多いはずだが、それを察知する人間側の感受性は衰えていると思う。
物体としての森は現存しても、森の闇を出現させられる感覚は、どうなのだろう。
ここ数年、狩猟的生活、狩猟登山など、狩猟と名のつくものを目にすることが増えたが、彼らが本当にしたいのは、自分で鹿を屠って食べることで生命や生存のリアリティを再確認することよりも、衰えていく察知能力を取り戻したいという生存本能に近いのかもしれない。
それは暗部への、危険への感度と言い換えられる。
私は、フォークナーの「熊」を読みながら、娯楽的にも読めるこの狩猟小説の根底に流れる暗さが気になり続けた。人間の殺意、熊の殺意、犬の殺意。それらの殺意が暗いというわけでは、もちろんない。それらは、やっつけたいという明瞭な目的がある分、わかりやすく、明るいとさえ言える。暗さというのは、もっと不明瞭で、なおかつ、質量がずしりとある。
主人公の少年は、10歳で、熊狩りに加わる。成長にしがたって、相応の役割を与えられる。その過程で、少年は自らを鍛えるために、夜の森へとたった一人で入り、方向感覚、危険察知能力、その他、森で生き残るための、あらゆる能力を得ようとする。
熊が恐るのは、強い人間ではない。強い人間に対しては平然と通り過ぎていゆくだけだが、弱く怯える生き物に対しては潰しにかかる。怯えるものは何をしでかすか分からない。分からない常態のものこそ怖いのだという。
少年は、何に対しても怖がらない自分を作る。夜の森を歩き、さらに熊と出会おうとする。
熊と出会うために、身に付けた文明の利器、銃やライトなどを全て木の枝にぶら下げて、手ぶらで森を行き、そしてやがて熊に出会う。
私は、このシーンが大好きで、自分の山での体験と重ねて納得する。森を歩くと、鹿によく出くわす。お互い小さく驚いて、ただ見つめ合う。そのうちに、私の方がはっと気づいてカメラを取り出そうとする。必ずそのタイミングで鹿は慌てて森へと去っていくのだ。ただ見つめ合えればいいのに、余計な欲が邪気となって森の生き物に伝わるのだろう。私は、きっとどこかで怯えているのかもしれない。
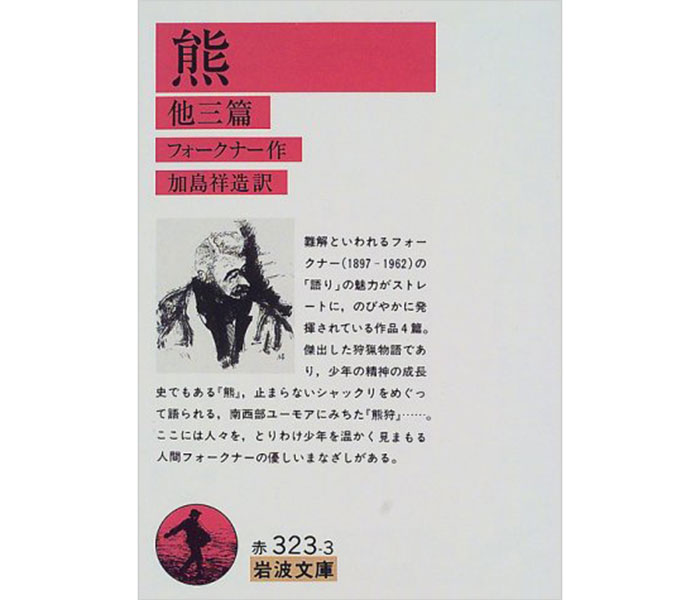
『熊 他三篇』岩波書店
ウィリアム・フォークナー/著 加島祥造

