2018/06/29
三砂慶明 「読書室」主宰
『華氏451度』ハヤカワ文庫SF
レイ・ブラッドベリ/著 伊藤典夫/訳
『やんごとなき読者』白水社
アラン ベネット/著 市川 恵里/訳
■「悪書」が存在しない世界『華氏451度』
本を読むことは、自分の頭で考える妨げになるのでしょうか? 力強く「NO」と答えてくれたのは、SFの巨匠、ブラッドベリです。本が自然発火してしまう温度、『華氏451度』で、ブラッドベリは、本を所持することや読むことが国家に対する犯罪とみなされる、全体主義的な近未来社会を描きました。人々は仕事中も耳に「海の貝」と名付けられた超小型ラジオをつけ、自宅の居間の壁はスクリーンのようなテレビに囲まれ、常に政府にとって都合の良い情報にさらされつづけている世界です。
「知性」という言葉は絶対の禁句で、主人公のガイ・モンターグは禁じられた本を発見して燃やす焚書隊の一員ですが、ある少女との出会いから、焚書の仕事に対して疑念をいだきはじめます。誰が悪書を決めるのか?
秦の始皇帝による焚書坑儒、ユリウス・カエサル軍によるアレキサンドリア図書館焼失、ナチス・ドイツでの焚書など、独裁国家による文化の破壊には枚挙のいとまがありませんが、なぜ、独裁国家は本を燃やしてきたのでしょうか? 焚書隊の責任者、ビーティ署長はモンターグを諭してこう言っています。
「書物などというしろものがあると、となりの家に、装弾された銃があるみたいな気持ちにさせられる。そこで、焼き捨てることになるのだ。銃から弾をぬきとるんだ。考える人間なんか存在させてはならん。本を読む人間は、いつ、どのようなことを考えだすかわからんからだ。そんなやつらを、一分間も野放しにおくのは、危険きわまりないことじゃないか。」(宇野利康訳)
実際に本を読み、自分の目で世間を見、自分の頭で考えるようになったモンターグは、危険人物として社会を追われ、荒野を放浪しながら書物そのものの内容を記憶し、生ける「書物」になることを選択します。半世紀以上も前に書かれた本書が、いまなお輝いてみえるのは、書物の禁止や語彙の矮小化、映像メディア、スマートフォンの爆発的な普及が、考えることを難しくさせると警告を発しているからかもしれません。
■誰にも止めることのできない女王の読書『やんごとなき読者』
では、考えるためだけに、本は存在しているのでしょうか? 個人的には、違うと思っています。一言でいえば、本を読む動機はもっと単純で、何もかもを忘れるほどに面白いからではないでしょうか? それをまさしく作品として目の前に差し出してくれたのが、イギリスの劇作家にして俳優、アラン・ベネットが描いた小説『やんごとなき読者』です。
本書は、英国女王エリザベス二世がひょんなことから読書にのめりこみ、挙句の果てに読書のために公務がおろそかになってしまうという軽快な喜劇作品です。王室周辺の執事たちは、女王から読書を遠ざけようと、クッションの後ろに隠していたアニタ・ブルックナーの小説を爆破したり、旅行先におくった本を行方不明にしたり、何を読めばいいかを助言していた職員を配置換えしたりと、あらゆる手立てを尽くしますが、女王を止めることはできません。
「あの年でなぜいまさら? とまわりは思った。だが女王にとってはこれほど真剣なことはなく、一部の作家が書かずにいられないと感じるように、本を読まずにいられなかった。作家たちが書くために選ばれるように、彼女は老境に入ってから読むために選ばれたのだと感じた。」
女王にとって文学は、ひとつの共和国であり、「本は想像力の起爆装置」。ためらいがちにはじめた読書が、次第に読みながらメモをとるようになり、最終的には自分の考えを書きとめるように進化していきます。本に導かれるように女王が一冊の本から別の本へと手をのばし、次々に目の前に新しい世界の扉が開かれていくのは感動的です。
ラストシーンも圧巻で、読みなおす度に驚いてしまうのが恥ずかしいのですが、何度読んでも幸せになれる本です。
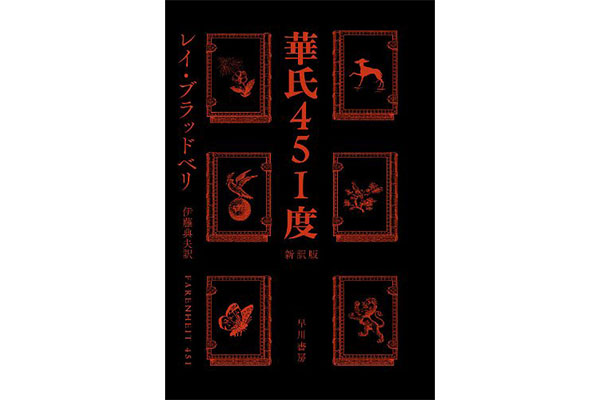
『華氏451度』ハヤカワ文庫
レイ・ブラッドベリ /著 伊藤典夫 /訳

『やんごとなき読者』白水社
アラン ベネット/著 市川 恵里/訳

