2021/05/14
長江貴士 元書店員
『錯覚の科学』文藝春秋
クリストファー・チャブリス、ダニエル・シモンズ/著 木村博江/翻訳
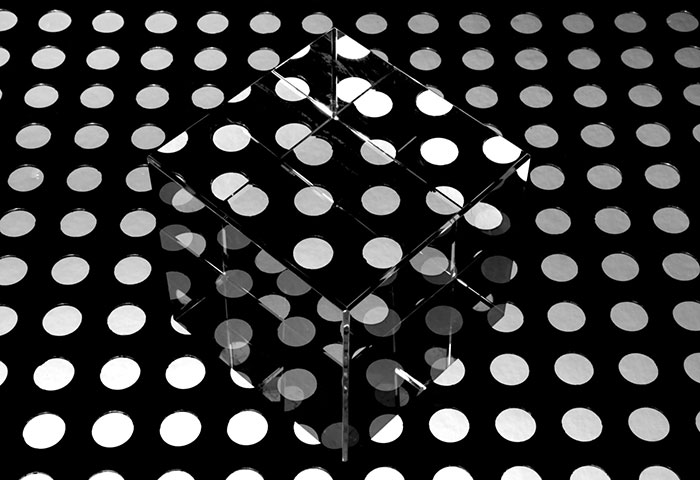
本書の著者二人は、心理学の世界に衝撃を与えたとある実験を行い一躍有名になった。この実験はその後教科書にも載り、類似の実験が様々に行われ、僕らが日常的に様々な事柄を「錯覚」しているという事実を突きつける。
その実験は、以下のyoutubeで実際に体感することが可能だ。
字幕が英語なので先に説明をしておこう。リンク先に飛ぶと、6人の女性が2つのバスケットボールを使ってパス回しをしている映像が流れる。3人は黒いTシャツを、そして残りの3人は白いTシャツを着ている。映像をよく見て、白いTシャツを着た3人のパス回しの回数を正確にカウントするだけでいい。
この映像を見た全員が衝撃を受けるわけではないが、どれだけ追試を行ってみても、半数近くの人は著者らの意図通りの反応を見せるという。僕も、最初に見た時は、あまりの衝撃にひっくり返るほどだった。
本書は「錯覚」についての本である。「錯覚」というと真っ先に思い浮かぶのは、錯視図形ではないかと思う。同じ大きさなのに違う大きさに見えたり、静止画なのに動いているように見えるというようなものだ。
その程度の「錯覚」であれば、面白いね!というある種の娯楽であり、日常生活に大きな支障を来すことはない。しかし本書では、様々な実例を取り上げながら、人間がどうしても避けられない「錯覚」が、トラブルや事故に繋がり得る、ということが示されていく。
僕たちは、自分が見たもの・聞いたもの・覚えたことに割と信頼をおいている。まあそれはそうだろう。あの時あれを見た、これを聞いた、というのは、自分の感覚としては絶対と言えるようなものだろうし、なかなかそれを疑う機会は少ない。
しかし本書を読めば理解できるが、それらを全面的に信用するわけにはいかない。人間の知覚や記憶は、あまりにも曖昧で信頼がおけないものなのだ。これは、「曖昧にしか覚えられないから信頼できない」という意味ではない。自分がはっきり記憶していると信じていることでも、事実とはズレるのだ。
その印象的な実例を紹介しよう。アメリカで輝かしい経歴を持つバスケットボールのコーチが選手から訴えられた。その選手はコーチに首を締められたと主張し、その時の様子を事細かに語ったのだ。しかし、その場にいた選手たちは、コーチが首を締めたなどという事実はなかった、と証言したのだ。数年後、その時の状況を写したビデオが偶然発見された。そして、首を締められたと主張していた選手の記憶が誤りであるということが判明したのだ。しかしその選手は最後まで、自分の記憶ではコーチから首を締められたというのは間違いない、と言い張ったという。
もちろんその選手が嘘をついている可能性もある。しかし、コーチと選手二人きりの状況だったのならともかく、その場には他にも多くの選手がいた。その状況で、虚偽の主張を続けることに意味があるだろうか。もし彼が嘘をついていないとすれば、彼の脳内では、実際には起こらなかったはずの出来事の記憶が作り出された、ということになる。
こういうことは、もっと日常的なレベルでも起こる。例えば、こんな実験が知られている。被験者たちは、ある研究室に集められる。そしてその部屋に30秒間いた後、別の部屋に移され、そこで「研究室には何がありましたか?」と唐突に質問される。すると被験者たちは、実際には研究室に存在しなかった「本」や「キャビネット」など、「研究室にありそうなもの」があったということを「思い出した」というのだ。
人間の記憶というのはこのように容易に改ざんされてしまう。何故なら脳は、実際に見たこと・聞いたことではなく、予期するものを記憶することが多いからだという。「こうなのではないか?」という予想の方が、記憶に定着しやすいというのだ。
またこんな実験も行われている。アメリカで、「9.11のテロの際、あなたは何をしていましたか?」と質問をするというものだ。印象的な出来事が起こった時の記憶は、他の記憶よりも鮮明であり、これは「フラッシュバルブ記憶」と呼ばれている。さて、9.11のテロ直後にその質問をし、答えを記録していた研究者たちは、数年後同じ質問を同じ被験者にした。すると、記憶が食い違っている人が多かったという。しかし被験者の多くは、研究者が記録した内容よりも、自分が今記憶していることの方が正しい、と感じていたという。
ここでは記憶の話にだけ触れたが、本書では他にも様々な「錯覚」が取り上げられている。知識や自信があることが判断などにマイナスに働いたり、物事の原因を認識し間違えたり、注意を向けていたはずなのに見落としたりと、実際の実例や症例を取り上げながら、人間の知覚の限界を様々に描き出していく。
今後益々社会では、人工知能が様々な場面で組み込まれていくことだろう。それが良いことなのかどうかは色んな判断があるだろうが、その変化は避けようがないことだろうと思う。例えば、自動車の自動運転技術などは、事故を大幅に減らすことだろう。知覚や記憶に欠陥のある人間に任せるより、遥かに安全だと言える。
しかしそういう社会になるということは、益々人間の能力が退化していくことに繋がっていくことにもなるだろう。運転中に周囲に向けていた注意を、もうしなくていいということになれば、使われなくなるその部分は少しずつ衰えていくだろうし、それは運転に限らずあらゆる場面に及ぶだろう。そうなれば益々人間は、劣った知覚の中で生きていかなければならないということになるかもしれない。
そうなる前に僕たちは、人間の知覚はどこに限界があり、人間は原理的にどういうミスをする可能性があるのかについて、きちんと理解しておく必要があるのではないかと思う。その認識のために、本書は最良の一冊と言えるだろう。
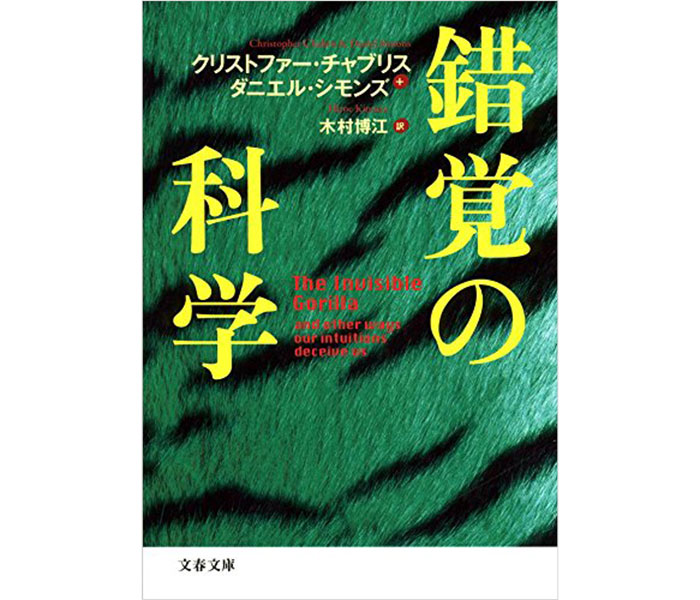
『錯覚の科学』文藝春秋
クリストファー・チャブリス、ダニエル・シモンズ/著 木村博江/翻訳

