2021/05/12
大平一枝 文筆家
『暮らしの哲学』/毎日新聞社
池田晶子/著

なぜもっと早く読まなかったかと悔やみに悔いた。こんなわかりやすくて、一言一句が胸に染み込むように爽快で、あたたかくてせつない哲学書をほかに知らない。そんなふうに言ったら著者の池田晶子さんはきっぱり否定するだろう。「これは季節や人生の機微について思索した哲学エッセイよ。哲学書を記したかったのではありません」
お会いしたことはもちろん一度もない。だが、本書を読むと、きっとこんなふうにさばさばずばりと、気負いのない言葉でおっしゃるんじゃないかと思わず想像してしまう。
本書は、『サンデー毎日』に2006年4月16日号からちょうど1年間連載したエッセイをまとめたものである。哲学者であり文筆家の池田晶子さんは、2007年2月末に46歳で病気で早逝。4ヶ月後に刊行された。
私は長い間、この人の書を避けてきた。『14歳からの哲学』という40万部超のベストセラーに、メジャーというだけで毛嫌いしてしまったのと、ずば抜けて美しい人という天が与えた二物が羨ましすぎたのかもしれない。それと、あまりに子育てと仕事にいっぱいいっぱいで、哲学に興味が向かなかった。限られた空き時間に、新しい世界を開拓する心の余裕がなく、日々が指の隙間からこぼれ落ちるようにするすると流れていってしまった。
ところが、子育てが一段落した今、どんなきっかけか買って読み始めたら、あっというまに魂を持っていかれた。『むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、』と綴った井上ひさしの名言を、哲学というフィールドで完璧に体現していた。
なるほど、だからあんなにも世の中に受け入れられ、今も読み継がれているのかと(池田さんの本は絶版が少ない)、素直に脱帽した。そして謝りたくなった。美人だからなんていう歪んだ理由で毛嫌いしてごめんなさい。
清々しさと、わずかな切なさと
本書に、『「情報弱者」にも言わせてほしい』という見出しのエッセイがある。
しかし「将来」なんてものは、よく考えると、どこにも存在していない。遠い将来であれ、近い将来であれ、それはあくまでも現在の自分の観念としてしか存在していないものだから、観念として予想される将来が現在となった時、じつはその人は存在していないのかもしれないのです。それなら何のために、現在を節約して、将来に貯蓄なんかしておいたのでしょうか
健康で仕事がうまく行っている時には、そのことで自分は幸福なのだと錯覚しがちですが、病気になったり危機に際したときに、そのような幸福の危うさに、初めて気がつくことになる。現在幸福である以外に、幸福であることはあり得ない (『暮らしの哲学』 p124)
コンピュータ社会の“時間を短縮することは便利だ”という思想に対して、真っ向から反論しての記述だ。
行間から、今ここに生きていること、現在を存分に味わいなさいというメッセージが伝わる。そう自覚したとき、“現在”というものは、「計り知れない深さと広がり」を持つと。
生きているとはどういうことか。暮らすとはどういうことか。もっといえば生ききるとはどういうことか。池田さんは差し出す回答は、いつも本質をついていて端的だ。平易な言葉で読み手の心に寄り添い、しかし世の中のだれにもなにごとにも媚びずに清々しく、そして少し切ない。
書くだけ書いて突然天に旅立ってしまったから、切ないんだろうか。
本書は、春夏秋冬の順に綴られている。とりわけ「初夏」がいい。
満開の桜は、過ぎ去って還らないもの、失われて戻らないものを思わせる。去年は一緒に見て笑った人がいなくなっても変わらず満開になる姿に、人は喪失や不在の感覚を呼び覚まされる。だから鮮やかで美しいけれど心に痛い。
いっぽう初夏の若葉から新緑、そして万緑に移り変わる季節は、燃え上がる生命の力を感じさせる。人は桜のように過去を振り返ったりせず、木々を芽吹かしめる力に励まされ、勇気づけられ心浮き立つ。
だから、『5月。世界は青年だ。』と池田さんは書く。
なんと力強く爽快なフレーズだろう。だが、彼女がこれを書いた時どう病と付き合っていたかわからないが、いま在ることの幸福を繰り返し説いた人の5月の形容には、やはりどこかわずかな切なさが宿っているように私には映る。
みな、死に向かって生きている
わたくごとで恐縮だが、去年のコロナ禍に、詩人の長田弘にはまり古本を買い集めてはくり返し読んだ。なぜあそこまで惹かれたかというと、長田さんが、見過ごしがちな日々のささやかな幸福を見つける天才だったからだ。路傍の花。時とともに形を変える雲。葉がすれの音。コロナなど知る由もない20年も前に書かれた詩のひとつひとつが沁みた。世の中は大変なことになっているけれど、私達が生きる世界は、視点を変えたらこんなにも美しい。もう少し我慢をして頑張ってみようじゃないかと、心の小さなつっかえ棒になった。
今年のコロナ禍は池田晶子に支えてもらっている。14年前の本書には「平穏な日常というのは、平穏でない日常があるからこそ平穏である。」という一節がある。
誰もがそうであるように、コロナは平穏の日常、当たり前の尊さを私たちに思い起こさせた。池田さんは哲学者の視点から長田さんのように、私たちがありがたく思っている日常のもっと足元の小さな移ろいに目を向け、耳を傾けている。
たとえば夏の終り、日が暮れるのが早くなってきた頃、ジージーミンミンと命の盛りとばかりに鳴いていたセミがピタリと鳴き終わる瞬間があるという。そして、コオロギや松虫など地面の住民たちの涼やかな声に移行するこの時期この時刻があると。
「夜気が肌に滲みてくるように」、「心に秘めやかに沁み込んでくる」(p131)虫の音(ね)を聴きながら、彼女は、“私とはなにものか”を思索する。虫の音は、私のどこで鳴っているのか。耳か。頭の中か。聴くという経験は、どこで誰に生じているのか。夢中で聴き入っているとき、「私が聴いている」とは言わない。ただ虫の音が存在する。だから彼女はこう結ぶ。
世界はあまねく音楽である。
また、すべての人の死因は「生まれたこと」だと綴る。みな打ち揃って死へ向かっている。季節にめぐりがあるように、始まりには終わりがある。春が始まりで、植物が枯れ衰えていく秋が終わりだ。だが、土が冷たく凍え、万物がそれぞれ自分の内に引きこもる冬は、じつは地中で命を暖め、春をはらんでいる。ここに「永遠」がある。
しっかり「今」を生きながら、生から永遠を感受せよ。
私はそんなふうに彼女の遺言を解釈した。そして文末の1行こそ珠玉だ。
人は「みんな」旅人なのであります。
ああそうだ。暮らしながら小さく抱いていた人生の不思議を、池田さんはすべて自分の言葉でデザインし、解き明かしている。
私たちは終わりに向かって生きているけれど、今この時を愛し、自然の営みがもたらすささやかで壮大な喜びを享受しながら暮らしたら、日々は思うほど悪くない。ウイルスとの戦いのゴールが見えないこんな毎日でも、生きることは奇跡みたいに尊いのだと気づかされる。するするこぼれ落ちる日常にこそ生きる意味があり、自己が存る。
これが哲学ってやつか。
我慢が強いられ、働き方や暮らし方、生き方など自分の内側に目がいきやすいコロナ禍。万緑輝く5月に、池田晶子が遺した言葉はきっと全身に沁み渡るはずだ。
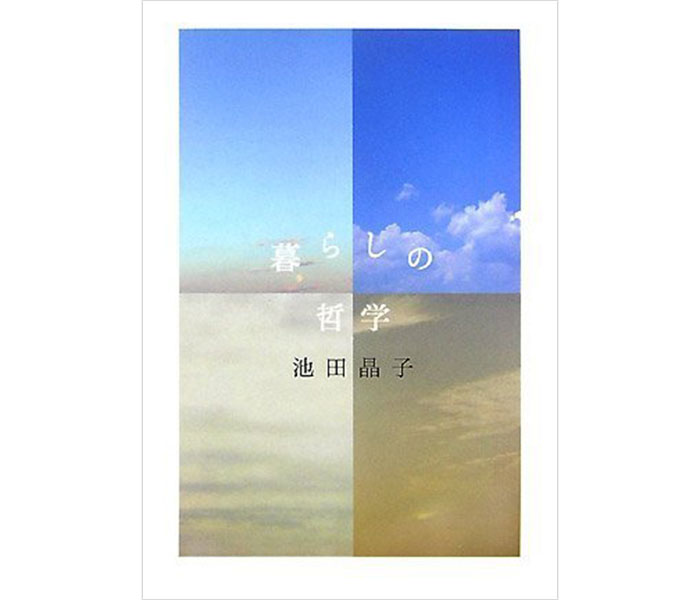
『暮らしの哲学』/毎日新聞社
池田晶子/著

