2021/10/28
馬場紀衣 文筆家・ライター
『身体の中世』ちくま学芸文庫
池上俊一/著

中世の文献や図像にはおおくの身体的、感情表現がちりばめられている。豊富な素材は、当時の社会性を解き明かす貴重な資料だ。生身の人間の「からだ」と「こころ」からヨーロッパ中世を見直した本書は、謎に包まれた中世ヨーロッパの人間観の奥深くまでもぐり込んだ一冊。
興味深いのは、中世人は現代の私たちのような羞恥心をもっていなかったということ。貴婦人は騎士にかしずかれながら入浴していたし、若い女性たちはバラの花びらをふりかけてもらっても動じたりしなかった。あまり裕福でない人たちは老若男女、みんな裸で一つのベッドに横たわって眠り、施療院のベッドもそんなありさまだったという。
著者によれば中世における「羞じらい」とは行為や意志、運動と結びついたものだったという。つまり、他者にあられもない格好を目撃されることはかならずしも「羞じらい」と結びつかなかったのだ。もちろん、中世においても性を意識されたときの裸体は羞恥の対象になった。それでも日常生活のおおくの場面では、おおらかに裸体をさらす状況のほうが多かったようだ。
「ヨーロッパ中世においては、裸体自体はなんら淫らではない。それは、見せつけたり見せつけられたりしてその上を意味ありげな視線がなぞるとき、初めて淫猥の情をかき立てる。その視線にたいする反応が恥を作るのである。」
当時、肉体は脆さ(罪になびきやすい)のシンボルであり、誘惑・苦悩・死の宿る場所でもあった。たとえば姦通を犯した男女は、罪の由来した器官、つまり性器を紐で結びつけて民衆のなかを吹き鳴らしたラッパに先導されながらパレードする罰が与えられた。裸体に与えられる屈辱は、宗教と結びついた鞭打ちなどの苦行にも見ることができる。
「中世のからだは、内と外との、かならずしも単純ではない関係(中略)に巻き込まれており、さらに、からだの部分、四肢や器官は、全体としてのからだの一部としてだけではなく、それぞれ独自に、あるいは勝手に、自然と超自然との橋渡しをしたのであった。」
ひとことで身体といっても、その意味するところは多様だ。ヨーロッパ中世では身体の各部位にさまざまなメタファーが盛りこまれていた。たとえば「手」の高度化された身振りは魔術的・聖なる力を伝える媒体とされていたし、「足」の大きな女性は多産だと考えていた。「頭」は身体の中枢としてもっとも高貴で天にも対応する場所だった。「頭」はまた、生命力が宿っていると信じられていた。中世では「髭」にすら迷信がある。身体の表層だけでなく、その奥の「血」と「骨」にも人びとは生と死のイメージを抱いていた。
まさに中世人の身体は「メタファーとシンボルの劇場」だったわけだ。本書では、四肢や器官など生まれながらにあらかじめ所有している部分のほかに声や表情、身振りなどの身体コミュニケーションについても取りあげられている。
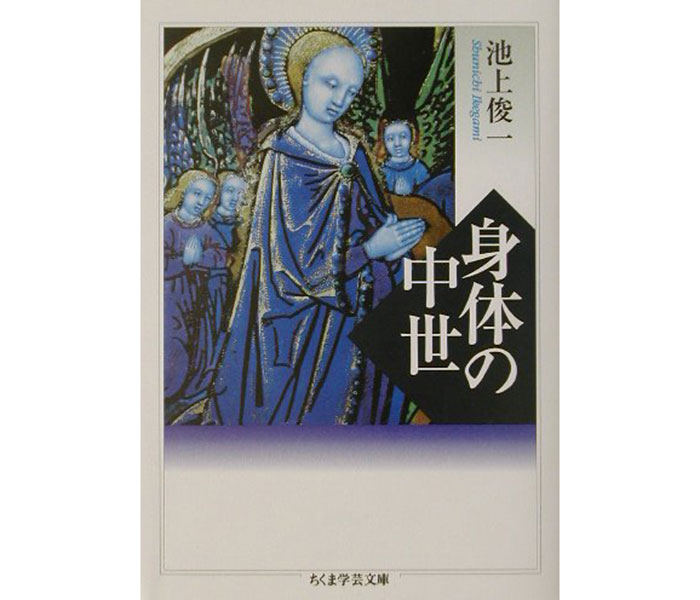
『身体の中世』ちくま学芸文庫
池上俊一/著

