2018/08/17
友清哲 編集者・ライター
『怪物』KADOKAWA
中村航、井上尚弥/著
意外に思う人もいるかもしれないが、率直に言ってボクシングはマイナー競技の域を出ていない。
もちろん黄金期とされる時代はあったけれど、近年はたまに社会に向けて盛大に話題を撒き散らしたかと思えば、醜聞の類いばかり。どれほど素晴らしい選手が現れ、どれほどの快挙を成し遂げようとも、そのニュースがちゃんと届くのは、せいぜいライトなスポーツファン止まり。これはもう、僕自身が四半世紀以上のボクシング歴を持つ身ゆえ、ずっと抱え続けてきた諦念のようなものである(実際、キックや総合格闘家と混同せずに、ボクシングの現役チャンピオンを正確に言える人って、ごく僅かですよね?)。
それでも、やや地味なポストに甘んじながらも、脈々と伝統を育んできた日本のボクシング界。故・白井義男が1952年に日本人初の世界チャンピオンとなって以来、今日までに90人もの世界チャンピオンを排出してきたのだから、これは立派なものだろう。新聞の扱いを見ても、日本タイトルマッチ以上の試合は、スポーツ紙だけでなく一般紙にもちゃんと結果が掲載される。これはプロレスやキックボクシングにはない待遇だ。
だからこそ、残念でならないのである。今この時代に登場した「モンスター」こと井上尚弥の凄さが、十分に周知されていない現実が。井上の名や顔を記憶する人は少なくないかもしれないが、彼がこの長い日本ボクシング史において、いかに不世出の傑物であるかを理解せずにいるのは、非常にもったいないことだ。

高校時代に史上初のアマチュア7冠を達成し、鳴り物入りでプロデビューした井上は、4戦目で日本タイトルを、5戦目で東洋太平洋タイトルを、そして6戦目であっさり世界タイトルを獲得(いずれも最速、あるいは最速タイ記録)。要は世界を穫れるかどうかというレベルなど、はるかに凌駕する存在だった彼は、デビューからの5年半ですでに3階級制覇を成し遂げている。
げに恐ろしきは、そんな井上がまだ25歳ということだ。参考までに言えば、カエル跳びで有名な輪島功一が、ようやくデビューしたのが25歳なのである。一体、この若者の行く先には、どれほど洋々とした未来が開けているのか。
しかし、スポーツ紙や専門誌がどれほどその逸材ぶりを喧伝しても、一般には届きにくいのがマイナー競技の悲しいところ。前置きが長くなってしまったが、マニア層がそんなもどかしさを燻らせていたところに登場したのが、本書『怪物』だった。
アスリートがキャリアの最中に自伝を著すのは珍しいことではないが、本書がユニークなのは、作家・中村航と井上、2人の“共著”という体裁を採っている点だ。
本書はあくまで中村航によるノンフィクション作品でありながら、モチーフである井上尚弥の名を筆名に並び立たせている。その意図は不明だが、芥川賞候補にもなった純文学の気鋭と、今をときめくモンスターの揃い踏みで、単なる評伝以上の世界が生まれるのではないかと、期待してしまったのは事実だ。
果たして、純文学作家は僕らが愛して止まないボクシングを、そこらのゴーストライター(あ、僕のことです)ではとうてい及ばない美文で表現してくれた。たとえば、個人的に印象深いのは次のシーン。
「……お父さん、僕にもボクシング教えて」
真吾は驚きとともに尚弥を見やった。
意志と勇気――。そこには確かに六歳男子の、小さな意志がある。
みぞおちの辺りに生まれた何かが、やがて真吾の胸を熱くしていった。かがみ込んで目を突き合わせ、真吾は尚弥に語りかけた。
「教えてもいいけど、本当にできるのか? ナオ、ボクシングは甘くないんだぞ」
これは幼き日の井上が、トレーナーでもある父に初めてボクシングをやる意志を初めて打ち明けた時のこと。後に世界を席巻する親子鷹の挑戦が、まさにスタートを切った瞬間である。

本書『怪物』には、そんな怪物ボクサーの来歴と背景が、時にドラマティックに、時に扇状的に綴られている。早熟な天才への周囲の反応。強すぎるがゆえの対戦相手探しの苦労。記録づくしのプロキャリア。
おそらく筆者の中村航は、取材や執筆の過程において、なぜこれほどまでの怪物が生まれ得たのか、その秘密に迫ろうと試みたに違いない。しかし井上の強さは今なお、掘っても掘っても底を見せないため、取材者として幸せな徒労感を味わったのではないか。
去る5月。10年ものあいだ不敗を誇った英国人王者を、初回で仕留めて3つ目のタイトルを手にした井上は、そのリング上から高らかにこう言ったものである。――怪物ぶりはアピールできたのではないかと思います、と。
正直に明かせば、1人の物書きとして嫉妬する思いもある。僕自身もインタビュー対象として、井上と何度か対峙してきたが、せっかく同じ時代に活動していながら、彼にとことん張り付き、話を聞き、得たものを存分に表現する機会には到達できずにいるからだ。井上尚弥とは、そう思わせるほどの存在なのである。
本書を介して井上のこれまでの足跡を共有することは、これから先の感動を享受するための通過儀礼にもなるはずだ。
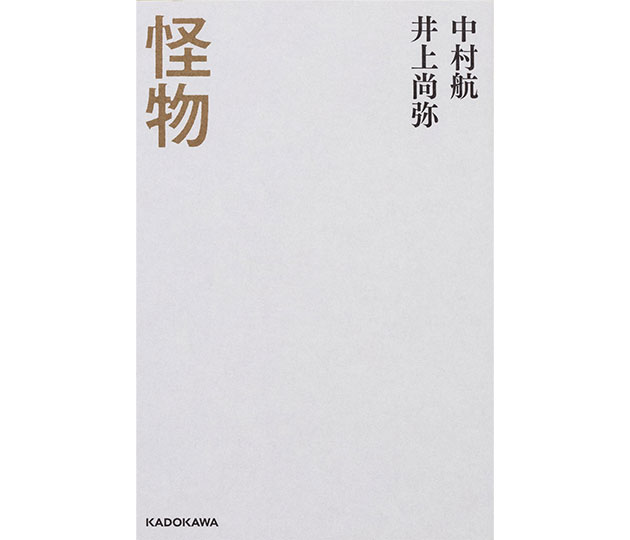
『怪物』KADOKAWA
中村航、井上尚弥/著

