akane
2019/04/05
akane
2019/04/05
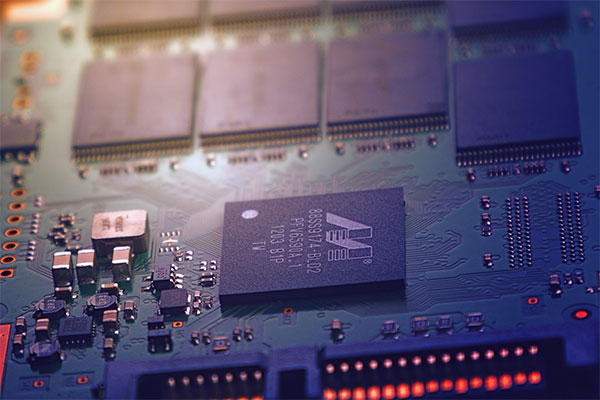
前回のコラムでは、イノベーションというと、その担い手としてスタートアップ企業を連想する傾向が強いと思われますが、必ずしもそうではないことに触れました。
既存企業は改良・改善型のイノベーションには強いが、不連続的なイノベーションには弱いという通説があります。
しかし、『日本のものづくりを支えた ファナックとインテルの戦略』で描いた革新史は、既存企業もまた、不連続的で革新的なイノベーションの担い手にも十分になれるはずだということを、改めて想起させてくれるのです。
日本を代表するトヨタ自動車もまた、豊田自動織機の社内部門として始まったのであって、決してスタートアップ企業として始まったわけではないということを忘れてはなりません。
ただし、そこには「優れたマネジメントがあれば」という前提条件が付くことはいうまでもない、ということについても前回のコラムで触れました。
今回のコラムでは、『日本のものづくりを支えた ファナックとインテルの戦略』で描いたファナックとインテルの経営を振り返りながら、新規事業を生み出し育成する2つのポイントを指摘したいと思います。
まず重要なのは、新しい技術・製品・事業の領域をどのようにして探索するのかということです。インテルでは、MPUの選択はボトムアップ的に現場主導で行われました。経営のトップがMPUという方向性を最初から明示したわけではありません。それどころか、IBMのパソコンに基幹部品として採用されるまで、経営のトップはMPUの意味と価値を計りかねて逡巡していたのです。この場合、経営のトップの功績は、現場から上がってきたその着想を評価し、IBMのパソコンに採用されるまでの10年以上、撤退せずに投資を継続したという点にあるといえるでしょう。
他方ファナックの場合、探索はトップダウンで始まったという点でインテルとはかなり異なります。CTOだった尾見がコントロール分野という広い探索領域をトップダウン的に指示し、その範囲内で稲葉がNC(数値制御)分野という領域に絞り込み、CTOはそれを評価し、了承したのです。そしてその後、CTOだった尾見は9年間に及んだ赤字事業を辛抱強く支援し続けたのです。
このように、新しい技術領域や製品領域の着想が、組織内の一体どこで生まれて誰から始まったのかについて、インテルとファナックでは組織内の出生地は異なっています。しかし、10年程度、トップが我慢強く支援を継続して、いわゆる「死の谷」を超えたという点では共通しています。
世の中を大きく変えた革新性の高いイノベーションの真価が広く認められるためには、それほどの忍耐の時間を必要とするということなのかもしれません。
最近は、新規事業を始めても3年程度で見通しが立たなければ撤退する企業が多いと聞きます。ルール化されているのかどうかは別にして、社内にそのような慣行がある場合が多いようです。
しかし、何年程度で撤退を決めるべきかについては、革新性の度合によって異なり、一律に決めることができる性質のものではありません。たかだが3年程度で撤退していれば、世界に大きな影響を与えるイノベーションは日本から生まれなくなってしまうかもしれないのです。
既存企業がイノベーションを遂行し育成するための重要なもう一つのポイントは、既存事業との関係性です。当時、インテルはDRAM、富士通は通信機という既存事業を営んで収益の柱としていました。既存事業は主力となる既存事業と既存顧客を持っているために、新規事業との分離や統合の度合いなど、距離感をどう設計するのかが重要な経営課題となります。
これについては、インテルもファナックも共通した枠組みで行われたことが見てとれます。
それは、既存事業とは明確に分離させたうえで、経営層が新規事業を直接統括するという枠組みです。
「分離する」という意味は、ただ単に組織的に別の部署にすればよいということではありません。技術や人などの経営資源、評価の基準、さらには組織文化まで違ったものにするという意味です。
既存事業の改良と新規事業の探索・育成は、異なる性質を持ったタスクです。
したがって、異なった能力を必要とします。
そのために、既存事業から切り離し、それに相応しい土壌に種を蒔かなければ、新規事業を育てることはできません。
そして、経営層がそれを守ってあげなければ、当面、利益を生み出さず金食い虫でしかない新規事業は、発言力と政治力の強い主力事業に侵食されてしまうのです。
インテルとファナックの革新史を俯瞰していえることは、新技術・新製品・新事業などの着想は、組織内のどこでどのような経緯で生まれるのかは企業によって異なるものの、着想の育て方には共通点があるということです。古くはブレーンストーミングから近年はデザイン思考まで、優れた着想を得るための手法が提案されてきました。
しかし、つまるところ、優れた着想は組織のマネジメントよりも個人の資質に負うところが大きいのではないでしょうか。
とするならば、よいアイデアが我が社に少ないことを嘆くよりも、はたして組織の中でよい育て方をしているのかどうかに注意を払うほうが建設的といえるのではないでしょうか。
つまり、革新的で斬新な着想の芽が、実は組織内の合意形成プロセスの見えないところで、密かにつぶされてしまっているのかもしれないのです。
※以上、『日本のものづくりを支えた ファナックとインテルの戦略』(柴田友厚著、光文社新書)から抜粋し、一部改変してお届けしました。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.