ryomiyagi
2022/09/27
ryomiyagi
2022/09/27
今や日本のアニメは世界を席巻している。話題作が新作を発表するたびに興行収入を更新し、作品のOPやEDを飾るテーマソングがビルボードを賑わすようになった。それもこれも、サブスクリプションによる楽曲や動画の配信サービスに負うところが大きい。かつて映画は、公開を待つかレンタル開始を待つしかなかったし、音楽は、メディアによる露出かCD化を待つ意外に方法が無かった。そしてそこには、言語の違いなど、日本国内で制作されるコンテンツが持つ致命的なマイナス要因が大きな壁となっていた。
昭和30年代生まれの私にとって、音楽と言えば洋楽だった。毎週土曜日に岩国基地から流れてくるFENのトップ40に噛りつき、邦楽とは異なるサウンドに耳を傾けたものだった。そして、国内のバンドやアーティストとアメリカやイギリス発のバンドサウンドの余りの違いに暗澹たる思いすら抱いたものだ。そんな当時、まことしやかに言われていたのが「日本語でロックはできない」だった。
それが今、アニメと一緒ではあるが日本人バンドの作ったサウンドが世界から絶賛されている。嬉しいとともに、誇らしい思いまでもが胸をよぎる。SNSやサブスクの功績こそ大なのだが、それにも増して日本人アーティストの進化が目覚しい。
そしてそこには、たくさんの先人がいたし、そんな先人たちのサウンド作りだけに留まらぬ様々なメディア展開があったことは間違いない。
今も忘れられない『イカすバンド天国』などがそうだろう。視聴者であるバンド好きたちは同番組を「イカ天」と呼び親しんだものだ。そんな伝説の番組を作っていた吉田建氏が本を出版したと聞いた。『平成とロックと吉田建の弁明』(光文社)がそれだ。さっそく、レジェンド・吉田氏の弁明とやらを聞いてみよう。
対談形式の本書には、もうお一方、今や伝説となった『シーマン~禁断のペット~』などを世に送り出したゲームクリエーターの斉藤由多加氏だ。どちらの方も、なかなかの難物である。
斉藤「『イカ天』の時代のバンドブームって、今はどこへいたんですかね?」
吉田「あれはねえ、バンドブームなんかじゃないんだよ」
斉藤「違うんですか?」
吉田「違う。あれはバンドブームではなくて、“アマチュアバンド”のブームだったのよ」
斉藤「あ、そういうことか。となるとアマチュアであることの何がウケたんですかね?」
吉田「それまでのプロがお金をじゃんじゃんかけて出してくる歌謡曲の黄金時代に対する、反動、かな」
斉藤「その反動というのは、今でいうと地上波テレビに対するユーチューバーアイドルみたいなものですか?」
吉田「そんなもんかもね。あのはさ、TBSの看板番組だった『ザ・ベストテン』の12年近い放映が終わったばかりだったのね。それも関係があると思う。言ってみればさ、プロの仕事人のヒットのテクニックに対するアンチテーゼというかね、音楽の原点回帰というか」
昭和30~80年代と、日本は歌謡曲全盛の時代が長く続いた。NHKはもとより、民放各局が歌番組を持ち、年端もいかぬ少女たちは、TVを前にコタツの上に立ち上がり、私もいつか……とアイドル歌手の振りを真似ては家族の笑いを誘ったものだ。そんな中、歌番組にこそ出てこないが、それでも若者たちの間で人気を博す、その後「邦楽ロック」と呼ばれる日本人バンドが幾つも誕生し活躍し始めていたように記憶している。が、しかし、当時の私は圧倒的な洋楽シンパで、たどたどしい譜割の邦楽ロックなるものに圧倒的な違和感しか感じていなかった。などと言うと身も蓋も無いが、それほどに、初期の日本人ロックバンドは、エレキサウンドに日本語を乗せることに苦労していた。
「ロックは英語でなければ歌えない」「ロックサウンドに日本語は乗せられない」そんな風に、ロックに憧れる若者たちは思い込んでいた。
斉藤「けど、ロックが日本に来てこれだけ時間が経過して、曲もたくさん出て、でもいまだにその宿(しゅくあ)から逃れることができない理由ってなんなんですかね?」
吉田「音楽業界の権益構造」
斉藤「権益? ロックって権益なんですか?」
吉田「音楽産業が、って意味。そこにロック人気が出てきて産業が巨大化した。ロック音楽ってのはさ、今でいうところの、配信から課金までの一気通貫のプラットフォームを実現したのよ、欧米の産業界が」(中略)
吉田「そう、で、その公用語が英語なわけ」
斉藤「そういうことか。」
吉田「だからさ、日本人は日本語と英語という比較でのみ捉えてしまっているけどさ、フランス語圏でも、ドイツ語圏でも、日本と似たような議論はあったと思うよ。発明した国が権益を取るだけのことですよ」
確かにそうなのかもしれない。譜割やサウンドのニュアンスに対して、自国語の歌詞を乗せることの違和感に悩んだのは、日本人だけではないのかもしれない。レイ・チャールズやチャック・ベリーのように言葉をサウンドに乗せるには、硬い響きを持つドイツ語はもちろんのこと、世界一美しい言語と言われるフランス語ですら違和感があったに違いない。
今からおよそ45年前。サザンオールスターズがデビューした時。ものすごい勢いでヒットチャートを駆け上がる、彼らのデビュー曲『勝手にシンドバッド』を聞きながら、作詞家をめざす友人がため息をつきながら「こいつ(サザンオールスターズ)は天才だな。譜割の前後に言葉を乗せてる」と言ったのが忘れられない。当時、ものすごい勢いでヒットチャートを駆け上がるその曲には、軽快なテンポに乗せた早口言葉のような歌詞が踊っていた。それまでは、一つの音に一語しか乗せられなかった邦楽に対して、サザンは一音の前と後ろに言葉を乗せて歌っていたのだ。それだけで物語りはより深くなるし、グルーブは軽快になる。もしかすると、あの瞬間から、邦楽ロックの再生と巻き返しは始まったのかもしれない。
吉田「僕の中の劣等感の正体ってさ、自分が『普通の人』ってことだったんだろうな。それを指摘されたり、自分で気づいたりしたくなかったんだと思う。自分はアーティストなんだぞ、ってさ」
斉藤「ロックミュージシャンであることを否定していたのもそれですかね?」
吉田「そうだと思う」
斉藤「歌手のバックで、軍師官兵衛みたいに、コントロール塔になっている方が建さんには似合っている?」
吉田「うん、どうだろう。そうなんだろうね、きっと。由多加さ、表現者とはキャラが違う、でもそれを認めてさ、照れずに普通に生きていこう、それが吉田建なんだということが、今回の件ではっきりわかったんだな。お前にはそれを気づかせてもらった」
と、対談形式であるが故に、お二人の間で前後する葛藤と苦悩が、何度となく繰り返される。そして、著者であり邦楽レジェンドの吉田氏自身の懺悔にも似た告白までが記されていた。
日本ポップス界の重鎮、吉田建氏と、ゲームクリエーターの先駆けである斉藤由多加氏による共著は、全編対談と言う型破りな形をとった一冊だった。
そこには、日本のロックが生まれた瞬間から過渡期における苦悩や、全盛期を迎えたかに見える現代まで、日本のロックバンドの変遷がつまびらかに記されていた。
『平成とロックと吉田建の弁明』は、洋楽で育った「ロック大好きオヤジ」から、「ロックって何? Jポップ最強じゃん」と嘯く若者たちまで、音楽好きを自称するありとあらゆる方々に一読をお勧めしたい、そんな素敵な一冊だった。
文/森健次
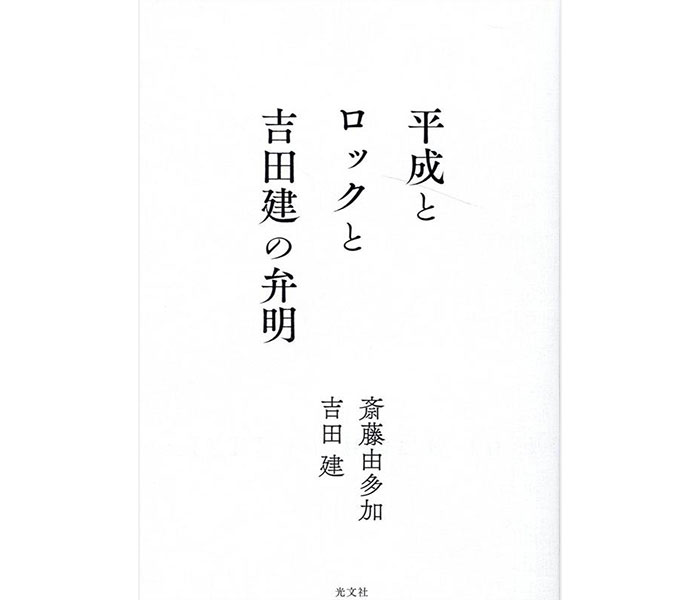
『平成とロックと吉田建の弁明』
吉田健、斎藤由多加/著
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.