ryomiyagi
2022/09/28
ryomiyagi
2022/09/28
先ごろ、20世紀のロックシーンを代表する、エルビスプレスリーの伝記映画『エルヴィス』が公開された。およそ2時間半に及ぶ作品で、キングオブロックと呼ばれた男が名曲の数々を口ずさみながら魅惑的なヴォーカルパフォーマンスを見せていた。この「白い肌をした黒人」と呼ばれた一人の男によって、20世紀後半のミュージックシーンは一挙に開拓されたと言っても過言ではないだろう。しかし、そんな、後にロックの王様と呼ばれる男は、その余りに熱狂的な支持が故に、白人社会と黒人社会を分断しておこうとする政治的イデオロギーにより様々な妨害を受けることとなる。それでもなお、若者たちの新しい音楽を希求する思いは過熱し続けた。そして、ビートルズやローリングストーンズなどが登場し、いよいよミュージックシーンはロックバンドを主体とするムーブメントを巻き起こしていく。
映画『エルヴィス』は、そんなロックの黎明期をなぞらえた面白い作品だった。そして、「果たして日本のロック黎明期とは?」と思い起こさせられた。そんなタイミングで、本書『平成とロックと吉田建の弁明』(光文社)を入手した。著者は、べーシストであると同時にプロデューサとしても日本の音楽界を牽引してきた吉田建氏と、『シーマン』など伝説的なゲームを世に送り出してきたゲームクリエーターの斉藤由多加氏。全編お二人の対談形式という異色な一冊だが、日本にロックが生まれた瞬間から現在に至る業界事情を語るにはふさわしい著者であり対談ではないかと思い、急いでページをめくった。
斉藤「音楽の仕組みそのものを発明したのは、紀元前のギリシャのピタゴラスたち、って知ってます?」
吉田「たぶん知らない」(中略)
斉藤「例えばですが、ここに1メートルのギターの弦があるとします。これを指で弾いた時の音を『ド』とすると、この弦の長さの2分の1である50センチのところで押さえた時に出る音はなんでしょう?」
吉田「『ド』だよ。1オクターブ高いド」
斉藤「そうです。正解!」
吉田「それが、面白いのか?」
斉藤「知らない人多いですよ」
吉田「知ったところで何が面白いわけ?」
斉藤「音は、数字が母だ、という事実。」
吉田「君の言ってることがよくわからないんだけど、数字から生まれると何がどう面白いの?」
斉藤「すべての音が12の音種で記号化されたから」
吉田「12のどこがどう面白いの?」
斉藤「じゃなくて音が、数字のように人間の道具になったからですよ。」
音楽プロデューサーとゲームクリエーターによる音楽談義という試みが意図する化学変化を垣間見るような一説だ。それにしても、私たちが理解し享受している音楽と言う得がたいエンターテインメントの生みの親が、まさかピタゴラスだったとは、この一事をもっても本書を手にしたかいがあると言うものだ。
吉田「小さなグループだからメンバーの個性も見えてくる。それがロックバンドだよ。少人数でできるし、AやEといった簡単なコードで演奏できるとなった途端、音符なんか読めない、いわゆる劣等生たちがドカドカッと入ってきたんだよね。そこで、大きく音楽のDNAが書き換えられたと思うんだ。専門知識がない一般人に普及すると文化はここまで発展するのか、ということをロック音楽は見せつけたと思うよ」
斉藤「なんかパソコンが生まれた話に似てますね」
吉田「ん? どこが?」
斉藤「反体制なところが」
吉田「パソコンって反体制なの?」
斉藤「ええ。昔はコンピューターは国防省とか大企業しか使用できない高価なものだったんですが、それに反発した、アメリカ西海岸のハッカーたち……ま、思想的には反戦のヒッピーですね……が手作りのパソコンを売り出した」
吉田「あ、アップルもヒッピーが作ったって話?」
ロックが生まれた事情とパソコンが生まれた事情が、かくも近しい色合いを持つとは、初耳でもあるし頷けるとても面白い見解だ。また化学変化を起こしている。
洋楽一辺倒で育った昭和30年代生まれの私の周囲には、バンド野郎やギター少年がたくさんいた。そんな中でも、仲間内でも「上手い!」と評判の一人が、ある日通っていた高校を退学し「○○ちゃん、ちょっと行って来る」と唐突な一言を残してアメリカへ行ってしまった。そして彼は、現地の高校を卒業しバークレー音楽学院へと進む。そして20代半ばにして帰国した彼は、めでたく大手レコードメーカーにディレクターとして採用された。そんな嬉しい知らせを助手席で語る彼に、配属先を尋ねると「邦楽」と一言。あれほどのロック好きで、ポップス・ロック部門で最高峰とされる同学院まで出た彼がどうして邦楽なのかと聞くと、「○○ちゃん、今は邦楽がゴールドラッシュなのよ」と答えたのを今も鮮明に覚えている。
確かに彼の言うとおり、80年代に入った国内の音楽業界は、それまでの歌謡曲一辺倒からニューウエーブだのクロスオーバーだのと、ロックテイストの強いアーティストが活躍していたが、そんな風に彼は戦略の様なものを立てていたに違いない。
吉田「むしろアナログ音楽の魅力と言えば、レコードジャケットだな。由多加はアナログレコードのコレクションとかは持っていないの?」
斉藤「今も少しは残してますよ」
吉田「あの時代は、ジャケットという名のアートが本当に美しかったんだけどね。今は音楽もダウンロードして聞く時代だから、ビジュアルの要素がないんだよな。僕らの時代は、音楽はジャケットという名の巨大なアート作品としても記憶されるわけ。でも、今のiPhoneとかのダウンロードだと、手触り感とかビジュアルがないじゃん? つまんないよね」
その通りだ。あのLP盤のレコードジャケットは、それだけを眺めていられる一つの作品だった。という今は、音源と同時に動画が配信されたりするのだが、この動画とレコードジャケットは全くの別物のように思う。
と同時に、本書が語る「アナログからデジタル」へと音楽事情が変遷するとともに、それまで音楽ビジネスは勿論のこと、バンド活動にまで大きな影響力を持っていたレコード業界が一気に斜陽化し始めたように記憶している。やがて、音楽好きの間では「もうパッケージビジネスは終わりだ」などと言われ始めたものだ。音源を録音し、これをパッケージして売り出す。これがレコード会社のビジネスの主体である。それが、本書で著者が語るようにダウンロードして完結となると、それ以前のビジネスが通用しなくなる。
2000年代の音楽の業界事情は、この大惨事に対する悲喜こもごもだった。
そんな思い返すことの徒然を、本書は鮮やかに彩ってくれる。
本書『平成とロックと吉田建の弁明』(光文社)は、和製ロックの黎明期を知るレジェンド・べーシスト吉田建と、レジェンド・ゲームクリエーター斉藤由多加が何年越しかで語り継いだ昭和から平成の邦楽史をまとめた貴重な一冊だった。また本編には、そんな吉田建氏だからこそ語れる、多くのレジェンド・ロッカーたちとのやり取りが鮮やかに語られており、その一つをとっても十分に楽しませてくれる。
文/森健次
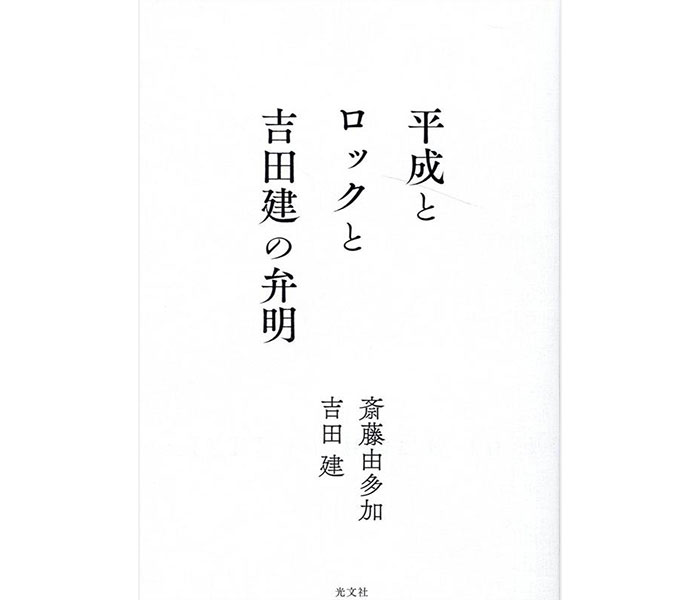
『平成とロックと吉田建の弁明』
吉田健、斎藤由多加/著
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.