2018/12/20
大平一枝 文筆家
『吉原幸子詩集』思潮社
吉原幸子/著

そのときどきで、胸に刺さる詩が変わる
スラリとした細身で、とびきり美人。東大卒業後女優を経て詩を本格的に書き始める。スペックがいちいち刺激的な吉原幸子は、昭和40年代から平成の始めまで、女性のための詩作表現に尽力した詩人である。結婚歴はあるが、レズビアンでもある(明言はしていないが作品で示唆している)。
2年前、朗らかな人柄の料理家に取材したら、吉原幸子の名が出て、興味を持った。読めば読むほど、彼女の紡ぐ言葉にしびれた。若い頃この詩に助けられたという料理家の言葉が胸にストンと落ちた。
物書きの容姿から説明するのもどうかと思うが、こんなかっこいい詩人が、昭和の時代に活躍していたことを、どんなきっかけでもいいから知ってほしくて綴ってみた。
詩集の多くは古書店でしか手に入らないが、『吉原幸子全詩1~3』(思潮社)は2012年に刊行されている。『吉原幸子詩集』(1973年/同社)も、アマゾンほか多くの古書店で容易に手に入る。
強くて孤独で、勇ましくて繊細。吉原幸子の世界は、相反する多様な魅力が混じり合っていて、とても一言で表すのは難しい。同世代の茨木のり子とも工藤直子とも違う、独特の光と影が絶妙のバランスで同居する。だから、その時の自分の心の状態によって、胸に刺さる詩ががらりと変わる。
同じ“弱っている”ときでも、少々元気がないときは、ぽんと背中をおしてくれるような強くて優しい詩に。
ものすごく落ち込んでいるときは、絶望的に深い闇の底からじっと天上のかすかな光を見つめながら嘆く、哀しい詩に。
ぐぐぐ~っと言葉の海に引き寄せられ、気づいたら沖合にいて言葉の海に心地よく浸っているうちに、自然に傷が繕われている。
私はたくさん詩を読んでいないので、詩集とはこういうものなのか、それとも吉原幸子だけが為せる技なのかわからない。ただ、この本がそばにある。それだけで、いくらか強くなれる。それだけは間違いない。
ありふれた一瞬を、鮮やかに収納する魔法
「人が死ぬのに
空は あんなに美しくてもよかったのだらうか」(『空襲』)
言葉の刀でスーッと静かに、けれども鋭く世の中を斬る作品は、彼女の真骨頂で、高く評価されてきた。だが、私は、どこにでもある平凡でありふれた日常の一瞬を、見たこともないような言葉で鮮やかに描写する独特の表現力に、胸を掴まれる。それらに出会うたび、私はいつもいつも、はああともほおおともいえない変な声が漏れてしまうくらいだ。
どこかで 母のよびごゑがする
原っぱに
くつといっしょに かうもりと 夕やみと
駄菓子のやうに甘酸っぱい 淡い孤独が
落ちかかる 『かくれんぼ』
誰でも いちど 小さいのだった
わたしも いちど 小さいのだった
(略)
大きくなったからこそ わたしにわかるだいじがることさへ 要らなかった
子供であるのは ぜいたくな 哀しさなのに
その中にゐて 知らなかった 『1喪失ではなく』
花びらは どんなあじがするか
おさじは どんな重みがあるか
時計は どんな音がするか手をさしのべ
身をのり出して
むきたての世界を おまへは つかむ 『Jに』
上記2作は、『幼年連祷』という自費出版の処女作に収められていた。『Jに』は生まれたばかりのわが子が題材だ。
後年、女性の表現活動を支援し、激しい詩もたくさん発表しているが、私は彼女のやわらかでみずみずしい、なんていうことのない平凡な一瞬を切り取り、永遠の言葉で封じ込めた「幼年」がテーマの初期の詩に、強く惹かれる。
50年を経てなお、透明な水のように、心の細部までおいしくしみていく。詩に理屈など要らない。こんなおいしい水が湧き出る泉を、過去に置き去りにするのはもったいない。
疲れたときも、どんなときも、そばに置いておいたらきっとあなたを潤し、役に立つ。クールでビューティ、とびきりかっこいい人生の先輩からの贈り物である。

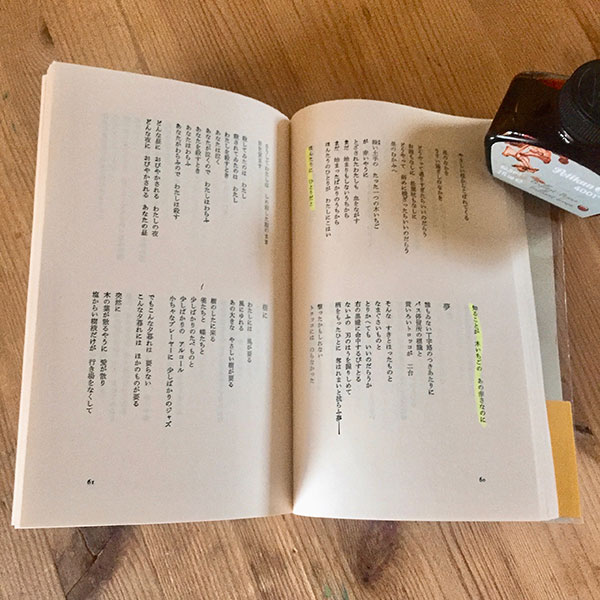
撮影/大平一枝

『吉原幸子詩集』思潮社
吉原幸子/著

