2019/10/18
田崎健太 ノンフィクション作家
『真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園』文藝春秋
三宅玲子/著

想像力とは本来無限であるはずだ。しかし、実際にはそれまでどんな人生を歩んできたのか、によってその人間の想像力は限定される。だからこそ、ぼくたちは人に会い、本を渉猟するのだ。
そんな当たり前のことを『真夜中の陽だまり』を読みながら思った。
これ博多にある夜間保育園――どろんこ園のルポルタージュである。
恥ずかしながら、この本でぼくは、夜間保育園、ベビーホテルについて初めて知った。
そして、そこで働いている多くの無名の人たちが必死で踏ん張っていることも。
彼ら、彼女たちの言葉には、ずっしりとした重みがある。
どろんこ園の保育士の須ヶ原は、自分がかつて働いていたベビーホテルについてこう語る。
「あの1年間で、悲惨な親子をたくさん見ました。思い出すと胸が苦しくなるので、ふだんは自分の中でふたをしているんです。だって、そういう人を支え続けるの、無理なんですよ。本当に苦しかった」
無表情で赤ん坊を連れてくると、無言で手渡し、南新地のソープランドに出勤する風俗嬢。とげとげしい態度で子どもを叱り、須ヶ原に攻撃的な視線を向けるキャバクラ嬢。心にふさぐものを溜め込んだ母親たちから受け取った子どもたちと須ヶ原の、長い夜が始まる。(中略)
深夜、酔っ払っておぼつかない足取りで迎えにくると、子どもを抱きかかえて、よろけながら帰っていく母。別の母は、朝方、風俗街から無表情で戻ってくる。ひと言も言葉を発しないまま、子どもを抱き取ると、須ヶ原に背を向けた
どろんこ園は親たちが、人生の〈負のループ〉から抜け出すための施設でもあるのだ。
どろんこ園は、九州大学の学生だった天久薫が、七三年に保育士である妻の真理と始めた夜間託児所が基になっている。このとき、天久は検察官を目指して司法試験の勉強をしていた。保育園の仕事に加えて、夜間に子どもを預かっていた真理に押し切られる形で、夜間託児所を始めたという。
夫が借金を残して蒸発した、あるいは夫の暴力から逃げてきた、といった女性たちと向き合ううちに天久は、この仕事に注力していくことになった。
天久は時に、自宅に子どもを連れて帰り、面倒を見ている。なぜそこまでするのか――彼がはっきりと語ることはないが、著者の三宅玲子は、総合失調症を抱えた父親、それを支えた母親を目の当たりにして、弱者の立場を強く意識するようになったのではないかと、推測している。
どろんこ園はいろいろな人間に支えられてきた。
例えば――。
夜間託児所から、キャナルシティ博多の中に入る認可保育園である、どろんこ園への脱皮を助けたのが“中洲のドン”と呼ばれた社会党市議の北岡幸太郎だった。北岡は終戦直後にキャバレーを経営しており、よるべのない女性たちの事情を熟知していた。
間接的ではあるが、ベビーホテルの劣悪な環境を取材したテレビディレクター、番組を観て規制に動いた政治家たちも、そこに含めていいだろう。
元々、著者の三宅が、どろんこ園を訪れたのは、過去に取材した建築家の設計だったからだ。天久、親そして子どもと知り合い、彼女はのめり込んで行く。母でもある三宅は“取材者”から踏み出し、子どもを自宅で一時預かったこともあった。
天久の誕生日、手紙を送ると深夜にメールが届いた。そこには新事業を始めると書かれていた。翌日、三宅は天久に電話を入れる。
新事業の対象が昼の子どもたちなのか、それとも夜の子どもたちなのか確認したかった。
「夜の子ですよ」
果たして天久はこう答えると、改まった口調でこう続けた。
「いいですか。ここははっきりしておきますがね」
一瞬、スマホを持つ手に力が入った。天久は、これまでの取材で一度も声を荒げたことがない。
「私が新しい仕組みを使ってまたベビーホテルを始めようとするのは、取材の間、ずっと、中洲の子どもはどうするんですかって、あなたに言われてきたからですよ」
どろんこ園は深夜二時まで。しかし、その時間に閉まるのでは、中洲の繁華街で働く女性たちは子どもを預けられない。待機児童にもなれない“見えない子どもたち”をどうするのだと、三宅は知らず知らずのうちに天久を責めていたのだ。
この本を読みすすめながら、ぼくの中に、黒い感情がわき上がってきた。
こうした状況を劇的に変えられるのは、政治の力である。しかし、国政に出ている彼ら、彼女らの多くは、血縁により「職業」として政治家になった“世襲”の人間たちだ。
子どもの頃から政治家の家に生まれて、ぬくぬくとした温室で育ち、まともな本も読まず、しかしそれなりの学歴を与えられ、見た目は爽やかで中身はからっぽ、口当たりのいい演説を垂れ流し続ける、世襲政治家たちに、見えない子どもたちを思いやる想像力があるのだろうか、と。
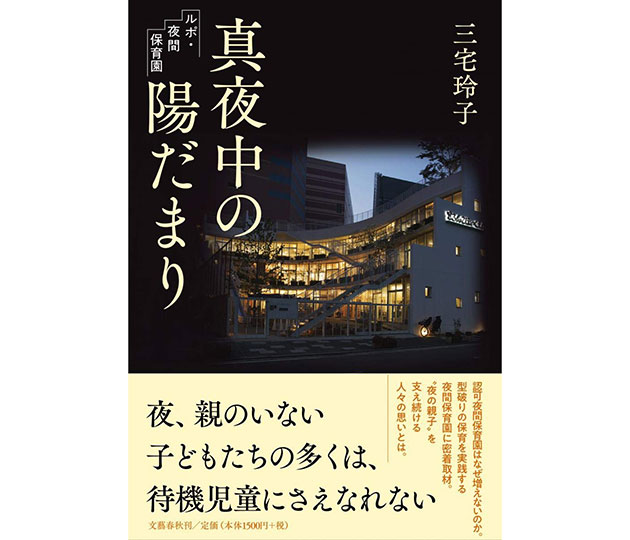
『真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園』文藝春秋
三宅玲子/著

