2020/03/05
横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店
『たおやかに輪をえがいて』中央公論新社
窪美澄/著
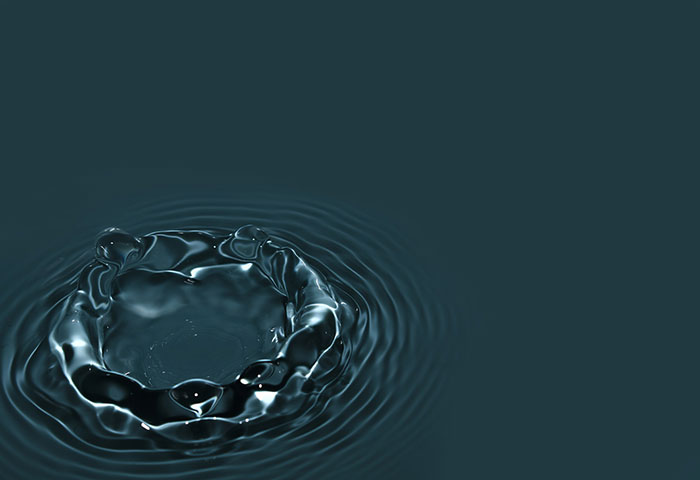
クローゼットの床に落ちていたのは見覚えのないカラフルなカードだった。絵里子は目をしばたかせながら、そのカードに手を伸ばす。それは風俗店のポイントカードだった。
このカードはきっと夫のものなのだろう。けれど、絵里子はそうなのだと思うことがどうしてもできない。帰りも遅く休日に仕事をすることも増えたけれど、毎日きちんと家に帰ってくる。それに、夫は結婚する前から性に淡白な方だったのだ。そんな夫が、こんな店に行っているはずがないではないか。
主人公の絵里子はパート勤めをしている52歳の主婦で、結婚してそろそろ27年が経つ夫の俊太郎と、20歳になる娘の萌と三人で暮らしている。家と職場を往復する何の変哲もない日々だが、さしたる不満はない。このありきたりで平凡な暮らしは、たった一枚のカードを見つけてしまったことで徐々に綻びはじめていく。いや、その出来事は単なるきっかけだったのかもしれない。
夫の俊太郎とは、絵里子が父の看病のため病院通いをしていた頃に、立ち寄っていたバーで出会った。彼は、いつも一人で難しい顔をして本を読んでいた。ハリネズミみたいに全身に棘をまとい、誰も近づいてほしくないと訴えているような彼と言葉を交わすようになったのは、ある雨の日の出来事がきっかけだった。店を出て、突然の雨に途方にくれる絵里子に傘を差しだしてくれたのが、俊太郎だった。その傘は黒い布地に「サカイ」と上手とは言えない刺繍が施されていた。
傘とお礼のハンカチを渡せたのはそれから随分経ってからだったが、二人は言葉を交わすようになった。絵里子は、最期を迎えつつある父の看病のため病院に立ち寄っていて、このバーが息抜きの場所であること。父と母は離婚していて、今は母と妹と三人で暮らしているが、自分だけが毎日仕事帰りに病院に寄っていることなどを話した。俊太郎の方も、離れて暮らす母が亡くなって東京と地元を行き来していたこと。仕事は飲料メーカーの営業職で出張が多いことなどを話してくれた。
二人のご縁を結んだのは本だった。絵里子自身は本を読まないが、父が読書家で古い本を大切に読んでいた。父の本を俊太郎に貸すようになり、二人は定期的に会うようになった。
決して饒舌ではなく、いつも怒ったような顔をしている人。でも、絵里子の話にはきちんと耳を傾けてくれ、そばにいると安心できる人。二人は数年付き合ったのちに結婚し、萌という娘にも恵まれた。
二人が出会ったとき、結婚したとき、娘が生まれたとき。二人でいるしあわせも、家族が増える喜びも、分かち合っていた時があったはずなのだ。でも今は、そんな日々から随分遠い場所に辿り着いてしまった気がする。でも絵里子は、本当は気づかないふりをしていただけなのかもしれない。
夫と娘が言葉を交わさないようになったのはいつからだっただろう?一人で夕食をとる日が増えたのはいつからだろう?夫と会話がままならないようになったのは、いつからだろう?いつから夫と、体を重ねていないのだろう?
見つけてしまったカードのことを問いただせばよいのだろうか?けれど絵里子にそんな勇気はないし、誰かに相談できるような軽やかさも身に着けてはいない。
でも、絵里子はこのまま悶々と日々をやり過ごすことを選ばなかった。それは、女性たちの様々な人生に触れたことがきっかけだった。
久しぶりに会った大学の同級生の詩織は、女性が好きだという自分に気づき、思い余って告白してしまった人に振られてしまった。その女性をこれ以上怖がらせないため、という理由で整形と、豊胸手術までした。男性と結婚していたこともある彼女だが、今は20歳ほど年下の女性の恋人がいるという。
家族に何も告げずに向かった旅先では、片方の胸がない美しい年上の女性と出会った。その女性は癌が再発してもう治療を受けたくないけれど、夫がその選択を許してくれず、せめてもと一人で旅行に来たという。自分は家族にも友人にも恵まれている。けれど、誰にも弱音を吐くことができない。私はプライドが高いから、と軽やかに笑う彼女の姿は絵里子の心を大いに揺さぶった。
そして、絵里子の母親の存在。母は絵里子の父と離婚したのちに二度再婚し、今は三回目の結婚相手と二人暮らしをしている。父と母の間に何があって離婚にいたったのかを絵里子は知らない。けれど、父が病に侵されたと分かったとき、母は見舞いにも行かず葬式にさえ参列しなかった。それに、これから三人で力を合わせて暮らしていこうとする矢先に、母は再婚した。長念許せないと思っていた母親だったが、本当は母のことを許したいと思う自分がいることにも気づく。
絵里子は妻と母という役割を全うし、その枠からはみ出ないように日々を生きていた。その場所の外に、しあわせがあるなんて想像もしていなかった。でも、絵里子が出会った女性たちは誰一人として同じ人生を歩んではおらず、それは人生には無数の選択肢があると教えてくれているようだった。
絵里子は明るい色に髪を染め、襟足が見えるくらい髪を切った。今までとは違う仕事も得て、自分の本当に好きなものを選択する暮らしを始めた。他人から見るとほんのささいなことだろう。けれど絵里子にとって、それはとても重大な決断で、同時に決意表明でもあった。
人生は続く。だから、丁寧に選びなおしていけばいい。これから夫とどんな関係でいたいと望むのか。娘とはどんな親子でありたいのか。絵里子は自分で決断する強さをいつしか身につけていた。
私たち女性にはきっと、自分たちが思うよりもずっと力がある。それは、命を宿し生み育てるという、女性という性に生まれた宿命とセットで備わっている力。時には許し、時には受け入れ、その上で自分の道をまっすぐ歩くのだ。一人で生きていく強さも、誰かとともに生きていく“たおやかさ”も持ち合わせている私たちだ。簡単ではないけれど、試してみる価値はある。
「そうなのだ」と確信に満ちた想いと同時に、胸に勇気の明りが灯るのを、いま私は感じている。
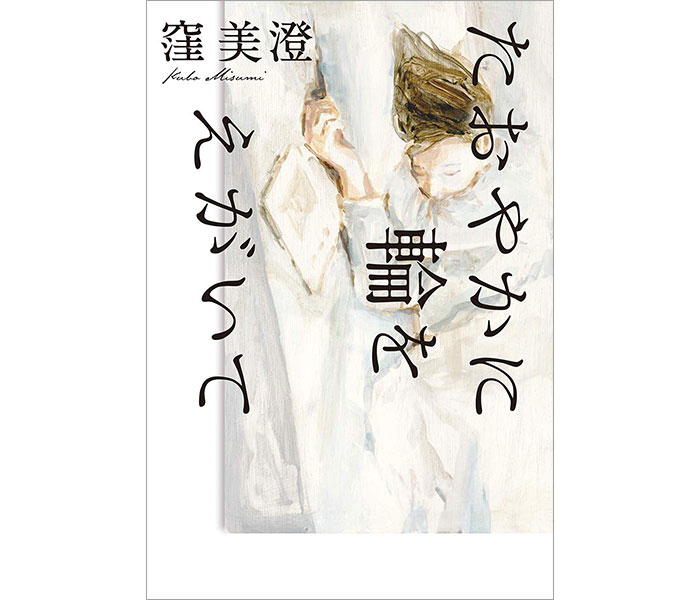
『たおやかに輪をえがいて』中央公論新社
窪美澄/著

