2020/09/28
吉村博光 HONZレビュアー
『友がみな我よりえらく見える日は』幻冬舎
上原隆/著

「友がみな われよりえらく 見ゆる日よ 花を買い来て 妻としたしむ」(『一握の砂』所収)
本書を開くと石川啄木のこの短歌がある。書名だけを見ると「自分を卑下する人々の本」のようだが、
ホームレス同然の生活を続ける芥川賞作家、五階から転落し両目を失明した市役所職員、容貌に自信が持てない独身OL…取材対象との距離を絶妙に保ちながら、無駄のない文章で心の拠り所を描いた素晴らしいノンフィクションだ。取材対象にとっての「石川啄木の花」にあたるものは何か。それがわかったとき、読み手の心はフワッと軽くなる。
生きていれば誰しも、いつかは自尊心の危機に見舞われる。窮地にありながら自分を取り戻す術を身につけていれば、人生はより生きやすいものになる。しかし、その術を手にするのは容易いことではない。万人共通の特効薬などはなく、
「がんばれ」とか「努力しろ」というのは簡単だ。しかし、底なしの危機におかれた多くの人にとって、「がんばる」こと自体が疑問なのだ。そっちにはもう意味はない。本書に登場する芥川賞作家は、高校生の頃に芽生えた精神世界の探求をすべく、浮浪者のような生活を受け入れている。受賞作のような作品を書けと励まされても、どうしようもない。
最初の「友よ」という話は、実際の著者の友人の話である。酔っぱらって5階から転落し両目を失明した47歳の友人は、著者が見舞いに行くと、老人のような姿でCDを聴いている。彼は、若いころ、必ず本を2~3冊むき出しで持ち歩いていたという。失明によって読書ができなくなった彼が見出した光とは何か。
最後の「リストラ」という話は、窓際にまわされ辞職を余儀なくされた6人の若者の話だ。ある時、彼らの会社は営業部署を新設し、500人の社員のうち80人をそこに配属させた。しばらくすると、机も引き出しのない長机に変えられた。会社に復讐するために6人は結束して闘った。その結果、彼らが手にしたものとは何か。
コロナ禍は、私たちを窮地に追いやっている。本書に収録された14の実話から、生きるヒントをもらえる方も多いと思う。できれば、自分にとっての「花」は何か、を考える視点を忘れないようにして読みたい。自分よりも辛い人がいるのを知り励まされたとか、自分も含めて人生は辛いことばかりだと感じた、という読み方はさみしい。
かつて、すべての人が同じ陽の光を目指して歩いている時代があったのかもしれない。しかし現代は、様々な方向から差してくる光を目指して、それぞれが歩いてゆく時代なのだと思う。ある意味孤独な時代なのかもしれないが、我々はそこにそれぞれの「花」を見出していくしかないのだ。
うつ病を患っている方に「がんばれ」という言葉をかけてはいけない、とよく言われる。本書の登場人物に「がんばれ」ということは、
そもそも、いまあなたの目の前にある「花」は本物なのだろうか。私が本書を閉じたとき、ある句が脳裏をよぎった。世間が当たり前の正月を寿ぐなか、それとは少し趣が違う我が身の幸せへの思いを込めて詠んだ小林一茶の句だ。
「めでたさも 中くらいなり おらが春」(『おらが春』所収)
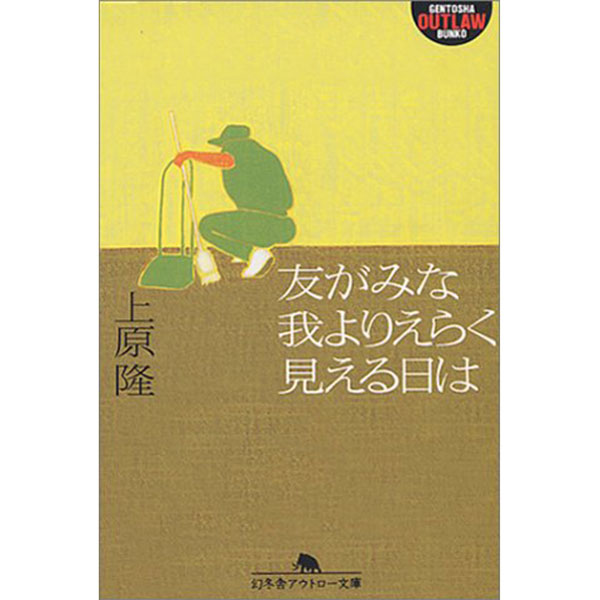
『友がみな我よりえらく見える日は』幻冬舎
上原隆/著

