2021/03/03
馬場紀衣 文筆家・ライター
『まなざしの装置 ファッションと近代アメリカ』青土社
平芳裕子/著

ファッションの中心にいるのは、なぜいつの時代も女性なのだろう。女性服と同じように、男性ファッションにも流行はあるし、オシャレ感度の高い男性もいる。にもかかわらず、街は女性のためのファッションで溢れている。だから当然、近代のファッション史は女性を抜きに語ることはできない。
産業革命を迎えた19世紀ヴィクトリア朝時代のイギリス、ロンドンでは雑誌やメディアに「お針子」がさかんに登場するようになる。この時代、財産権を持たない女性が自らの体面を保ちながら一人で生きていくためには、家庭教師になるか、あるいは「お針子」になるしかなかった。
1840年代、布地を服にするためには人手が必要だった。そこで求められたのがお針子たちだ。お針子の多くは少女で、彼女たちは14歳から帽子を作りはじめ、二年の見習い期間を終えるとより大きな流行品店で見習い職人として働くようになる。
彼女たちの労働環境は過酷だ。朝の8時から夜の10時までイスのうえで縫い続けても、一週間で稼げるのはせいぜい6シリング。その稼ぎの中から、蝋燭代や仕立物をプレスするための燃料代、石炭などの支払いを済ませると手もとに残るのは2シリング。しかも春の社交界シーズンには一日15時間、急ぎの注文が入れば18時間働くこともあった。明け方まで休みなく働かなくてはならないこともあり、たった2時間の睡眠さえ取れないお針子もいた。ファッションの需要が高まる中、お針子たちは美しく着飾るレディのために機械のように働いたのだ。
本書には、お針子たちの厳しい生活を表した絵や版画が紹介されている。1843年に出版された『針の奴隷』と題された小冊子には、お針子の健康状況を示した版画が掲載されており、長時間イスに腰かけたまま縫物をするために骨格が変形してしまった背骨のイラストが描かれている。
工場での労働環境の問題が高まると、お針子たちの過酷な状況は社会に認知されるようになる。そして政府による委員会の報告を経て、堅固な階級社会での「作る人」と「着る人」の権力関係は崩壊していく。
本書は、19世紀前半から20世紀前半に女性誌やファッション誌、ショーウィンドウやミュージアムにおけるディスプレイの事例を取り上げながら、これらのメディアでファッションと女性との関係がどのように結ばれたのかを解明する。「飾る女性」から「縫う女性」「模る女性」「巡る女性」へと至る女性像の変容を辿っていくと、ファッションと共に生きてきた女性たちの、美しくも過酷な姿が浮かび上がってくる。
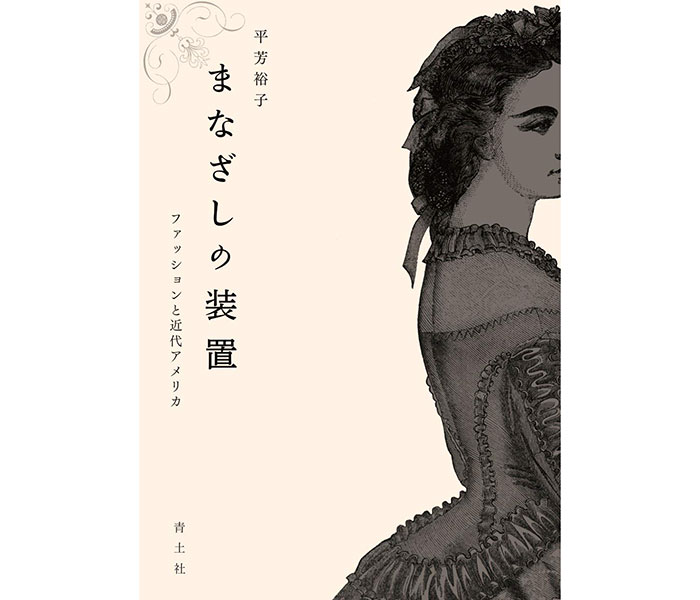
『まなざしの装置 ファッションと近代アメリカ』青土社
平芳裕子/著

