2022/08/24
横田かおり 本の森セルバBRANCH岡山店
『パパイヤ・ママイヤ』小学館
乗代雄介/著

これは、わたしたちの一夏の物語。
他の誰にも味わうことのできない、わたしたちの秘密。
ここからはじまる物語は17才の少女のきらめきを克明に切り取る。
そのまばゆさは夏の太陽のようなエネルギーに満ち、時に直視できないほどだった。
青春を思い出すなんてひと言で決して語ることはできない。
“あの夏”を知っているだなんて、口にすることも憚られる。
分かったつもりで語ることは彼女たちを蝕んできた「悪」に私自身が加担してしまうことだと思うからなおさら。
だからこそ私は傍観者の立場のまま、受け取った物語をもう一度世界に表出させる。なるべく透明な存在であれたなら、彼女たちの傍らにいることが許されるのではないかという希望とともに。
それがどこにでもいる少女のありふれた物語であったとしても――
この物語について語らなければという強い衝動が私を突き動かしている。
六月の終わり、午後五時を回って暑さは少しゆるんでいた。海辺の町の片隅にある、田んぼと笹薮に挟まれた細い道は、陽光をさえぎられて薄暗く感じられる。
そこを一人、パパイヤが歩いてくる。
「そのまま小櫃川(おびつがわ)の河口まで来て、木の墓場みたいなとこ」
初めて会う少女たちの待ち合わせ場所としては、いささか不釣り合いで不穏な空気さえ感じられる情景が脳内を駆ける。
引き返すことだってできた。誰とも知れない不審さを理由にすることは簡単だった。
でも。
「ママイヤ?」とパパイヤは言った。
ちょっと笑って、ぶら下げていた足を引き上げてから、わたしは言った。
「ほんとに来たんだね、パパイヤ」
SNSを通じて出会ったパパイヤとママイヤの名前は「パパ嫌」「ママ嫌」という一見冗談に思えるハンドルネームからなる。しかし、二人で過ごす時間が増えるほどにその名前に託したはずの軽さは鳴りを潜め、笑いに落とし込まないと耐えられない重さがふたりの肩に伸し掛かっていたと知る。
木の墓場で本を読んだり写真を撮ったりしているというママイヤの日常には他者の気配がなく、女子高生の生活というものが微塵も感じられない。
長身を生かしバレーボール部で活躍するパパイヤは、こんがり焼けたすらりと伸びた手足をどこか持て余したまま。
まだまだ知らないことばかりで、語れないことは胸の中に多分にあった。
けれど、とりとめもない会話は途切れることなく続き、時おり起こる笑いが二人を無垢な少女の姿にかえす。時計の針は緩慢な動きで、この夏は永遠に終わらないように思えた。
同時に現実が肩を叩いて夢の時間がいつ壊されるとも知れない予感があっただろうか――
「写真撮ろうよ、記念に」
ママイヤは再びカメラに手を伸ばしたのだった。
打ち捨てられた場所に来訪者が現れる。
こちらからの質問には一切答えず挙動不審なまま不思議な絵を描き上げた少年。彼の目には本当に空が黄色く見えていたのだろうか。
まるで神の使いのように二人の前に現れた少年の実態は知れずしかし、その後に現れる人物へとつながる足跡を残す。
どう見てもホームレスという出で立ちの老人が、水の引いた前浜を歩いている。
「それ、拾っていいか」
「だからもう、きいれえもんを集めようと思ったの」
怪しい老人の突然の乱入にパパイヤとママイヤは警戒心を募らせる。しかしとにかく「黄色いもの」を集めているという老人の強引なマイペースさにすっかり調子を狂わされた二人はこう名乗ったのだった。
「わたしは、ママイヤ」
「ウチは、パパイヤ」
「オレは、所」
「ジョン」
何がそうなってこうなったのか。朧げな記憶を脳裏に浮かべつつ思いつきを口に出したということが透けて見えるような思考回路と、所ジョンの誇らしげな顔の激しいギャップがおかしさにさらに拍車をかける。
自転車に乗らないままパパ抜きの人生を送ってきたママイヤ。
酒の種類に詳しくたまにケータイを止められるパパイヤ。
そこにはそれぞれが抱える家族の問題が潜んでいて、「知りたい」と思う傍観者は先へ先へと急ぐ気持ちがとめられない。しかし、彼女たちを急かすようなことがあってはならない。二人の間にたゆたうように流れる時だけが彼女たちの口を開く魔法を要したものだった。
一人で多くの時間を過ごすママイヤ。
雑多な感情渦巻く学校という場所では本当の自分ではいられないと感じるパパイヤ。
背負ってしまった秘密は誰にも打ち明けてこなかった。そこに至るまでの過程は自然なようでいてやっぱり複雑で、周りを見渡しても同じ境遇の友は一人もいないように思えた。
抱えるには重すぎる。かと言って言葉にするのは容易くなく、どうやっても長々とした自分語りになってしまう傷の吐露に耳を傾けてくれる人なんてきっといない。
期待と失望を繰り返しやがて諦念にいたるには、二人は若すぎたというのに。
夏はまだまだ終わらない。
少年が描いた絵を探す旅。あの日衝動的に海に投げ入れてしまった絵入りのペットボトルを探すことになったのは、所ジョンの出現によるものであったし、二人が出会うことで生まれたあらたな潮流に飛び込んだからだ。
二人には時間が必要だった。家族の呪縛から逃れ、どこにも居場所を見つけられない集団から距離を置き、贈られた名前すらも捨て。
二人の少女は、無意識に、けれど確かな足どりで浄化の旅へ進んでいく。
本当に楽しそうに、私の頭の上で指が弾んだ。悩みってなに。ぼうっとする頭がどうにか考えているうちに、パパイヤの指はまた小さな円を描き始める。
「それで、初めて思ったからちょっと変なんだけど」そこで頭を撫でる手が止まった。
「なんか、なりたい自分だって気がするんだよね、あんたといる時だけ」
ママイヤは、泣いた。子供のように大きな声を上げて。
寂しくて悲しくてやり切れないのに、抱きしめてほしい人は高く明るい場所からわたしを突き放した。ママイヤは才能溢れる母とは違いすぎる「普通」の自分を捨ててしまいたかった。
パパイヤは、そんなママイヤを抱きしめた。
明るくリーダーとしても振舞えるパパイヤの家では、父が酒に溺れそれは過去の自分の不甲斐なさが原因だと自らを責め、そしてこんな苦しみを友人に打ち明けられるわけもなく。
同じ学校にいたら友達じゃないかもしんないね。
うん、そうかもしれない。
写真って、思い出を巻き上げるみたい。
でも、ちょっとだけ強くなったから。
忘れちゃダメなんだと思うよ。自分が自分だってこと。
変わったことは、少し優しくなれたこと。
「でもさ」ふいにパパイヤが言った。「あんま期待しちゃダメだからね」
「どうして?」慌てて子供みたいな声が出た。
「そんな奇跡とか夢みたいなことって、めったに起こんないんだから」
「そうかな」「そうだよ」
「わたしはそうは思わない」「なんで」
「この夏、奇跡みたいなことばっかり起こって、ずっと夢みたいだったから」
奇跡は二人が出会ったことから始まっていた。
似たような傷を持つ二人が本当に会うことにどれほどの勇気がいっただろう。
この夏に自転車を乗り回しながら黄色い空の絵を二人で探すことになるなんて、想像もつかなかった。
ママイヤの心もとなさ。パパイヤの葛藤。
過去の痛みが二人を引き合わせてくれたのなら、それは、その傷は、もう「ギフト」だと言い切ってもいいだろうか。
笑って、笑って。泣いてもいいよ。
あなたのいる景色のすべてを、わたしは切り取っていく。
弱いわたしはほんの少しだけ強くなって、あなたの姿を見つめてく。残していくから。
どうか、これからも。
このままいよう。
ママイヤが撮った写真には二人の思い出が夏の太陽の光とともに閉じ込められている。
でも、それはもう呪いではない。
呪いを打ち破り、そこから脱却した二人が真の瞳で捉えた景色を瞬間的にただ切り取っただけのものなのだから。
私は二人の物語を知らない。
傍で見ることは叶わず、意外にも多すぎない写真ですら想像の中で覗き込むしか術がない。
でも、私には17才の少女たちの苦悩や悲しみや葛藤が見える。
けれどそれ以上に、光輝く希望をその手に取り戻した彼女たちの姿が見える。
尽くされた言葉と繊細で力強い物語によって、今私は彼女たちとともにある。
そんなことがただただ嬉しいなんて、私はきっとどうにかしている。
でも、心の底から叫びだしたくなるようなこの喜びは。
リズムも型も滅茶苦茶なダンスを踊りだしてしまいそうなこんな幸福は。
まぎれもなく物語が私に享受してくれたものだ。
私はこれから先、二人の姿を何度も思い出すだろう。
駆けり転び。
花のように笑い。夕立のように泣き。
生命のまぶしさあふるる二人の姿を思い出してしまうだろう。
その輝きを自分の中にも見つけられた時、物語を抱えて私はまた泣いてしまうだろう。
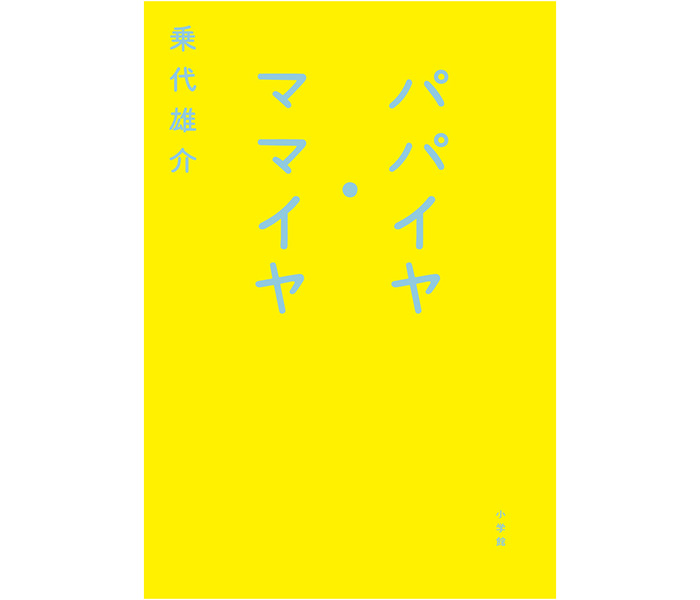
『パパイヤ・ママイヤ』小学館
乗代雄介/著

