2018/09/25
清水貴一 バーテンダー・脚本家
『死と生』新潮新書
佐伯啓思/著
本書は、人類史上最大の謎である「死」をテーマに、稀代の思想家と呼ばれる佐伯啓思氏が、混沌社会の現代に問う、衝撃的な思想書だ。
恥ずかしながらわたしは著者の名前すら知らなかったのだが、「死と生」というタイトルに違和感を覚え、本書を手に取った。なぜ、「生と死」ではなく、死が先に銘打たれているのだろうかと思ったからだ。
著者は、まえがきにこう述べている。
「高度な情報、産業社会にあって、生と死の問題についての関心をもてなくなっているのです。共通了解としての死生観などなくなってしまった時代には、われわれは、みな、自分の死生観を自己流に探し出すほかないのでしょう」
「本書は私なりの死生観の試みです。結論などというものは出るはずもありません」
という言葉に、好奇心をくすぐられた。
当然だが、生きている人間は、男女、貴賤、人種、美醜、善悪に関わらず、平等に死が訪れる。死から逃れられる者など、歴史を振り返っても一人といない。
死は、この世の生において絶対的であり、完全無欠の存在なのだ。だが、死が絶望の象徴として君臨し続けているからこそ、人類は死を覚悟し、限りある生を燃焼させてきたのではないか。そして、せめて苦しみを和らげる方法はないものかと、先達は叡智を結集させて、試行錯誤を繰り返しながら死と向き合ってきた歴史ではないのだろうか?

たとえば酒がそうだ。わたしはバーテンダーで、酒を売り、飲ませるのが商売だ。「酒でも飲まねえとやってられねえぜ」という定番のセリフがあるが、楽しさというより、「苦しみ」や「哀しみ」を紛らわせ、互いに寄り添うものとして親和性が高いのではないかと思っている。そして、酒は「忘却」とも親友だ。死を見つめるのが、死と向き合うのが怖くて、それをなんとか束の間でも忘れるために人類は酒を発明したのではないか。その証拠に文明や人種は、異なる場所で形を変えて酒を発明している。
そして、わたし達が真に怯えるのは「死」ではなく、「死に方」にあるという本書の指摘にも唸らされた。それは、近代の家族という形が崩壊へと向かっている上で、人は一人で死ぬことはできないにも関わらず、看取ってくれる家族がいなくなるという現実。死なせてくれる者がいないというのは、考えられる限り最も恐ろしい状況ではないか、と著者は言う。
本書で紹介されている、須原一秀氏や、評論家の西部邁氏は、明瞭な自己意識での意図的な死を選択している。現代の死の価値観として、老いて身体が不自由になり、自らの意思ではどうすることもできなくなる前に、潔く散ることを選択できる精神は、敬服に値した。わたしがもし無事に老年を迎えることができたなら、この境地に至る精神を備えておきたい。
本書の中に、トルストイの逸話も出てくる。「人生は無意味だ」という真理にいったんは辿り着き、自殺も考えながら、この世界的大文豪は人生観を大きく変えていくのだが、その思考も履歴も興味深かった。
最後に、著者の示した古代ローマの哲人、セネカの言葉を引用したい。
「何かに忙殺されている人間は、忙殺されているうちに、稚拙な精神をもったまま、何の準備もなく、いきなり老年に襲われる。そこであわてて、この老人は、わずか数年の余命を乞い求め、空しい若作りで老いをごまかそうとする。しかしそれでも病気や衰弱が襲ってきて、死を思い知らされる。そのときになって、怯えながら末期を迎え、自分の人生はおろかだったと後悔するのだ」
まさに、わたしのことを言われているようで、心に沁み入った。
今夜は酒を飲まずには、いや、誰かに注がずにはいられない。死生観について必ず誰かと話したくなる恐ろしくも深い一冊だった。だが、酒の肴にするには、少々劇薬かもしれない。
本書に登場する「あわせて読みたい」3冊
◎『イワン・イリイチの死』光文社古典新訳文庫
トルストイ/著
◎『人生論』新潮文庫
トルストイ/著
◎『自死という生き方 覚悟して逝った哲学者』双葉社
須原一秀/著
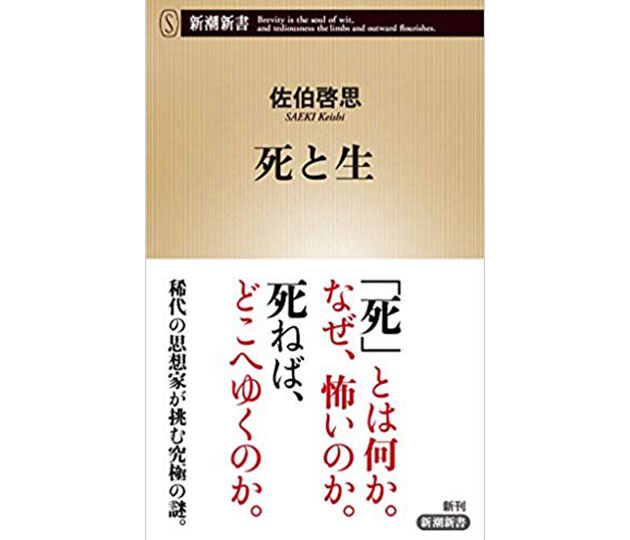
『死と生』新潮新書
佐伯啓思/著

