ryomiyagi
2020/08/01
ryomiyagi
2020/08/01

浜田寿美男『虚偽自白を読み解く』(岩波新書)2018年
連載第46回で紹介した『あやつられる難民』に続けて読んでいただきたいのが、『虚偽自白を読み解く』である。本書をご覧になれば、いかなる心理局面で無実の人間が犯行を自白するのか、なぜ彼らは自発的に「犯人」を演じるようになるのか、どうして「冤罪」の構図が生じてしまうのか、明らかになってくるだろう。
著者の浜田寿美男氏は、1947年生まれ。京都大学文学部卒業後、同大学大学院文学研究科博士課程修了。花園大学教授、奈良女子大学教授を経て、現在は奈良女子大学名誉教授・立命館大学特別招聘教授。専門は発達心理学・法心理学。とくに冤罪事件における自白や証言の心理研究で知られ、『取調室の心理学』(平凡社新書)や『心はなぜ不自由なのか』(PHP新書)など著書も多い。
さて、1990年5月12日午後7時頃、栃木県足利市内のパチンコ店で父親がパチンコをしている間に、同店の駐車場で遊んでいた当時4歳の女児が行方不明になった。その翌日、窒息死した全裸の女児の遺体が渡良瀬川河川敷の草むらで発見された。
栃木県警察本部は、この「足利事件」の捜査本部を設置して総勢180人余りで捜査に当たった。そこで浮上したのが、事件当時、幼稚園送迎バスの運転手だった菅家利和氏である。警察は、ゴミ袋の中から菅家氏の体液の付着したティッシュペーパーを押収し、女児の衣服に付着した精液のDNA型と合致するとの鑑定結果を得た。
1991年12月1日午前7時頃、菅家氏の自宅を訪れた警察官数名が、菅家氏に任意同行を求めた。一人の警官が女児の写真を取り出して、菅家氏に突きつけ、「謝れ」と怒鳴った。新聞で事件のことを知っていた菅家氏は、「どうしていいのか分からなくて、混乱しながらも、静かに手を合わせました。女の子の冥福を自分なりに祈ったつもりですが、そこから彼らはまた『やっただろう』と何度も怒鳴りつけてきました。何度も『自分はやっていません』と言ったつもりですが、こんな目に遭う理由がさっぱり分からずに、自然と涙があふれてきました」と述べている。
そのまま足利署に連れて行かれた菅家氏は、取調室に入れられた。この日は日曜日で、菅家氏は勤務先の幼稚園の先生から結婚式に招待されていたため、行かせてほしいと何度も取調官に頼んだが、拒絶された。ここで重要なのは、取調官が全員、DNA型の鑑定結果によって、菅家氏が真犯人に違いないと信じ込んでいた点である。
菅家氏によれば、この取り調べは、何時間も次のように続いた。「彼らは、自分たちにとって都合の悪い話には一切、耳を貸しません。『やっていません』と言っても、調べは絶対に終わりません。自分の言い分も、アリバイも、聞き入れてはくれません。『絶対にお前なんだ』と繰り返し、呪文のように言い続けるだけなんです」
「楽しみにしていた結婚式は、とっくに終わってしまっていました。昼と夕方に弁当を食べて、ぬるいお茶をすすっただけです。朝から一本もタバコを吸えずストレスも溜まります。『やったと言えば、楽になるぞ』と何度も言われました。……夜十時にもなれば、『もうどうでもいいや』というヤケクソな気持ちになってしまいます。……『分かりました。自分がやりました』とひと言、口に出して言いました」
それから裁判が始まり、2000年の最高裁判決により「無期懲役刑」が確定した。ところが、2009年に再鑑定した結果、当初のDNA鑑定が不正確であったことが判明し、彼の「無罪」が明らかにされた。菅家氏は、完全に「冤罪被害者」だったのである。
なぜ彼が「自白」したのかについては、本書の「虚偽自白過程モデル」で詳細に分析されている。取調官が「証拠なき確信」で犯人と決めつけて取り調べを行うと、どんなに精神が強靭な被疑者でも「虚偽自白」に追い込まれてしまうのである!
無実の人は、やっていないのだから「私はやっていない」とちゃんと言えば取調官もわかってくれるはずだと思う。にもかかわらず、いくら言っても取調官は聞いてくれない。だからこそ無力感に陥るのである。その点、開き直って嘘で否認している真犯人は無力感にさいなまされることはなく、それだけ自白に落ちにくい。このように無実の人の方がむしろ自白に落ちやすい要因がある。(P.37)
「真の自白」と「虚偽自白」の相違は何か、今後の取調官の「有罪立証」の方針はどうあるべきかを考えるためにも、『虚偽自白を読み解く』は必読である!
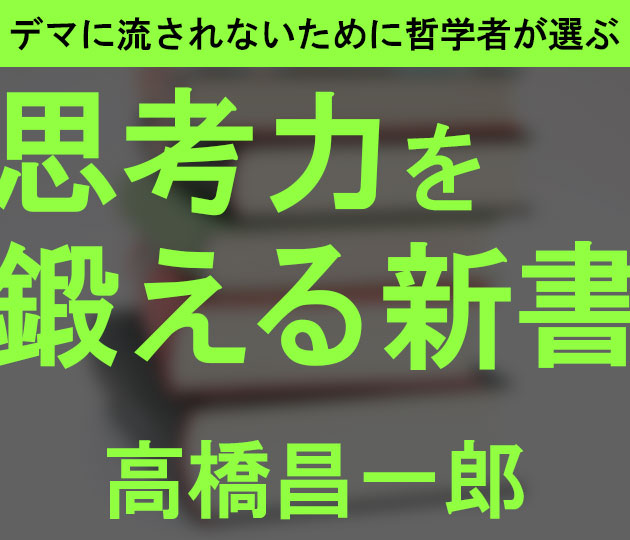
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.