akane
2019/09/27
akane
2019/09/27
藤崎慎吾 作家・サイエンスライター

30代までの筆者にとって、鯨肉といえば竜田揚げか大和煮だった。どちらも、さほどおいしいと思ったことはない。その印象が大きく変わったのは、「クジラ博士」こと加藤秀弘先生(東京海洋大学名誉教授)のおかげである。
作家になってから仕事がらみでお目にかかった際、単身赴任先のご自宅でミンククジラの「尾の身」をふるまってくださった。鯨肉では最高級の部位で、筆者のような貧乏人がそうそう口にできるものではない。刺し身でいただくのだが、大トロにも負けない濃厚な味だった。また別の機会には鍋で食べさせていただいたのだが、この時もついつい箸が進んでしまい、意地汚い私は翌日まで腹が張っていた。
ご存知の方は多いと思うが、今年の7月1日に商業捕鯨が再開され、すでに釧路沖ではミンククジラ漁が始まっている。早ければ9月末にも捕獲枠の上限に達する見通しらしい。また三陸沖などではニタリクジラ漁が行われている。しかし今のところ筆者の近所のスーパーに、鯨肉が出まわっている気配はない。我が家でも尾の身や鍋を味わえる日は来るのだろうか。
そんな思い切り庶民的な疑問も頭に浮かべつつ、8月の暑い日、筆者はクジラ博士が昨年まで教授を務めておられた東京海洋大学(品川)に向かった。同大付属の「マリンサイエンスミュージアム」で、お話をうかがうためである。博士は商業捕鯨の再開について、かなり憂慮されているという事前情報を得ていた。鯨肉のうまさを教えられた身としては、ちょっと聞き捨てならない。
マリンサイエンスミュージアムには、セミクジラとコククジラ、そしてドワーフミンククジラの全身骨格がある。圧巻なのは別棟にあるセミクジラなのだが、そこには冷房がないため、博士は涼しい本館の一階ロビーで白いものの混じった顎髭を撫でておられた。そこから2階に移動し、マグロの兜焼きのようにどんと置かれたミンククジラの頭骨と、クジラ全種の模型が展示されている一隅で、筆者は博士と向かい合った。

「また、おいしい鯨肉を腹いっぱい食べたいんですが……」と切りだしたい気持ちを抑えつつ、まずは日本の国際捕鯨委員会(IWC)脱退から、商業捕鯨再開に至った経緯について質問してみた。博士はIWCの科学委員会に40年以上も関わり、プロジェクトリーダーや分科会議長などを歴任してきた。科学者なので政治的なやり取りには関わっていないが、もちろん我々、一般人よりはずっと内情に通じている。そうした体験も含めて、海洋哺乳類学者としての半生を振り返りつつ書かれたのが『クジラ博士のフィールド戦記』(光文社新書)だ。
最初は「IWC脱退と商業捕鯨再開? 知っていることは全部書いたから本を読めよ」と言いたげな口ぶりだったが、「そこを何とか、かいつまんで」とお願いした。すると博士はIWC誕生前夜の話から、とうとうと語り始めた。
「第2次大戦後の1946年、主に戦勝国が集まって『国際捕鯨取締条約』を結んだんですね。批准のため2年据え置かれ、1948年に発効しましたが、その条約の下にできた国際管理機関がIWCです。戦前にも国際連盟が主導したジュネーブ協定の下に『国際捕鯨協定』があったんですけど、これはあまり機能しなかった。簡単に言うと、その反省のもとに国際捕鯨取締条約では、3つの柱を立てました。鯨類資源の適切な保護と管理、そして捕鯨産業の健全な育成です」
敗戦国だった日本は、戦前からの主要捕鯨国ではあったが、当初その「仲間」には入れてもらえなかった。連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の「思し召し」で加盟を許されたのは、1951年である。サンフランシスコ講和条約の発効が1952年なので、いわば戦後初めての国際舞台復帰がIWCだったわけだ。その背景には食糧難の日本で、多くの餓死者を出さないようにというGHQの思惑があったのだという。

「捕鯨というのは、いわゆるインフラが整っていないとき、それから食料の流通機構がよくできないときには非常に効率がいいのでね。魚はいろいろ集めてきて、それをどうこうして売るという格好ですけど、鯨は肉ごと来てくれるわけですよ。要するに、お魚屋さんというよりは、お肉屋さんがそのまま来てくれると。で、1頭捕るわけじゃないですか。消費地にいちばん近いところに持っていって、そのまま卸しちゃえばいいということなんです。だから魚を買い集めたりするよりは効率がいいですよね。私は『給食効率』と勝手に呼んでいるんですけど」
当時は捕鯨母船が徴用時に軒並み沈没したこともあって、潜水艦母船だった海軍特別輸送艦が捕鯨母船代わりに使われた――というような話が、この後に続いた。それは早送りで飛ばすことにする。
「国際捕鯨取締条約の目的は、今も変わっていません。現在、日本は脱退しましたけれども、この条約の下に色々な運用規則を定めて、捕鯨操業を管理していたわけですね。条約を変えるためには、締約国会議というのを招集して、そこで議論をして、合意していけば変えられるわけなんですけど、未だに変わっていない。これが今回のことにも、実はつながってきます」
適切な資源の保護と管理、健全な捕鯨業育成を柱にしていたIWCが、今はどのような状況になっているのだろうか。
「IWCの発足後、しばらくは捕鯨国主導の会議運営が続いていました。しかし1970年代の前半あたりから欧米諸国が捕鯨から撤退し始め、世界的に鯨類保護の機運も高まり、反捕鯨国の加入が相次ぐようになりました。やがて捕鯨国は少数派に転落。そして最も反捕鯨国の多かった1982年に、商業捕鯨モラトリアム(一時停止)提案が、有効投票の4分の3を得て採択されてしまったわけです」
ノルウェーなどは「異議申し立て」をして商業捕鯨を続けた。一方、日本は米国から経済制裁を受けたため、モラトリアム決議を受け入れて捕鯨を中止した。その後、捕鯨国と反捕鯨国は、それぞれに多数派工作をしかけていく。
そして2000年代に入ると、再び捕鯨国(持続的利用支持国)が増え始めた。沿岸で小型鯨類(イルカを含む)を捕ったり、クジラによる漁業対象種の「食害」に悩んだりしているカリブ海や西アフリカの発展途上国、そしてアジア諸国が加盟するようになったからだ。その結果、2006年には捕鯨国が反捕鯨国を、わずかながら一時的に上回り、商業捕鯨再開決議が採択された(といっても、実際の再開に必要な4分の3の票は得られていない)。しかし、以後は押したり引いたりをくり返し、両勢力は膠着した状態に陥っている。
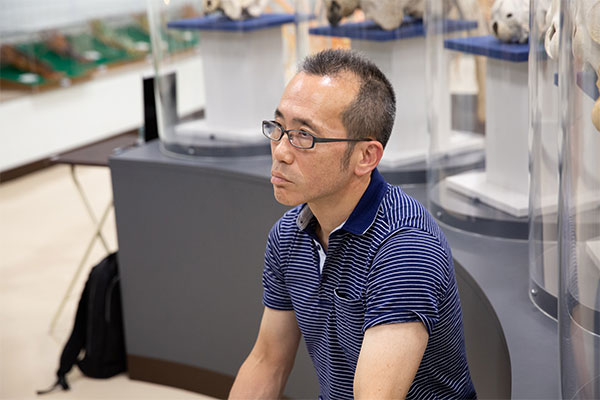
「詳しくは『クジラ博士のフィールド戦記』をお読みいただきたいのですが、IWCの正常化に向けて色々な調停もありました。しかし、もうここ7、8年は全く機能していなかったですね。ただ会議を開いているだけ。それに関連して一番がっかりしたのは、オーストラリアの代表が『クジラがどれだけいても、どんなに(資源が)健全であっても、もはや捕鯨をすることは許されない』と言ったことです。IWC科学委員会でクジラの適切な資源管理方式を長年、研究し続けた者としては、この上なくやるせない」
適切な資源の保護と管理というのは、平たく言えばクジラが減らないように、うまく利用していくということだ。そのために博士らは調査捕鯨などを通じてクジラの資源量(生息数)を解析し、どの程度なら捕っても大丈夫かを科学的に推定しようとしてきた。その最終的な成果が改定管理方式(RMP)である。
RMPは1994年にIWC総会で承認された。ところが、それを運用するための改定管理制度(RMS)については、20年近くの議論を経ても合意できず、未だにRMSは採用に至っていない。したがってRMPも使われていない。そこに、あのオーストラリア代表の言葉だ。これは条約に同意できないと言っているのと同じで、同国こそ、条文がそのままのIWCに所属しているのは矛盾している。だが結局、脱退したのは日本のほうだった。その理由や今後の方針については、2018年12月26日付の内閣官房長官談話を参照されたい。
「脱退については、やむを得ないと思いました。もう万策尽きたという感じでしょうね」と博士は言う。しかし案じているのは日本よりも、むしろIWCのことらしい。
「大戦後の紆余曲折を経て、今日までIWCは鯨類資源の世界的な管理を担ってきたわけですよ。日本の脱退によって、ますます機能しなくなっちゃうんじゃないかというのが、僕のほうの心配ですね。日本がいなくなって清々したと言っても、今度は議論をする対象がなかなかないじゃないですか。資源調査をやってデータを出してきたのは、主に日本ですから。ノルウェーやアイスランドも出しますけど、かなりミニマムレベルですからね。日本は積極的に出してきましたので。そういうところがなくなって、果たしていったい科学委員会で何を、どうやってやるのかというのが、むしろ科学委員会の中から見ていて、みんな心配なんじゃないですかね」

おそらく財政的にも厳しくなる。IWC参加国はそれぞれ加盟金を支払っているが、一律ではない。先住民捕鯨による捕獲頭数のほか、国連と同じでGNPが基準となり、それぞれに応じた額が決められている。つまり日本はアメリカと並ぶ、大口のスポンサーだった。それが抜けてしまったとなると、残った国々の加盟金が引き上げられるかもしれない。もし同じままだったら科学委員会などの活動は縮小されていき、普通の学会と同じになってしまう可能性もある。だが今のところは、成り行きを見守るしかない。

株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.