BW_machida
2022/04/28
BW_machida
2022/04/28
『感染症としての文学と哲学』
福嶋亮大/著

パンデミックが急激なスピードで全世界を巻きこみ、人びとが終わりの見えない不安に襲われるなか、20世紀の疫病文学の金字塔、カミュの『ペスト』に注目が集まった。この作品はペストが流行して戒厳令のために町ごと監禁されたアルジェリアのオランが舞台で、医者のリウーを中心とした男たちの群像劇を描いた作品だ。
疫病を扱った世界文学は『ペスト』を筆頭にボッカチオの『デカメロン』、ダニエル・デフォーの『ペスト』、トーマス・マン『ヴェニスに死す』のほか、日本では小松左京『復活の日』など数多い。文学は疫病を作品の中心的テーマとすることで「作品を取り囲む額縁とする一方、医学的な認識モデルも随時取り入れて、世界の把握の仕方を更新してきた」と著者は指摘する。
たとえばパーシー・シェリーやジョン・キーツら19世紀イギリスのロマン派詩人は、結核に繊細さや優美さといったロマンティックな意味を与えた。アメリカの批評家スーザン・ソンタグは、ホメロスの『イリアス』やトゥキュディデスの『戦史』を挙げながら、疫病がかつては「管理」と「対処」の対象であったことを述べている。
疫病はときに文学表現のなかに入りこみ、特徴的なイメージを読者に提供する。19世紀ロシアの詩人プーシキンの『ペスト流行時の宴会』という詩は、ペストのもつ闇の力を礼賛したもので、彼はペストから「人類再生のための悪魔的な力を引き出そう」とした。また、フランスの演劇人アントナン・アルトーは「演劇はペストのように、世界からその『潜在性』を引き出すもの」であると論じた。プーシキンやアルトーが語るのは現実のペストではなく、観念としてのペストである。
では新型コロナウイルスもやがて文学的記号となり得るのだろうか。著者はこれに懐疑的だ。かつてペストが黒死病として恐れられ、結核がロマン主義と結びついたような意味的結合は生じないのでは、と述べている。人類すべてが標的となる現代のパンデミックにおいて、新型コロナウイルスは特定の何かを意味することなく、増殖と変異を繰り返すというウイルスのもつ純然たる機能だけが際立つからだ。
「パンデミックが教えるのは、われわれの未来が不確実であり、かつ不条理でもあるという、ある意味では当たり前の認識です。トゥキュディデスにもデフォーにもトーマス・マンにも、善人だから疫病を免れるというたぐいの人道的な認識はありません。危険なウイルスがひとしきり流行した後、ある人間はたまたま生き残り、別の人間はたまたま死んでしまう。いかなる哲学も文学も、この不確実性と不条理さを打ち消すことはできません。」
カミュやボッカチオが残した疫病文学は21世紀のパンデミックのような異常事態を考える際に、今後わたしたちがいかなる精神的態度をとり得るか、その手がかりを与えてくれる。そんな予感から、人びとは不安に煽られるようにして物語へと手を伸ばしたのではないか。
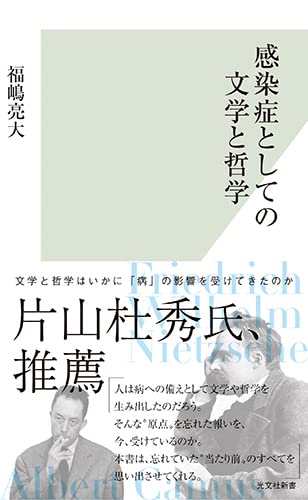
株式会社光文社Copyright (C) Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.