2019/05/13
吉村博光 HONZレビュアー
『無名』幻冬舎
沢木耕太郎/著

ウオッカが死んだ。父と観た最後のダービー。そのゴール板を真っ先に駆け抜けた馬だ。それまで混濁していた意識が一時的に晴れて、冗談さえも飛ばすようになった日曜の朝。私は父にダービーの出馬表を見せた。その1時間後、私は父の予想を握りしめ錦糸町にいた。
そこで購入した馬券は、スタートの頃にはいつものようにオデコに貼り付けられていた。「よおし、行け!」と言いながらファンファーレを聞き、二人でテレビ画面に見入った。それは、1週間前には想像すらできなかった、奇跡のような時間だった。
競馬以外にも、麻雀、釣り、パチンコ、卓球…たくさん遊びを教えてもらった。私は父の背中を追ってきた。しかし、ついぞ、その背中には追いつくことはできなかった。だが、今にして思えば、追いつきたくない、という思いもあったのかもしれない。
こういった機微を、ノンフィクションライターの沢木耕太郎は、自らの父の人生の軌跡を辿った本書『無名』のなかでこう述懐している。
たぶん私は父をいつまでも畏怖する対象でありつづけさせておきたかったのだろう。しかし、実際は、そう思ったとき、すでに父は畏怖する対象ではなくなっていたのだ。つまり、あらゆる意味において、反抗すべき父親は存在しなくなっていた・・・・・・。 ~本書より
沢木は自らの親子関係を「変則的なもの」と書いているが、私には共感する部分が多かった。私も何でも知っている父に対する畏怖心をもっていた。その一方で、守らなければならない存在のようにも感じていた。私は、まるで我が事のように本書を読んだ。
父の死の直後、仏壇の奥から出てきたのが本書だった。私はすでに読んでいたが、もう一度読み返してみた。父が本書を読むとき、その頭にあったのは祖父との関係だったのだろうか、それとも息子である私との関係だったのだろうか──。
戦後の混乱の中で、能力はありながら大学にいかず高卒で技術屋として身を立てた父。大学を出て机上の仕事をしている息子。裕福とはいえない家庭環境も似ている。もちろん私は著者と違って「無名」ではあるが、入社直後に、出張でパリには行っている。
薔薇の香やつひに巴里は見ざるべし ~本書より
『深夜特急』の最終目的地がパリ・ロンドンであることを知った、著者の父が詠んだ句だ。それにちなんで、私にも思い出すことがある。海外出張でパリに行くことを父に伝えたとき、父は嬉しさを隠すように、なんだか眩しいような表情を浮かべたのだ。
おそらく父は、私を思いながら『無名』を読んだ。そう確信したとき、私のなかに父の死が大きな塊となって入ってきた。それまで感じたことがないような激情が湧き上がってきて、私はその場に崩れ落ちた。それが、12年前の出来事だ。
今年は、亡父の十三回忌にあたる。その後私は、何度も本書から力をもらっている。ウオッカが死んで、平成も終わる。しかし、死者も、そして過ぎゆく時代も、永遠に消え去ることはない。私たちは、読み返すことで何度も出会えるのだから。
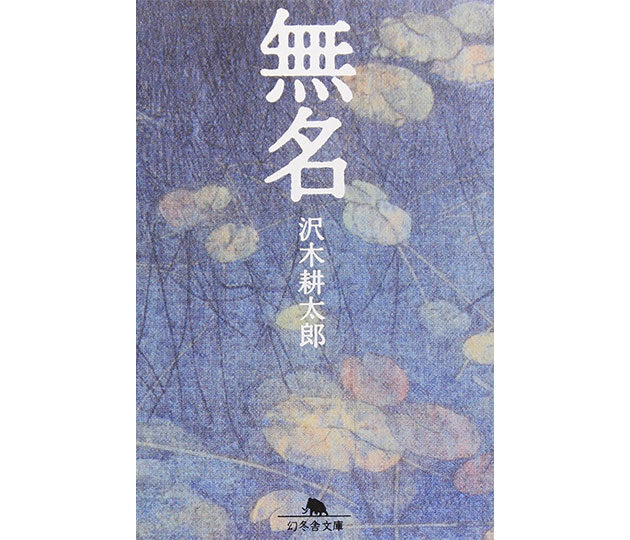
『無名』幻冬舎
沢木耕太郎/著

