2018/05/14
古市憲寿 社会学者
社会学者を困らせたかったら、「社会学って何ですか?」と聞くのがいい。それくらい「社会学」の定義は無数に存在し、しかもその多くは抽象的で理解しにくい。
何とか「社会学」のわかりやすい入門書を作れないかと思って、『古市くん、社会学を学び直しなさい!!』(光文社新書)という対談集を出したこともある。宮台真司さん、大澤真幸さん、上野千鶴子さんといった日本を代表する社会学者に、「社会学って何ですか?」と聞いて回ったのだ。
実はその時、どうしても対談の叶わなかった社会学者がいる。加藤秀俊さんだ。1930年生まれの加藤さんは、日本で初めて意識的に「社会学者」を名乗った一人である。
その加藤さんの新刊が発表された。その名も『社会学』(中公新書)。88歳の社会学者の、まるで人生の集大成のようなタイトル。重厚な学術書なのかと思ったら全く違った。非常に軽快な新書なのである。
加藤さんの考える「社会学」は極めてクリアだ。それは本来「世間学」や「世俗学」とでも訳すべきもので、「社会学」とは「世間話」そのものだという。実際、この本でも加藤さんの体験を交えた古今東西の「世間話」が展開されている。
「社会学」と名の付く本としては極めて異色だと思う。たとえば一般の社会学の教科書には、デュルケムやギデンズといった西洋の社会学者の学説紹介がひたすら羅列されていることが多い。しかし加藤さんはこれを「奇妙な習癖」と一刀両断する。
そもそも日本の「社会学」はどのように成立したのか。1877年に日本人として初の東京大学教授となった外山正一が「社会学ノ原理」という講義を行った。滞米中に親しんだハーバート・スペンサーという社会学者の最新刊の講読という内容だったようだ。1886年の帝国大学令の発効と共に、「社会学」は大学の中で独立した学科となった。
だが当然ながら「世間話」にはそれよりもずっと長い歴史がある。江戸時代には「江戸随筆」と呼ばれる膨大な雑記録が生まれたし、古くから旅人は世間話の運搬者として機能していた。
しかし、いいかげんな「世間話」では片付かない新しい状況が生まれた。人口が急激に増えたり、産業革命が起こったり、とにかく急速な「世間」の変化が起こったのだ。一般に近代化や産業化と言われる現象だが、この新しい状況に対応するために生まれたのが「社会学」である。
それでも「社会学」が「世間話」の延長であることにかわりないというのが、加藤さんの見立てだ。しかもその「世間」というのは、「わたし」にとっての「世間」でしかあり得ない。結局のところ「社会学」は「ちょっとばかり理屈っぽい世間話」に過ぎないというのだ。もっともその代わり、「読んでみておもしろくなければ落第」と手厳しい。
おそらく、日本にいる多くの「社会学者」は、この本を読んでも否定的な反応をするか、黙殺を決め込むと思う。あるいは怒り狂ったり、「時代が違うんだよ」と本書の発想を過去の遺物と決めつけるかもしれない。
なぜなら多くの「社会学者」は大学に所属し、広い意味で外山のスペンサー講読のようなことしかできないから。もしくは読んで面白い作品なんて書けないから。もちろんそれはそれで由緒正しい「社会学」のあり方でもあるのだろう。題名を出すのは控えるが、最近読んだとある社会学の論集は、窮屈すぎて息が詰まりそうな上、発見の少ない本だった。
比べて、加藤さんの「社会学」は自由で楽しい。
しかも活動期間が長いから、さらっと「わたしは帝国陸軍さいごの人間である」「友人のひとりにエヴェレット・ロジャースがいた」「パースンズ先生」の授業を「大学院生として傍聴していた」など、すごい話もぶっ込まれる。
もしこの本で加藤さんに興味を持ったなら、『メディアの発生』『メディアの展開』(ともに中央公論新社)という本格的世間話とでも呼ぶべき大著もおすすめだ。加藤さん自身が楽しんで「社会学」をしているのがよくわかる。そう、「社会学」はもっと面白くていいのだ。
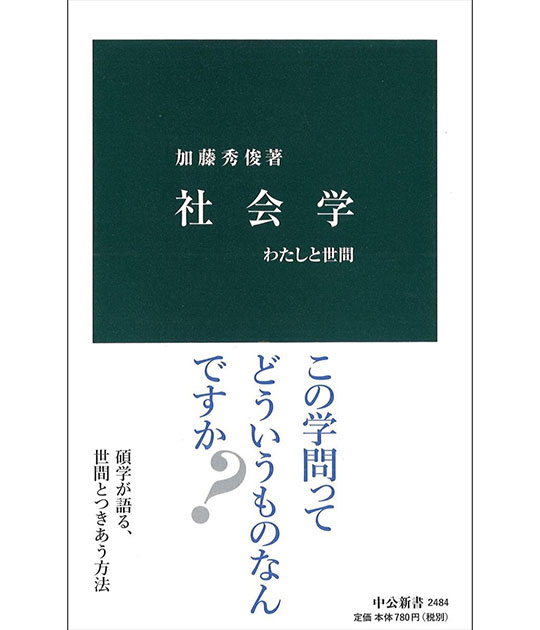
『社会学』中公新書
加藤秀俊/著

